 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
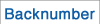 |
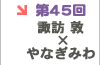 |
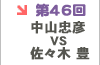 |
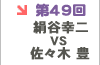 |
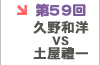 |
 |
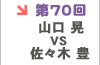 |
|
|
※画像はクリックすると拡大画像をひらきます。 |
 |

森村:私が最初に映像作品を作ったのは、1991年でした。そのころは遠慮があって自分の後頭部あたりだけを登場させていました。ですから顔はほとんど映っていません。もちろん声も出ていません。98年ころになると、アンディ・ウォーホルなどをテーマに映像作品を作りましたが、このときもまだサイレントでした。2000年に今度は、フリーダ・カーロをテーマにした映像を作り、言葉ではなくて音が加わりました。そして昨年の2007年、三島由紀夫をテーマとした映像作品によって、はじめて言葉が重要なメッセージになってきたといえます。というのも、1970年11月25日の陸上自衛隊市ケ谷駐屯地での三島由紀夫事件を扱っているものですから、演説という声の部分が必要でした。 |
 |
 |
●そうすると、今回の作品もチャップリンの『独裁者』の独白やレーニンの演説がテーマですから、三島由紀夫と同傾向で、言霊の力が肖像的な要素とともに最重要ですね。長い台詞ですが、アフレコはしていませんか。 森村:いえ、していません。多少のカンニングはあっても、ひとり芝居の流れが滞ったらぶち壊しですから、なんども取り直して編集をしました。 |
 |

森村:私はいま20世紀をテーマとしています。その前は、19世紀までが私の基本的な持ち場だった。21世紀の現在でもいろんな絵画はあります。でも、レオナルド・ダ・ヴィンチが『モナリザ』を描いたような時代の証言力というか、インパクトの強さは、20世紀に入るとずいぶん分散してしまい、小さくなってしまった気がします。絵画に代わって報道写真や映画・映像などが20世紀を語るときに、とても重要になってきた。 私は美術をテーマにしているわけですが、自分の中では19世紀まではそれが可能でも、20世紀に入ると美術や絵画だけでは収まりきらない多様性を感じます。そうなると、いろんなメディアを駆使するしかない。ジャーナリズムの写真にも喚起力の強い決定的な瞬間がある。それを私なりに検証したい。 |
|
 |
 |
| 森村:私は、「直感」でやっているだけですが、その直感が働かないと、推進力にならないようです。直感が表現の基本といってもいい。ただ、作品作りをしていくと、必ずいろんな問題が出てきて、はじめにイメージしていた着地点とはちがったものになっていく。それが面白い。ひとつひとつの過程を決めていきながら、かたちを結実していく作業の中で、新たな発見や意外性がうまれるからスリリングだともいえる。 レーニンの場合は、まず、ひとつの写真があった。その写真には多くの群集が写っていた。私のこれまでの手法なら、その群集のひとりひとりに私が扮装することも考えられたが、今回はちがうことを考えた。 |
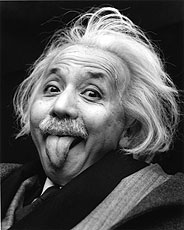 |

●上野のホームレスの人たちが、キリスト教関係者の慈善事業の差し入れで、まず一緒の賛美歌かなんかを合唱する場面にでくわすと、あまり気勢が上がっていない場面に出くわして、後に曳く。森村レーニンの演説に合わせてシュプレヒコールを上げている人々も、なんだか肩透かしで、それがかえってリアルだった。 森村:まさにそこですね。高齢者だから働きたくても職場がない。一時的に私が仕事として雇用する。ボランティアの学生を集めようとすれば、それも可能だった。俳優の卵を雇った方が、見栄えがよくて、それらしい元気のいい演技をしたかも知れない。私はそれでも20世紀の現実が欲しかった。だらだらやっているわけではないけれど、そんなに気勢は上がらない。それでもおっちゃんたちは何かの役に立っていることが分かってくれていた。強力な撮影ライトが当たって、自分たちに脚光が当たっているのを感じていたと思う。レーニンの立つ演壇を撮影するためには、手前の足場のしっかりした高い位置にカメラをセットしなければならない。そのセット作りを、おっちゃんたちは瞬く間に作りあげてくれた。工事現場で慣れたその作業手順は、感動的だったといってもいい。ここには昭和というが時代がしっかりと刻み込まれた顔があった。 |
森村:このレーニンが亡くなってから百年になります。その時代の違いを描くのが、私の関心事でした。 |
|
|

