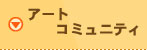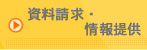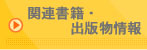植野氏の企図が実を結んでいる理由のひとつに、書道界が美術館での発表に偏した結果、その表現が展覧会芸術と化していることも挙げられないだろうか。作品が大型になり、また所属する団体が志向する表現の枠内にとらわれている傾向がほの見えるなど、現代に生きる我々の生活感覚との間に齟齬が生じているように思えてならないのである。
詩人で美術評論家の建畠晢氏が著書『ダブリンの緑』(五柳書院)の中で次のように指摘していることは暗示的である。「かつては注目すべき運動はアーチストの横の連携から生まれたきた。しかし今日では彼らの目は常に美術館の方を向くようになってしまっている。新しい動向はまだ萌芽のうちに、運動としての機運が熟成される以前に、美術館によって摘み取られ、スリリングな展覧会に仕立てられてしまう」。
書道界の力学とは一線を画す植野氏の取り組みは、かつての草庵茶道形成者たちが、唐物絵画が必須とされた従前の定則に縛られず、禅僧の墨蹟などを「茶掛け」として採り入れた大胆な発想を想起させる。キャレモジは現代版茶掛けの役割を果たしているといえるのではなかろうか。
|