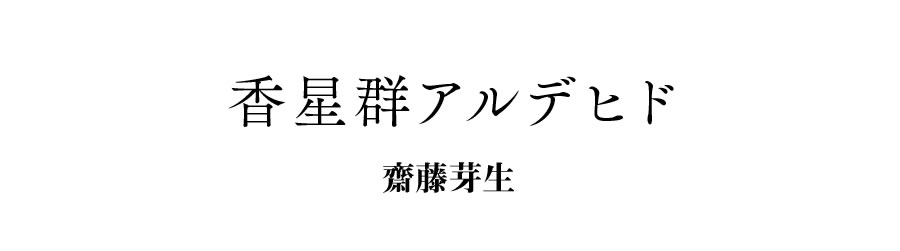20. 小石大の恋
青黒い疲労の影が帰宅の通勤電車を包む。戸口付近に佇む彼女がひときわ大きなその背丈で見渡すと、乗客は皆、漂流者のような顔をしている。
灰色や黒に包まれた男、男、男。彼女は考える。彼らにもそれぞれ妻子があり、そうなるまでの過程に各々なりの恋愛や出会い方があっただろう。とてもそうとは思えない、疲れた重苦しい存在の群れに、彼女は改めて押しつぶされるような思いがした。
身体の大きな彼女の傍には小柄な初老の男性が不機嫌そうに手摺につかまっていたが、ちょうどその男性の鼻先に彼女の肩が当たってしまった。男性はこの上なく不快なしかめ面で彼女を睨んだばかりでなく、あからさまに舌打ちをし、肘で彼女を邪険に押しやった。
すいませんと小声でいいながら(でも私はこれ以上小さくはなれないのに)と、普段いつも感じている引け目を必要以上に感じ、彼女は少し傷ついた。
仕事にも励み、快活で友人も多い彼女が、人生に何となく焦りを感じ始めたのは、多くの女性と同じく、三十歳を過ぎての漠然とした結婚や恋愛に関するものだった。
「もっと女としての自信を持てばいいのよ。人気者じゃないの。あなたさえその気になればいつだって恋愛出来ると思うんだけどな」
友人たちの意見はもっともだ。しかし判で押したようなその物言いの大雑把さに彼女自身飽き飽きしている。「あなたさえその気に」の気が本当に自分の内面からわき上がるのであれば、こんな焦燥も初めからない。
友人たちには言わずに、いわゆる「婚活」の催しに参加したこともある。しかし彼女にとっては、大学のキャンパスも今の職場もその様な場でも、同じように「何も起こらないくらいの適度な距離」を生む人の輪でしかない。熱心な親族が見合いを薦めて来たが、相手の男性と一対一になった時に、そのはかり知れない他人行儀の距離感を「結婚」の二文字だけで急速に埋める、という想像に、言いようのない虚しさを感じた。
「ええ?お見合い断ったことあるんですか。いやな相手ならしょうがないけど、正直、先輩は、自分が背が高いのを気にしてるんでしょう。俺みたいに小さすぎる男なんかからすると、かえって憧れますけどね」
よく言うことをきく後輩の男子社員は、抜け抜けと、賞賛でも愚弄でもないことを言いながら絡んでくる。つい口を滑らしたことで、自分の結婚や恋愛に話題の焦点が移ると、彼女はすかさずうまく話を切りかえし話題を移した。
しかし後輩の言うことは、まさに図星だった。彼女はどうしても、大きな身体を丸めて猫背になる。来るものは拒まない包容力を持っていても、自分からは殻を出ようとはしない弱さが彼女の中にあった。
電車が主要駅に止まると、大波に揺られた舟のように視界が大きく入れ替わる。先ほど肘鉄を食らわせてきた男も降りて行った。
彼女は溜息をつき、鞄の中をまさぐった。読みかけの文庫本を読めるくらいには電車も空いてきた。
そのとき、何か小石のようなものが文庫本とともに出てきて、ころりと床に落ちた。
唐突だったので、彼女はただそれが転がっていった先を見つめた。二、三の乗客も同じように転がったものを見、彼女の顔を見たが、それ以上の反応もせず拾おうともしなかった。彼女は近づきそれを拾い上げた。そしてさらに少し首を傾げた。
拾い上げたのは、小石くらいの小ささの、男の雛人形だった。
なんだっけ、という台詞が彼女の脳裏を旋回したが、何も思い当たることはなかった。ストラップやキーホルダーのようなものでもなく、お土産じみた安物でもなく、割合に精巧な細工で出来た小さな小さな本物の雛人形だ。
会社の誰かが間違えて入れたのか、明日皆に聞いてみようと思ってはみたが、思った途端に、心に一瞬寂しい風が吹いた気がした。
人目の付くところに鞄を置き放したりしない彼女の性分からして、それが偶然、鞄の奥深くに入り込むことも考えられない。彼女は普段自分が滅多に感じることのない、なにかの「暗示」に出会ったようなおろおろした動悸を感じた。
片手に乗せていたその男雛をゆっくり手のひらに包んで、そっと握りしめてみた。可愛い、と思ったのである。これを拾いものと言えるのかどうかはわからないが、彼女にとっては珍しく「何かと一対一で出会った」感覚を感じさせた。
しばらくぼんやりした気持で、読みかけの小説も広げぬまま男雛を握りしめ、彼女は窓の外の夜景を眺めていた。
電車が大きな川にさしかかる。
川の水に遠いマンションの金色の光が映り込む。いつもそれを美しいと思いながら見つめる習慣があった。屏風のようにデザインされた建物は、まわりの薄暗い建造物よりもきらびやかな灯を放っている。走るにつれそれの角度が次第に変わりゆくのを見切ってから電車は川を渡り終える。
その金屏風のマンションを見つめていた彼女は、一瞬、信じられない光景を目に捕らえた。
金屏風のすぐ傍に、横顔の巨大な「女雛」が鎮座しているのがふっと見えたのだ。
ライトアップされている白い鼻梁、結髪の上の金の髪飾り、膨らんだ十二単の胸元。
一瞬の色彩が、過ぎてからかえって鮮やかに、目の裏に残った。
もう電車は建物群の影に突入してしまい、いくら窓にはりついて雛の姿をビルの隙間に見ようとしても、もう見えることはなかった。
女雛が本当にあの場所にあるならば、大仏よりももっと大きな建造物だ。なにかの祭事の出し物の空気人形か何かにしても、巨大すぎる。
錯覚にせよ、あまりに鮮やかに見えたことに、彼女は茫然と感動した。
彼女は手のひらを開き、小石大の男雛を見つめた。そして次の駅で降りた。
町工場や雑居ビルの間をすり抜け、途中下車の暗い夜を、彼女は小走りに走った。
とにかく河川敷に立ってもう一度、あの大きな女雛を見るのだ。
心では、あれは錯覚に過ぎない、と思っている。けれど逆にもし、本当にあれが存在した時に自分はどう思うのか、という一抹の期待や不安もある。
二十分も歩いたり走ったりし、やっと堤防の芝生をよじ上り、河川敷に立った。
日頃電車から見るだけの風景の中に自分が登場している不思議さを、彼女はまず感じた。夜の大気の中に、高速道路の車たちの轟音が微かに混じる。この場所は、こんな空気の匂いがしていたのか、と思いながら深呼吸する。そして静かに視界を見渡し、ゆっくりと、あの金色の屏風のようなマンションに目を向ける。
案の定、そこには何もなかった。彼女は、安堵のような笑いのような溜息をついた。
「でも私は確かに見た。もう一人の証人は、ここにいる」と思いながら、彼女は手のひらの男雛を見た。
煩わしい大きなサイズのハイヒールを芝生の上で脱いで、斜面を降り、夜の河川敷を川岸まで走った。運動場やススキ原を過ぎ、息を切らせながら夜に紛れ、川の水のすぐ傍まで来ると思い切り、小石のように小さな男雛を、水面遠くに投げ捨てた。
闇の中、たった一人の大袈裟な芝居ぶりに少し照れながらも、裸足の彼女は、祈るように思った。
「小さいお内裏さまが、無事、あの大きなお雛さまのもとに行けますように。お婿入りね」
職場の休憩所でコーヒーを飲みながら、彼女は何となく後輩の男性社員に話かけた。
「昨日、鞄の中に小さーいお雛さまが入ってて」
「お雛さま?なんですかそれ」
「わからない。私には心当たりがないの」
このくらいと彼女は指で大きさを示して、
「小石大くらいの、すごく良く出来た、男のお雛さまがね」
と言いかけて、その先のことは何となく、話してもしょうがない、と思い口をつぐんだ。
すると小柄なその後輩は、愛嬌のある笑い声で言った。
「小石大って、恋・次第みたいでいいすね。なんかそのお雛様、俺みたいでいいな」
彼女は一年後、その後輩の男性社員と結婚した。
結婚式の引出物は、特別に発注した陶製の、大きい女雛と小石大の男雛の一対の置物だった。