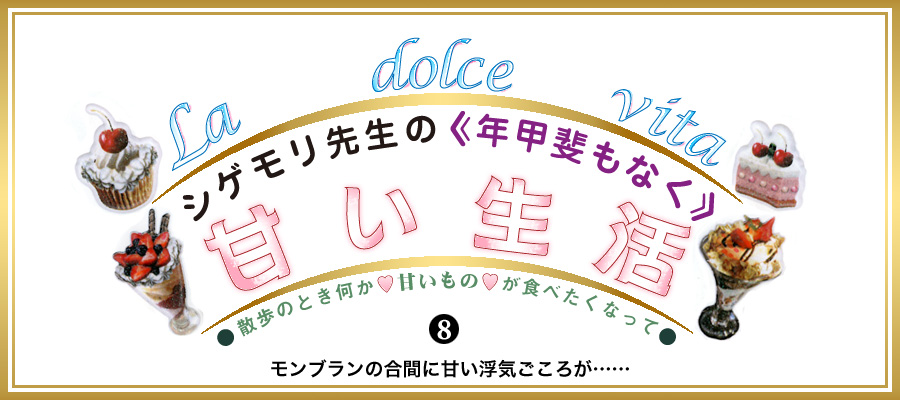去年の秋も深まりつつあったころ、秋といえば栗(マロン)。マロンといえばマロンペーストを用いてのモンブラン──ということで、モンブランを食べ歩きしてみようと思い立ったのですが、あるんですねぇ、ひとくちにモンブランといっても、その姿、形、そしてもちろん味のバリエーションが。
で、日本での元祖(?)モンブランといえば、この店。自由が丘の老舗。その名も「モンブラン」を訪ねました。

◉自由が丘「モンブラン」の外観。道行く人も、なんとなくオシャレ?
自由が丘といえば、大学を出て、横浜が勤務先になったとき、どういうわけか緑が丘という、自由が丘のとなり町のアパートの部屋を借りたことがあります。自由が丘から駅ひとつ。歩いても10分足らずか。というわけで、自由が丘は、ぼくの青春の1ページの町というわけで、洋菓子店の「トップス」(この店でのお好みはバナナケーキ)やジャズ喫茶の「5SPOT」(ジャズ評論家のいソノてルヲ氏の店)の思い出はあるのだが、「モンブラン」のモンブランを食べた記憶がない。
しかし、あの東郷青児描く包装紙には覚えがあるので「モンブラン」にも行っていたんだろうなぁ。そういえば、あのころは洋菓子店に入った場合、たいていはサバランを注文していた。あるいはプリンかババロア、かコーヒーゼリーか、もしあればワインゼリー。とにかく自由が丘の「モンブラン」で、本命のモンブランを味わった記憶がない。だから、今回の「モンブラン」訪問は、初めて行く店と同様だ。
自由が丘の洋菓子店となると、住宅がひかえているので銀座よりも女性占有率が高いことが想像つく。ここはやはり女性に同伴をお願いする。東郷青児の内装にふさわしいエレガントな女性を厳選、チャーター。といったって、ひと駅で来られる友達に、「ちょっと散歩がてら気分でお付き合いしてくれない?」という極めて謙虚なお願いです。
で、「モンブラン」で夕方5時に待ち合わせ。少し前に着いて、デジカメでお店の外観などをスナップ。
今回、そのときのあれこれの写真をチェックしていると……うむ!? 「モンブラン」の写真の前後にいろいろケーキ、和菓子の姿が……。そういえば食べてたんですね? この間。栗・マロン関係や他のスイーツも。
頭がモンブランになっていたので、他のスイーツのことを軽視していたのかしら、忘れていました。とにかく、せっかく賞味したのだから、春が来る前に、これらのことも、覚えとして書いておくことにします。
マロンといえば、もともとぼくがもっとも親しいスイーツ──それはマロングラッセだったのです。神田・神保町の洋菓子の老舗「柏水堂」のマロングラッセ。
世界に冠たる古書店街という立地条件もあるのだろう、ここのマロングラッセは、昔から文化人御用達の栗菓子として名を馳せてきた。人へのちょっとした手土産(てみやげ)としてもふさわしい。

◉銀紙に1つ1つ包まれた「柏水堂」のマロングラッセ。創業は昭和4年とのこと。

◉銀紙の中のマロングラッセはこんなカンジ。
ぼくは口の中で少しずつ溶かしながら味わいます。
ぼくは口の中で少しずつ溶かしながら味わいます。

◉6コ入れの、この、美し箱が葉書を入れておくのにちょうどいい。
最近の「柏水堂」では、犬のプードルの形をしたケーキが女性に大人気ですが、ぼくの定番はやはりマロングラッセ。栗の実の砂糖漬けですね、ほのかにブランデー(?)の香りがする。しかも、この6個入りの銀紙の美しい箱が、ちょうど葉書の入る大きさなので、空き箱は年賀状入れに愛用している。そういえば、モンブランというケーキは、このマロングラッセを作る際に崩れてしまったマロンの再利用としてマロンペーストを作るところから始まったものという。ということは、モンブランの生みの親はマロングラッセということになる。
しまった! 柏水堂のモンブランを食べてなかった。ショーケースの中にモンブランが並んでいるのは見ていたのに。銀座の「アンジェリーナ」や「シャルパンティエ」のモンブランと比べたら、ぐっと小粒(半分以下のボリュームか)で、紅茶かコーヒーのおともに手頃かな、と思っていたのに。
ここのマロングラッセとモンブランを一緒に味わえば、鳥肉と卵の親子丼ならぬ、マロングラッセとモンブランの親子マロンケーキとして楽しめたのに。これは近々、実践して、報告します。ここのティールームも小粋(レトロ)でとても気持ちいいしね。
柏水堂の話が長くなってしまったが、デジカメやスマホの記録をチェックしつつ、この間、味わった他のスイーツのことにふれておこう。
お、そうか、これは「栗福」。船橋・西武の地下で買い物をしたときに、この「栗福」の「限定販売店」に出くわした。長野県・小布施町からの出張実演販売だ。シュークリーム大の巨大たこ焼き器(?)で皮を焼き、中に栗の実をゴロンと入れる。ぼくは知らなかったけど、小布施は栗の名産地として知られているとのこと。1個252円で(これは安い!)という印象。ただし1名様5個まで。

◉運よくデパ地下で「栗福」の実演販売に出くわした。

◉たしかに福々しい栗まんじゅうだ。大きさは女性のこぶし大。

◉皮たっぷり、あんたっぷり、栗たっぷりの「栗福」。
事務所で仲間がひとり仕事をしているはず、と思ったので出来たてホヤホヤを2つ買ったのだが、到着すると、すでに退出のよう。牛乳を飲みながら、まだぬくみのある「栗福」2つたてつづけに。満足、満足! かなりの充実感。ああ、これは栗きんとんで有名な「すや」のそばまんか。ここのそばまんは岐阜県は中津川出身の編集者・Oさんが、なにかといえば自慢気に持ってきていた。ま、たしかにそばの素朴な香りと小豆あんの全体に品のいい甘味。茶菓子としての相性は抜群。

◉「すや」のそばまんは皮はソバ粉を使用。最後に皮の表面を焼いて、ソバの香ばしさを引き出す。

◉半分に切ると、この姿。ところで、なぜこの季節なのに、栗で有名な「すや」の栗まんじゅうなかったのかしら。
ところで、今回、写真に納め、賞味させてもらったこの、「すや」の饅頭、誰からいただいたのか記憶がない。ちょっと前のことなのに。中津川のOさんは親の介護で向うに行きっぱなしだし……。まっ、いいか、今度またくれば、(あ、あのときの「すや」は、この人だったのか)と思い出すことでしょう、と調子がいい。もうひとつ、やはり栗がゴロンと入っている菓子をいただいた。箱は小さいのに、ズシリと持ち重りがする。大泉学園町(練馬区)の和菓子屋「大吾」の〝武蔵野銘菓〟「爾比久良(にいくら)」。

◉包装紙にも「献上品」と誇る「爾比久良」。格調の高さを感じさせる。

◉どうですか、この美しい栗と小豆あんの断面。武蔵野を上った月のようにも見える。
ズシリと重いはずだ。卵黄と白あんの内側に小豆あん、その中に丸栗がミッシリと詰められている。白あんの食感はポソポソパサパサとすぐに崩れ、最初は、黒もじの楊枝などでは、ちょっと食べにくいなぁ、と思ったのだが、この白あんと中の小豆あんの味のバランスが実にいいんですね。甘さが押さえられているのであんの風味が生きている。そして、中心におわしますのは存在感のある丸栗である。この「爾比久良」は、歴史著述家にして十七代・長宗我部友親当主、長宗我部氏からのいただきもの。しおりには「献上品」とあり「昭和天皇の御訪米の折、御調達献上」と記されている。この風雅な味、アメリカ人にわかるだろうか、なんて思ってはいけません。
これも栗だ。神楽坂を歩いていたら見かけぬ和菓子屋が。ここ数年、神楽坂の店の転変が激しい。新しい店ができたな、と思っていると、いつのまにかまったく別の店に変わっていることも多い。
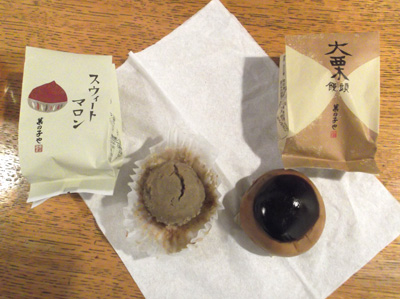
◉「神楽坂・菓の子や」のスウィートマロンと大栗。もちろん「栗シリーズ」のために試食。

◉ふたつに切ると、こんなカンジ。ぼくはどちらかといえば、大栗のほうが好きです。
この和菓子屋の場所に、どんな店があったのか思い出せない。それはともかく、この「神楽坂・菓の子や」、すでに人気店のようだ。店内に数人の客が品選びをしている。もともと性格が保守的なため、新規開店の店は避けがちなのだが、ミーハーでもあるので人が大勢入っていると、自分もつい入りたくなる。ものは試しとばかり「大栗189円」「スウィートマロン147円」「大納言きんつば126円」の三種をお持ち帰り。金沢の宴会で主催者からいただいた「棒茶」で味わう。(そういえば……)と、このときの金沢「中田屋」のきんつばを思い出した。一度、きんつばを食べくらべてみるかな。浅草の「徳太郎」とか、半蔵門の「一元屋」とか、神戸の「本高砂屋」とか。
と、モンブラン巡りの合間に、思いおこせば、いろいろスイートな浮気をしていたのですが、この他に、京都旅行の帰りの駅中で、伊勢の「赤福」があったので、これを自分と、あんこ好きのバー「S」の若オーナーK嬢へのお土産に。
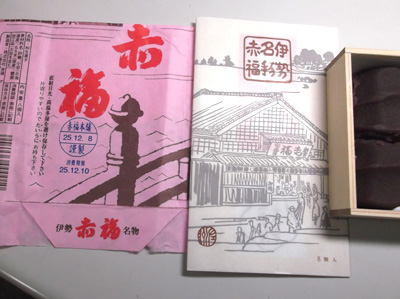
◉あんこ好きには絶対喜ばれる伊勢名物「赤福」
それから、これは誰がくれたんだっけ、こぶりのコッペパンぐらいのデカイ、スイートポテト。これも持ち重りがしたなぁ。食べきれないって、ひとりじゃ。事務所の皆といただきました。
◉ティーカップと比較して下さい。このスイートポテトの大きさ。思い出しました!
これはO氏に連れていってもらった浅草の古いBarのお土産でした。
それから長崎の・岩永梅寿軒の「もしほ草」、これは、つい最近、長崎旅行から帰った元文芸誌編集長・A同志より拝領。初めての味で、ひとくち入れたときは淡い違和感。海藻の味がするんだもの。しかし、微妙な塩気と甘味。そして牛脂の食感。やみつきになりますね、これは。これはO氏に連れていってもらった浅草の古いBarのお土産でした。
おやおや年末から新年、そして2月、食べてましたねぇ和洋のスイーツを。で、しかも2月14日、バレンタインデーで「おたんこナース」の原作者、小林光恵さんはじめ山ほどもらった(これはウソ)高級チョコレートでしょ、しかも夜のお酒は、ワイン、シェリー、日本酒、ビール、ウイスキー、焼酎、カクテルと、存分に楽しんでいるのですから──秋に連載を始めてから2.5㎏ぐらい太るのは当然のことでしょう。
(糖尿病にはくれぐれも気をつけて、ともかく体は動かそう)と強く自分に言い聞かせてはいる。甘いものって、食べれば食べるほどクセになるんですよね。一日二日間があくと禁断症状に似た心理状態になる。
じつは、この原稿を書いている途中、「やはり、いますぐ柏水堂のモンブランを食べねば!」(なぜこのタイミングで思う)と、原稿用紙を開いたまま飯田橋の事務所を飛び出してしまった。
あれっ、空から、またしても粉雪が。降る雪を顔で受けつつ神保町の信号を渡ろうとしたとき、同じこの「アートアクセス」で力作・「戦争画リターンズ」の連載をしている平山周吉氏とバッタリ。「おや、これからどちらへ」「いや、そこの柏水堂でモンブランを」と短い会話を交わして別れたのでした。
というわけで、自由が丘の「モンブラン」と「柏水堂」のモンブランおよびetc.は次回に。その次からは春らしいスイーツ訪問といきましょう。夢のような「甘い生活」の日々が続きます。
ところで、この「甘い生活」でも紹介した銀座「ジョルジュデュラン」が去年の暮(12月23日)閉店していました。店の前で「ボンジュール」と道行く人に呼びかけていた熱心なスタッフの女性たちは……?
(第8回おわり)