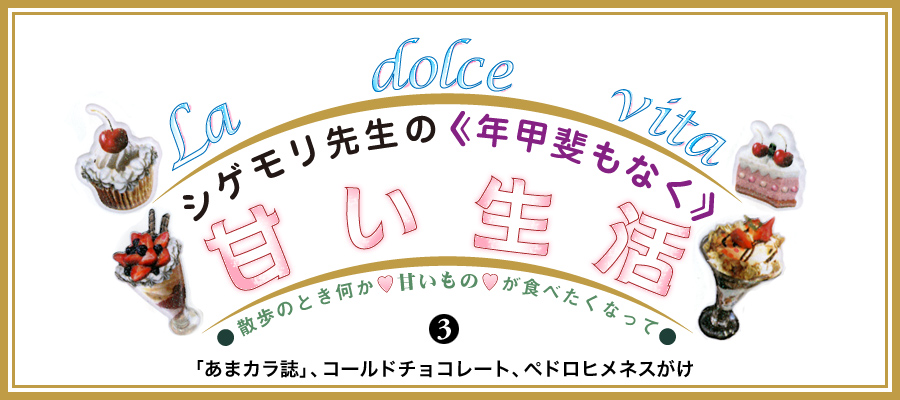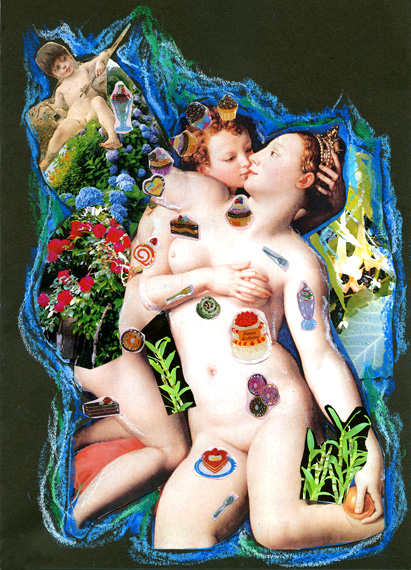
「Sweets Memories」コラージュ:安土利夫
前回、銀座「若松」でかき氷でも、と思って店を覗いてみたのだが、中高年の女性客で一杯だったので、腰が引けて入らずに撮ったショーケースのかき氷の写真が、まるでピンボケ。あまりにひどいので、再度「若松」へ。
またしても猛暑、午後の3時前、この日はなぜか客が少なめだったので入店。もちろん佐多稲子さんがお好みだったという氷あずき(850円)を注文。プラス、白玉(100円)をトッピングに。
白玉をかき氷の中に埋めてしばらくして口に入れると、白玉の表面が凍るのか外側がかたく固まり、不思議な噛みごたえが楽しめる。そして中は白玉本来のモチモチとした柔らかさ。

◉(左)白玉をトッピングで頼むと、あれっ、あずきが乗ってない!? と思うかもしれないが……。
(右)このように、あずきはちゃんとかき氷の中に。白玉を氷の中に埋めてしばらく置くと微妙な歯ごたえが。
汗だくで店に入ったのだが、この氷あずきを食べ終るころには汗は、すっかり引いてしまい完全にリフレッシュ。佐多稲子さんも、必死で生きる夏の日、この氷あずき一杯で元気を取り戻したのでしょうか。きっと、そうであったと思いたい。甘いものは人生の応援歌でもある。(右)このように、あずきはちゃんとかき氷の中に。白玉を氷の中に埋めてしばらく置くと微妙な歯ごたえが。
ところで、前回の稿で、「若松」発祥で人気を博したという、あんみつに対して、かつての文人が──あの甘いみつまめの上に、あんまで載せるとは!──と苦言を呈していたことを記したが、じつはその文人とは、誰あろう作家の小島政二郎。
小島政二郎は「眼中の人」や「鷗外・荷風・万太郎」などの私小説的文壇物の好著があるが、その名を一般に知られることになったのは、食と文壇交遊録の随筆集『食いしん坊』。
この『食いしん坊』に、「あんみつについての発言」がある。手元の朝日文庫版(昭和62年刊)を開く。
本文、冒頭、イキナリの言及である。
大阪、京都は知らないが、東京は大地震でガタンとお菓子がまずくなり、今度の戦争で、またガクンとまずくなった。
大地震までは、「餡蜜(あんみつ)」なんという甘いが上にまた甘い餡を掛けるような不合理な菓子はなかった。あの頃から、甘さに対する味覚が下落した。
小島政二郎の『食いしん坊』は朝日文庫上下の2巻で刊行されていて、食、とくに甘味に関する随筆集では、古今随一といえるものではないだろうか。
もともと食べもののエッセーは、圧倒的に左党、つまり酒飲みによるものが多い。たとえば食べ物のエッセーの名手といわれる吉田健一、池田弥三郎、そして比較的近年では、信奉者の多い池波正太郎などなど。大地震までは、「餡蜜(あんみつ)」なんという甘いが上にまた甘い餡を掛けるような不合理な菓子はなかった。あの頃から、甘さに対する味覚が下落した。
しかし、酒がまったくといっていいくらい飲めなかった、だから断固甘党の小島政二郎の随筆は、その点で異色にして貴重なのです。
この小島政二郎の食随筆の執筆舞台となったのが、知る人ぞ知る「あまカラ」誌。体裁は、というと、そう、今日も人気の銀座の高級PRタウン誌「銀座百点」に似る。と、いうよりは、まず「あまカラ」誌があって、これに似るタウン誌として「銀座百点」を始めとするレベルの高いPRタウン誌が登場した。
「あまカラ」誌に関して、概略だけ記しておこう。この、100ページに満たない小冊子が、食味随筆というジャンルの成立に果たした役割りは、あまりにも大きい。
「あまカラ」は戦後の昭和26年8月に創刊される。発行元(甘辛社)は大阪の銘菓の老舗で、もちろん現在も盛業の「鶴屋八幡」。このPR誌は、鶴屋八幡の商品をPRするのではなく、当時の文人、著名人を総動員しての珠玉の食のエッセー誌として注目を浴びる(終刊は昭和43年4月の200号と5月の続200号)。
今日でも「あまカラ」のバックナンバーは古書市などで時々見かける。創刊号から終刊号までの“大揃い”がどれほどの値がつくのか知らないが、バラで1冊800円とか1000円ぐらいだろう。
ぼくも、ずいぶん前に何冊か入手しているが(それも、100号目か、それこそ終刊の200号であったような気もする)、去年の本置き場の移動でどこかにまぎれ込んでしまった。そのうち出てきたらお披露目します。
それはともかく「あまカラ」誌がどんなに重要な存在であったかというと──この「あまカラ」の連載から、すでに紹介した小島政二郎の名著『食いしん坊』(単行本は昭和47年・文化出版局刊)が生まれ、また、ぼくの手元にあるものだけでもこの小島の編による『あまカラ(甘辛抄)』(昭和32年六月社刊)、谷崎潤一郎他『あまから随筆』(昭和31年・河出新書 ※この本は某麗人にして書痴の女性プロデューサーからの提供品)、そして高田宏編『「あまカラ」抄(全3巻)』(平成7年〜8年刊)などなどといった「あまカラ」本が続々と刊行されている。
また「あまカラ」誌に関しても、あちこちで語られる。その一例として、小島政二郎のような甘党一本槍ではなく、それこそ、甘辛両刀使いの剣豪、いや食豪・吉田健一の『舌鼓ところどころ』(昭和52年・中公文庫)にも「あまカラ」誌のことがふれられている。引用する。
「あまカラ」という雑誌があって、これは前から愛読しているが、この雑誌が現在でも成功している理由は、人間がものを食べずにはいられない動物であることに着目し、素人の食いしんぼう、それも多くはものを書くのに馴れている文士が食べものに就いて書いた記事を編輯して一冊の雑誌を作っている所にある。
とし、さらに
「あまカラ」と同じ四六判を横にした食べものの雑誌が恐らくは全国で五、六十種も出ていて(以下略)
とあり、「あまカラ」に対する吉田の評価と、この小冊子の影響を受けた類似誌がやたらと刊行されていたことがわかる。そうそう、ここまで書いてきて、大事なことを書き忘れていたことに気づいた。
安藤鶴夫の著作『雪まろげ』『年年歳歳』の2冊の内容は、すべて食べ物の出てくる話なのだが、それらすべてが、この「あまカラ」誌に連載されたものだったのだ。大酒飲みで知られた安藤鶴夫は、東京の甘いものについても心にしみる文章を残している。機会を見て紹介してゆきたい。
──と、かくのごとく「あまカラ」誌は戦後の食エッセーの重要な舞台となるのだが、その“主役”が、下戸・甘党の党首、小島政二郎だったのである。
ぼくの、この「甘い生活」の連載中、小島政二郎の「食いしん坊」は、先の吉田健一、池田弥三郎、池波正太郎、そして安藤鶴夫らの本とともに、常に傍に置かれることとなるだろう。
銀座「若松」のあんみつから小島政二郎、そして「あまカラ」誌と、話は食の味覚から食べものエッセー“味読”の横道に入り込んでしまったが、“甘いもの”を語るとき、小島政二郎と「あまカラ」誌は絶対にはずせないので、まずはクリアーしておいた次第。食べものエッセーの愛読者が「あまカラ」を知らなければ“モグリ”といわれても仕方ないくらいですから。
ところで、船橋駅すぐ近く、ステキな音楽好きが集まる超マニアックな音浴ギャラリーバー「サルブロ」で「若松」の白玉をトッピングにした氷あずきを食べた話をしていると、出るわ出るわ氷あずきに関する話が。
○北品川の「いちょうの木」とかいう店、30年以上前からのかき氷が食べられる喫茶店で、30種近くのトッピングができる、とか ○「ヨックモック」のブランド氷使用の“天然かき氷”は青山の本店だけではなく東京駅の一番街の店でも食べられる、とか ○表参道の「AOYAMA CAFE」では「かき氷職人」の名刺を持った店員による入魂のかき氷が食べられる、とか ○「日光・三ツ星氷室」の天然氷仕様の渋谷・神山町の「神山バル・セバスチャン」、とか ○駿河台・山の上ホテルのコーヒー風味の「大人のかき氷」、とか……。
かき氷かぁ。和菓子やケーキ、チョコレートなどにはそれとなく気を配っていたけど、かき氷は、まるで意識からはずれていたなぁ。子供の頃は別として。
ほんと、子供のころはよく食べた。それも小さいころは、イチゴとかメロンとか。少し高学年になると、ああいう派手な原色系は敬遠して、ミルクとかスイにする。いま思えば子供なりに、ダンディズムみたいな感覚が働くのですね。
今年の夏は長く暑かったが、それでももう9月末。かき氷の追求は来年までお預けとするか。他に食べたいスイーツは山ほどあるし。
ということで、話は銀座に戻って、すでに予告ずみのチョコレートショップのうち、「ピエール・マルコリーニ」へ。
……と思ったのだが、東京駅の丸の内一番街にヨックモックがあるんだから、銀座へ行く前に寄らない手はない。それに、氷あずきは、9月も末になるとメニューからはずされてしまうかもしれない。
ヨックモックに入る。注文は人気のイチゴでもマンゴーでもなくロイヤル・ミルクティーにする。これならなんとなく男が食べても違和感はないだろう、という無意味な思い込み。
なるほど、出てきたかき氷は紅茶色している。トップに生クリームとミントの葉が。それに練乳(コンデンスミルク)が添えられている。ミルクをかけるまえに紅茶かき氷だけを口に入れてみる。

◉ヨックモックのかき氷、ロイヤル・ミルクティー。読んでいた文庫本といっしょに。
ん? 噂に聞くブランド氷「四代徳次郎」のフワフワのかき氷ではないではないか。小さな氷の粒がしっかりしている、いわゆるフラッペ状のもの。ま、これはこれでシャリシャリ感があってよい。しかし「徳次郎」のフワフワ感は? とやっぱり疑問が残る。その場で問いただしたりすると、クレーマーと思われるといやなので、577円也のレジを済ませてから電話をしてみると……。
「すみません、徳次郎の氷は9月に入ったころには使い切ってしまって、いま出しているのはふつうの氷なんです。もちろん青山の本店も。かき氷そのものも、この秋分の日の連休までで終いになります。徳次郎の氷は前の年、前の年の秋に発注するんですが、今年は暑くて、売り切れてしまったんです」とのこと。なるほど納得、了解、というてんまつでした。
にしても、ぼくはこの年ゆえか、かき氷にはあまり執着心が湧かない。やはりデロリとしたものがいい。というわけで目的の「ピエール・マルコーニ」へ。

◉ピエール・マルコーニ外観。カカオの実がシンボルマーク。
1階のチョコレートショップに視線を走らせながらも2階のカフェへ。平日の夕方前なのにカップルや同士の客もいる。オシャレなこの店に男ひとりで入る勇気がなく、モダン麗人に助っ人役を頼み、カップル然とした風情(には見えないか)で席につく。メニューを見る。ぼくはコールドチョコレート(レモン)。モダン麗人は季節のパフェで、こちらもレモン。季節限定のメニュー。コールドチョコレートは大きめのカクテル・グラスにトロリと。パフェはフルートグラス(?)に3重層の容姿で。なるほどパフェというだけに見た目もたっぷりと、文字どおりパーフェクトな外観。
スプーン一口だけパフェを横領。淡いレモンの味がする。妙な甘さがなく品がいい。でもね、男がいきなり「パフェ!」というのもね。白ワインか泡ものかなにかで喉をしめらしてならともかく。

◉手前がコールドチョコレート(¥1100)、奥がパフェ(¥1500)。
で、ぼくはコールドチョコレート。顔を近づけると濃厚なチョコレートの香りにレモンのクールな香りが。テーブルにはスプーンが添えられているけれど、こういうものはスプーンでチマチマすくって味わうよりは、グラスを口に傾けてキューっと腔中へ。そして4〜5秒、口の中でチョコレートの風味を味わい、そして喉を越す。そしてまたキューっと腔中へ、そして4〜5秒、口の中で……。と、これを4〜5回繰り返すと、もう、ほとんどなくなる。しかるのち、残ったチョコレートをスプーンでていねいにすくいとる。美味しいチョコレートは高級なワイン同様、大切ですから。
このコールドチョコレート、余計な甘さがないので、この後、スコッチを飲んででもワインを飲んでも問題はない。と、いうことで、モダン麗人を伴って銀座・泰明小学校の向い、昔の月光荘のあったビルのシェリーの品揃えではギネスブック級の「シェリー・クラブ」へ。

◉カステラの上にバニラアイス。これにたっぷりシェリーのペドロヒメネスをかける(¥840)。満足!(シンプルなアイスにシェリーがけも¥525)
この日の目的はシェリーを飲むより、ここのペドロヒメネスをかけたアイスクリームを楽しむこと。オリーブとエビのアヒージョをつまみにアモンティリアードを3杯ほど。で、〆(しめ)に、バニラアイスにシェリーのなかでももっとも甘く濃厚なペドロヒメネスをかけたのを「“ツユダク”でお願いね」などと、吉野家で牛丼を食べているようなレベルの低い冗談を言う。こういうことを言うようになったら、もう少々ご酩酊の証拠──と席を立つ。このあたりの、自らを律するあたりが昨日、今日の、甘辛両党使いではないところ。
とはいうものの、カウンターに扇子を忘れてきてしまったような……。
(第3回おわり)