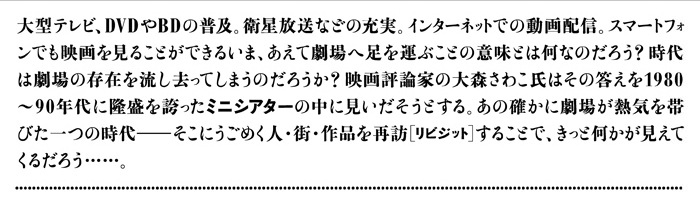[第7回より続く]
アメリカでの公開から1年遅れて『ストップ・メイキング・センス』(84)の日本公開が実現するが、クズイ・エンタープライズでの配給が実現したのも、これまでの葛井克亮社長のニューヨークでの人脈があってこそだった。宣伝を担当していた遠藤久夫さんは振り返る。
「当時の葛井社長はニューヨークの映画人に信頼される存在になっていたので、普通では考えられないほど有利な条件で、映画を配給できることになったんです。日本側のリスクが少ない契約で、特別待遇ともいえる条件でした」
もっとも、配給権は得たものの、映画をかける劇場がすぐには見つからなかった。
「新しい会社だったので、当時はどこも見向きもしてくれなかったです。この作品だけではなく、クズイが持っていた音楽感性の映画をかけるための劇場探しは大変でした」
辛抱強く劇場を説得してまわり、渋谷ジョイシネマ、新宿の歌舞伎町シネマ2、吉祥寺のバウスシアターなどが公開の話に乗ってくれて、レイトショーという形で上映が実現した。ジョイシネマや歌舞伎町シネマ2はいわゆるミニシアターではなく、ふだんは拡大系の娯楽映画をかけていたが、そんな劇場がインディペンデント系映画の上映にチャレンジしてくれた。
社長が『ストップ・メイキング・センス』のポスターの裏に掲載した文章を引用すると――。
「ストップ・メイキング・センス〔概念にこだわらないとか理屈で考えるのはよそうとかのニュアンス〕というタイトル通り、この映画は音楽的世界と演劇的世界と映画的世界が見事に融合したスタイルをもっている」
「〔アメリカでの〕宣伝はマス宣伝ではなく、観た人々の口から口へ、この映画のすばらしさが伝わっていく。人々がロスやニューヨークへ旅行する時、この映画を観ていくのが目的のひとつになってくる」
「日本でも今や若者達は個人主義に目覚め始め、マスによる与えられた宣伝に拒絶反応が出て来ている。知る人ぞ知るという良い作品を自分たちで見つけ、口から口へと伝えていく感覚が時代の流れになってきているように思える。日本の若者達の感覚も、まさにストップ・メイキング・センス!、である」
「各映画会社に配給を依頼したが、なかなかストップ・メイキング・センスの感覚で興行するのは現実的に受け入れ体制が整っていないという理由で公開が決まらなかったが、〔3つの劇場の〕人々とストップ・メイキング・センスの感覚で共感。映画のプロデューサーも賛同し、我々自身がストップ・メイキング・センス!のフィーリングで配給することになった」
「時間はかかるだろうが、なぜ、今、ストップ・メイキング・センスの時代なのかが、口から口へと拡まって、理解されていけば幸いと思う」
レイトショー公開は保障金を映画館に積まなくてはいけない昼間の興行と違ってリスクが少なかったという。「1日1回だけの興行なのが逆によかったと思います」と遠藤さん。その方がかける側は金銭的な負担が少ないし、劇場側も夜7時からのロードショーが終わった後のあき時間を利用できるからだ。
◉『ストップ・メイキング・センス』の日本版ポスター。唐突なコピーに注目
宣伝に関しては日本のファッション・ブランドも巻き込んだ。今ではブランドとのタイアップは他の映画会社でもとられているが、当時としては珍しかった。映画の中ではボーカルのデイヴィッド・バーンがだぶだぶのビッグ・スーツを着て「ガールフレンド・イズ・ベター」を歌いながら踊るシーンがあり、映画のハイライトとなっている(「ストップ・メイキング・センス」という歌詞が出てくる)。ポスターにはスーツだけを撮影した印象的な写真が使われているので、ファッション・メーカーのメンズ・ビギと手を組んだキャンペーンを考えた。Tシャツを作り、2~3分の映画館用のオリジナルのコマーシャル・フィルムも製作した。メーカー側は海外での作品の評判をすでに知っていたので、自社のイメージアップを図れると考えたせいか、快くタイアップを受け入れてくれたという。
また、求人雑誌「アルバイト・ニュース」(現在の「an」)に「映画スタッフ、募集」という広告も打った。スタッフといっても、実際は渋谷や新宿などでの映画のビラまきの仕事だったが、この告知が予想以上の反響を呼び、アルバイトの面接が予定されていたビルの前に列ができて、宣伝部としては成功への手ごたえを感じ始めたという。
「公開前に問い合わせが多かったので、ヒットすると思いました。とにかく、変にスノッブな映画ではなかったところが良かったですね」と遠藤さん。
いざ公開してみると、興行は大成功に終わり、特に渋谷では約3カ月のロングランとなった。レイトショーだけの公開であるにもかかわらず、1億円以上の興行収入を上げることができたのだ。
「上映中はまるで寅さんの映画を見るように拍手している人や映画館の後ろで踊っている人もいたようです」と遠藤さん。
宣伝部の同僚だった伊地知徹生さんは「ライブ感を会場に持ち込め、音楽ファンなどとクロスオーバーできたことがうれしかった」と振り返る。
当時、この映画に惚れこんでいた私は何度か劇場に行ったが、公園に通りにある渋谷ジョイシネマの前には長蛇の列ができていて、それだけで映画への興奮が高まった覚えがある。私の見た回に踊っている観客はいなかったが、曲の切れ目には拍手が出て、実際にコンサート会場にいるような気分になったものだ。
映画の中では客席が最後の曲以外では写らず、こちらもコンサート会場の観客の目線でステージ上の演奏を堪能できる。ただの甘いラブソングが歌われることはなく、ナンセンスな言葉を重ねることで都市生活者の孤独や狂気が浮かび上がる。メンバーたちはアートスクール出身なので、視覚的な見せ方もうまい。ランプやスライドなど、使われるのは最小限の小道具なのに、曲ごとに異なる表情が見える。
撮影されたのはハリウッドにあるパンテージ・シアターで、モノトーンのスーツ姿で歌い、踊るデイヴィッド・バーンの不思議な存在感は、ミニマリズムのスタイルが流行した80年代のパフォーマンスの洗練されたパワーを伝える(蛇足ながら、頭の切れる殺人鬼の心情を歌った「サイコ・キラー」は、今見ると、ジョナサン・デミ監督の後年の代表作『羊たちの沈黙』(90)の知的な殺人鬼、レクター博士のイメージに重なるところがある)。
映画のポスター裏には生前バーンと交流もあった映画&音楽評論家の故・今野雄二さんのコメントも印刷されている。
「デイヴィッド・バーンの白いスニーカーから始まって、黒いユニフォームのスタッフ達までが全員ステージ上に勢ぞろいするエンディング──そこで初めてキャメラがステージを降りて客席の中へ入っていく。どの顔も幸せいっぱいに輝いている。何て素敵な眺めなんだろう。トーキング・ヘッズの音楽は演奏する者にも聴く者にも、幸せそのものの響きなのだ」
遠藤さんの話によれば、このライブ映画は音楽、アート、ファッションなどに興味がある若い観客を集めた興行だったという。映画ファンをターゲットにしていた従来の映画興行の壁を打ち破り、まさに“ストップ・メイキング・センス”の精神が生きた作品となった(だからこそ、パルコなどの上映にも影響を与えたのだろう)。
一方、伊地知さんはこんな話をしてくれた。「あの頃の日本の観客には新しいものに食いつくエネルギーがあったと思います。クズイ・エンタープライズのやり方はイベントなどとからめて1本の映画をセールスしていました。映画だけではなく、プラスのおもしろさを加えていたわけです。ミニシアターの創生期であり、自主映画の運動が盛り上がったり、インディーズ音楽が生まれたりという状況があったので、アメリカのニューヨーク発のインディペンデント映画を受け入れる環境にありました。また、小さな配給会社が出てきて、それぞれの自社のカラーを作り、ビデオ会社もオルタナティヴなものを商売にしていたおもしろい時代でした」
◉『スミサリーンズ』のチラシにも掲載されている「THE LATE SHOW」のロゴマークは、グラフィティ・アートの雄、キース・ヘリングによるもの。ファンなら紛れもない彼の筆致をここに見るはず
『ストップ・メイキング・センス』の成功の後、クズイ・エンタープライズは「ザ・レイト・ショー」という自社レーベルを作り、ゴスペル音楽を描いた先駆的な作品『ゴスペル』(82)、人気歌手スティングのソロ活動の始まりを見つめたドキュメンタリー『スティング/ブルータートルの夢』(85)、パンクの元祖、セックス・ピストルズが出演する『D.O.A.』(81)、都市で生きるジャンキーの告白を映像化した『グリンゴ』(84)、ミュージシャンのリチャード・ヘル出演の『スミサリーンズ』(82、監督は後にマドンナの女優デビュー作を撮るスーザン・シードルマン)といった作品をレイトショー公開した。今となっては知る人ぞ知る的なニッチな作品が多いが、こうした映画にも音楽やストリートといった初期のクズイ・エンタープライズが得意とした要素が入っている。
社長はジム・ジャームッシュ、スパイク・リーといったNYインディーズの中心的な監督の作品にも初期の段階から注目していて、スパイクの86年の長編デビュー作『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』(86)は西武グループの映画配給会社、シネセゾンと組んで公開にもこぎつけた(劇場はシネセゾン渋谷)。
86年に渋谷のパルコで行われたぴあ主催の「NYインディーズ映画祭」に参加するため来日したスパイクはクズイのオフィスを訪ね、NYにいるジャズ・ミュージシャンの父親、ビル・リーとFAXを使って作品に関するやりとりをしていたという。
「その時、スパイクは嘆いていたんですよ。黒人の自分には取材のオファーが少ないって。でも、とにかく、音楽好きだったので、オフィスにあったスティングの音源をあげたら喜んでいました。一緒に焼鳥屋にも行きましたよ」と遠藤さん。
また、前述の「ザ・レイト・ショー」のレーベルのロゴマークを手がけたのは、80年代のグラフィティ・アートの旗手として人気のあったキース・ヘリングだ。会社は88年に1年間限定で、キースのポップ・ショップの経営も手がけた。そんなことからも、いわゆる映画だけにとどまらなかった社の個性が見える。 キースは渋谷の街が好きで、特にオクトパスアーミー【http://www.octopusarmy.co.jp/】という店をたびたび訪ねていたという。遠藤さんはキースとのこんな印象的な出来事も話してくれた。 一緒に表参道のスパイラルにある店、KAYに寄ったら、壁にバスキアが描いた絵があったという。同じNY出身のストリート系アーティストとして、バスキアに対抗意識を燃やしたキースは、その絵の横に自分もマジックでグラフィティを残した。結局、バスキアは88年に27歳で、キースは90年に31歳で、この世を去る。その後の残酷な時の流れを考えると、このほほえましいエピソードに別の意味が加わる。 「キースがもういないのは寂しいですね。彼もエイズには勝てなかった。ストリートの英雄にはなれなかった……」と遠藤さん。


◉『バグダッド・カフェ』は音楽とともに大ヒット。『ワイルド・アット・ハート』公開時は監督のデイヴィッド・リンチが来日した
90年代が近づくと、クズイ・エンタープライズはニューヨーク・テイストからさらにレパートリーを広げて、ドイツ出身のパーシー・アドロン監督のファンタジー『バグダッド・カフェ』(87)を大ヒットさせた。テーマ曲の「コーリング・ユー」がいつまでも耳から離れない心優しい作品だ。この映画は渋谷を代表するミニシアターのひとつ、シネマライズとクズイが手を組んで成功した作品でもある。
さらにデイヴィッド・リンチ監督の『ワイルド・アット・ハート』(90)では商社の資金協力も得て、東宝系の昼間の拡大ロードショーも実現した。この映画とコーエン兄弟の『バートン・フィンク』はいずれもカンヌの大賞であるパルムドール受賞作で、こうした作品によって配給会社としてさらに大きな道へと踏み出していく(遠藤さんと伊地知さんは、こうした変化が起こる中、退社した)。
他にはジョン・ウォーターズ監督の代表作『ヘアスプレー』(88)も配給しており、パルコで公開している(後にこの作品はブロードウェイでミュージカル化されて話題を呼び、ジョン・トラボルタ主演のミュージカル映画としてリメイクされてヒットした)。
監督選びに先見の明があり、ポップなテイストの作品を売るのがうまい。そんな印象がこの会社にはあったが、90年代以降はジュリエット・ビノシュやジュリー・デルピーといったヨーロッパの人気女優たちの共演が話題になった故クシュシュトフ・キェシロフスキ監督の女性映画『トリコロール』3部作(93~94)なども配給して、創生期とはかなり個性を変えている(女性路線の作品はBunkamuraル・シネマで公開)。
80年代から90年代にかけてミニシアターに個性的で良質な作品を送りだした配給会社だったが、創生期を知る人間としては原点ともいうべき渋谷のささやかなオフィスでの光景が妙に忘れがたい。
小さな部屋でビールを飲みながら新しい音楽や映画のことを語り、バブル時代のどこか浮かれた街のエネルギーも体中で受けとめていた。
何かキラキラするものを探し、直感を頼りに猥雑な空気の中を歩く。
そんな80年代の渋谷のストリートの残像が、トーキング・ヘッズのライブ映画を見るたびに今も脳裏によみがえってくる──。

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。