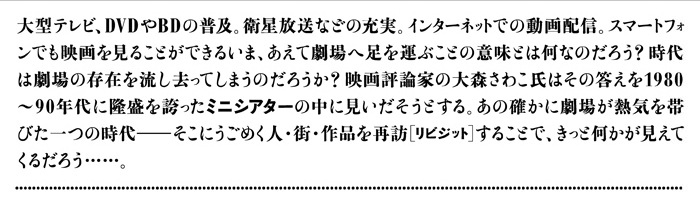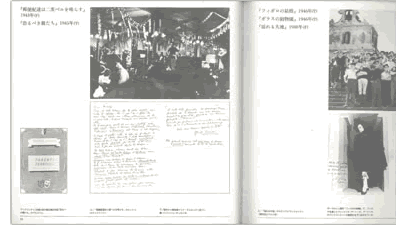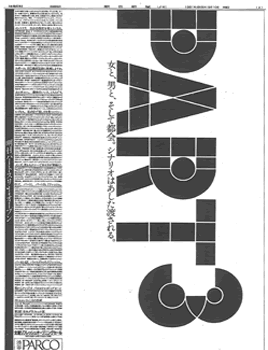80年代は都市文化が注目された時代だった。日本経済も絶好調で、パリやニューヨークなどの影響を受けながら、東京も国際都市の仲間入りを果たし、街中に明るいエネルギーがあふれていた。
ミニシアターという(当時は)新しかった文化も、東京を中心に発展していったが、80年代のミニシアター界を振り返った時、最も勢いのあった街として浮かぶのが渋谷である。シネセゾン渋谷、シネマライズ、ユーロスペース、Bunkamuraル・シネマをはじめ、多くのミニシアターが誕生し、それぞれに個性を発揮していた。
その渋谷に誕生した最初の商業的なミニシアターはここにあげた劇場ではなく、実はパルコのスペース・パート3(現シネクイント)だった。オープンは1981年9月11日。ここを映画館と呼ぶことに抵抗を持つ人もいるかもしれない。常設館ではなく、演劇や展覧会など、ジャンルを超えたイベント会場として使われていたからだ。
上映された作品群の系譜もバラバラな印象があるが、たどり直してみると、内容的にはおもしろいものが上映されている。
スペース・パート3の最初のイベントは「ヴィスコンティとその芸術」。イタリアのルキノ・ヴィスコンティ映画祭とその衣装展だった。衣装展の方はヨーロッパの他の都市でも行われていたが、東京でのイベントは、当時パルコの名コピーライター(クリエイティヴ・ディレクターも担当)の小池一子プロデュースで、本国での点数を上回る華麗な衣装の数々が展示された。一方、映画祭の方は後に配給会社ケーブルホーグを作ることになる根岸邦明も参加していて、初期の『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(42)から晩年の『イノセント』(75)まで9本のヴィスコンティ作品が上映され、地方からわざわざ映画祭を訪れたヴィスコンティ・ファンもいたという(ビデオがない時代なので、こういう映画祭でしか過去の作品を見ることができなかった)。
スクリーンで映像を見ることだけで完結するのではなく、そこに出てきた衣装も楽しむことで、ヴィスコンティが象徴するヨーロッパ文化の華やかな雰囲気にふれる。そんな広がりのあるイベント精神がパルコにはあったようだ。
「いろいろな情報を発信していこうというのが、パルコの増田通二社長の中にはありましたね。劇場があって、出版があって、催事があって、その中に映画がある。さらにちょっと遅れてクラブ・クワトロというライブハウスもできました。パルコの場合、演劇に関しては西武劇場〔現パルコ劇場〕があって、安部公房や寺山修司などのすごい舞台が多かったのですが、映画には大きな比重が置かれているわけではなく、パルコでの出し物のひとつという扱いでした。だから、ゲリラ的にいろいろなことをやっていました」
80年代のスペース・パート3の方針について振り返ってくれたのが、当時、スペース・パート3のSP(セールス・プルモーション)部に所属していた根占克治さんだ。
「パルコは西武〔流通グループ〕系の会社で、増田社長は西武の堤清二社長の学校の同級生で、教師をやめて36歳で西武に入社した方です。まずはパルコの第一号店、池袋パルコを作ったわけですが、当時は資金が十分になかったので、山口はるみさんがイラストを描いたポスターを街にバンバンはって、宣伝につとめました」
池袋パルコは69年に誕生した。隣には本家の西武デパートがあったが、パルコは170のテナントを集めたファッションビルというコンセプトでスタートし、ファッションに対して新しい意識を持った団塊の世代の若い女性にアピールすることで成功を収めた。
73年には渋谷パルコがオープンするが、この時は(まだ)タヌキが出るといわれていた駅から900メートルほどの区役所通りを「公園通り」(パルコとはイタリア語で公園の意味)と呼び、より洗練されたストリートに変えようとした。
その結果、最先端のファッションビルとして若い層の支持を得て、8年後の81年に3つめの渋谷でのビル、パルコ・パート3が完成する。「公園通り」以外にも、「スペイン坂」「ファイア通り」「オルガン坂」など、パルコの発案で周辺の路地に名前がつけられ、街作りにも貢献した。83年3月11日の『朝日新聞』には「パルコの横の大きな壁をウォールペインティングによる宣伝の場所に使うことを提案する」という内容の記事も載り、「街自体が新しい情報を発信する媒体になりつつある」と増田社長は語っている。
「増田社長は雑誌ではパロディ誌の『ビックリハウス』も創刊しています。編集を担当したのは劇団の天井桟敷にいた萩原朔美さんと榎本了壱さんで、当時のアメリカの雑誌がモデルになっているようです。他にも日本パロディ展や日比野克彦を発掘した日本グラフィック展などもありました。王道の西武デパートに対して、自分たちはサブカルチャーでいく、というのが、増田さんの中にはいつもあったようです」と根占さんは言う。
サブカルチャーというと、今はアニメ・カルチャーなども視野に入るようだが、当時は違う意味を持っていた。王道のメイン・カルチャーに対して、サブカルチャーがあり、中心からはずれた音楽や小説など、さまざまなジャンルのものを意味していた(たとえばクラシック音楽は王道だが、ロックはサブカルチャーだった)。
◉同紙8月10日朝刊の東京面に掲載された記事。「ヒューマンサイズ〔=巨大すぎないスケールのことを指すらしい〕」の公園通りらしさを演出するため、「派手な宣伝をせず、さりげなく開店する」というところにパルコの自信が透けて見える(縮刷版コピー)
ヴィスコンティという出し物は、今、考えると、サブカルチャー的ではないが、当時、日本ではヴィスコンティ・ブームが巻き起こっていたので、最先端をめざすファッションビルにふさわしい最初のイベントに選ばれたのだろう。
複数の作品を集めた映画祭や連続上映はパルコが得意とすることで、ヴィスコンティ映画祭の後は伝説のサイレント女優、グレタ・ガルボの作品を集めた「グレタ・ガルボ映画祭」が行われている。また、80年代後半にはヘルマン・ヘッセの小説にヒントを得た「魔術劇場atレトロ」と題されたユニークな連続上映もあり、ヘッセ原作、ドミニク・サンダ主演の実験的な作品『ステッペンウルフ/荒野の狼』(74)やテレンス・スタンプが詩人ランボー役を演じた『ランボー/地獄の季節』(71)なども上映された。
『暗殺の森』(70)のヒロインとして知られるサンダは70年代後半にパルコのCFに出演していて、ミステリアスな美しさを漂わせたヨーロッパの人気女優だった(彼女やフェイ・ダナウェイが出演していた70年代のパルコのCFは鮮烈なインパクトを映画ファンに残したものだ)。そうしたCFの流れを組んで『ステッペンウルフ』や『ルー・サロメ/善悪の彼岸』(77)のように、日本ではオクラになっていたサンダの出演作が、80年代後半になってから陽の目を見たのだ。ヨーロッパ映画の場合は、同じく81年にスタートしていた六本木の俳優座シネマテンと共同上映が行われることもあり、『アナザー・カントリー』(83)や『眺めのいい部屋』(86)といった大ヒット作も生まれていく。
「シネマテンとはお互いの足りない部分を補っていたと思います。シネマテンは情報を握っていて、映画に関するノウハウがありましたが、パルコには資金がありました。スペース・パート3の場合、次の出し物が決まっていると、映画がヒットしてもロングランできないという難点がありましたが、シネマテンはそういう制限がありませんでした。また、シネマテンは夜の上映が中心でしたが、パルコはもっと早い時間の上映でした」
85年にはスペース・パート3の変化をうながすひとつの事件も起きている。至近距離にあった劇場、渋谷ジョイシネマでレイトショー上映されたトーキング・ヘッズのコンサート映画『ストップ・メイキング・センス』(84)に多くの若い観客がつめかけたのだ。
「レイトショーでこれだけ人が入ったことにとても驚きました。渋谷の夜は若者がこういう文化を求めているのか、と思ったものです。それでうちでも、ジョン・ウォーターズの『ピンク・フラミンゴ』(72)や『フィメール・トラブル』(74)をレイトで上映することにしました」
『ピンク・フラミンゴ』はアメリカでは70年代に都市部の劇場で真夜中に公開されて、異例の大ヒットとなったが、その過激な内容ため、なかなか日本の土を踏めなかった。ディヴァイン扮するアブノーマルな巨体のヒロイン(といっても男)が、隣人たちと「どっちが最低な行為か」を競い合う。最後は犬の糞をめぐる衝撃的(いや、笑衝撃?)な場面も登場する。
「あの映画には他にも忘れらない場面があります。ある露出狂の人物が出てくるんです。本当は男ですが、見た目は女にしか見えない。正体が分かる場面があるんですが、当時は大事な場面にボカシが入り、そのユーモアが伝わらないんです。他にも『眺めのいい部屋』や『ルー・サロメ/善悪の彼岸』などにもボカシの箇所がありましたが、いま、考えると時代を感じますね。たいして意味のない場面も修正が入ると、逆になんだろう、と勘ぐったりして(苦笑)」
この時代らしい苦労(?)をしのばせるエピソードだ。修正の場合、そこだけビデオに落としてボカシを入れる方法が安上がりなので、画面の粒子が粗くなる。今では考えられないようなチープな修正技術がまかり通っていた。
『ピンク・フラミンゴ』を監督した伝説の監督、ジョン・ウォーターズは86年にパルコ劇場やスペース・パート3で開催された「ぴあフィルムフェスティバル」のニューヨーク・インディーズ映画祭のゲストのひとりとして、(新人だった)ジム・ジャームッシュや(無名の)スパイク・リーらと共に来日もし、インディペンデント界の新しい活気を伝える役割も果たした(ウォーターズは、毎日、違うジャケットと靴を着用して、とてもおしゃれだった。渋谷を見て、「まるで『ブレードランナー』(82)から抜け出てきたような街だね」と言っていた)。
「ウォーターズは若い恋人(男性)と一緒に来ていましたね。アメリカのインディペンデントの監督といえば、うちで上映した『セコーカス・セブン』(80)のジョン・セイルズも来日していて、僕がホテルに迎えに行った覚えがあります。ニューヨーク・インディーズとカルトムービーというのが、この頃のパルコのひとつのキーワードかもしれません」と根占さんは語る。
今のようにB級のゲテモノ映画だけを意味するのではなく、風変わりながらも、長い年月に渡って映画ファンに愛される映画が、当時はカルトムービーと呼ばれていた(もっと言葉の意味が広かった)。

◉昨年で34回を数えた新しい才能の発掘を目的とした「ぴあフィルムフェスティバル」は、第5回(1982年)から第10回(87年)まで、パルコ・スペース・パート3で開催されていた
◉幻の映画『エル・トポ』は、約20年潜伏したのち、日本で公開された
佐藤は海外で密かに買い求めた風変わりな未公開作を70年代から80年代にかけて新宿の自身の上映スペースで上映していた。プリントの状態はけっしていいとはいえない。しかし、幻の映画を目にできるだけで誰もが満足していたはずだ。非合法の上映だったが、そうした闇の中にいた伝説の映画をパルコという商業的な施設が拾い上げることでより多くの観客が目にすることになった。70年代のサブカルチャーの毒が、こうした上映によって失われた、という批判も耳にしたが、80年代に登場したミニシアターの多くが、日本で幻といわれた洋画の初公開に貢献しているように、パルコの劇場にもそういう動きがあったということだろう。
アレハンドロ・ホドロフスキー監督のメキシコ映画『エル・トポ』ではひとりの男の魂の旅が描かれ、シュールで、マカ不思議な映像を体験できる。『ピンク・フラミンゴ』は東映ビデオ(配給はケーブルホーグ)、『エル・トポ』はにっかつビデオが権利を持っていたようだが、これに関して根占さんは回想する。
「80年代半ばからビデオが売れた時代で、レンタルも伸びて、日本で出ていないものがないか各社が探していました。とにかく、何でも売れていた時代です。今はビデオを売ることを目的として劇場公開される作品もありますが、あの頃はそうではなく、まず劇場できちんと公開して、次にビデオという順番でした。『エル・トポ』などは僕たちの方から、ビデオ会社にポスターのアイディアを出したりしたものです」
インディペンデント映画を育てる動きは、洋画だけではなく邦画に対してもあった。パルコの製作で『ビリィ★ザ★キッドの新しい夜明け』(86、山川直人監督、高橋源一郎原案、三上博史主演)や『ウンタマギルー』(89、高嶺剛監督、小林薫主演)といった新人監督の作品も作った。前者に関しては86年7月27日『朝日新聞』首都圏ページに「自主映画に口出さず金出す」というタイトルのニュースが出ていて、既成の映画作りにとらわれない方法で製作を進めたことが、当時としては新しかったようだ。後者にはパルコが『セコーカス・セブン』、『メイトワン1920』(87)といった代表作を上映したアメリカのインディペンデント監督、ジョン・セイルズが沖縄の軍人役で出演しており、海外の映画祭でも評価された。
上映に関しては滝田洋一郎監督の風刺的な作品、『コミック雑誌なんかいらない!』(86)もかけた。「『コミック雑誌なんかいらない!』はピンク映画を撮っていた滝田監督が初めて手がけた一般映画で、過激な内容のせいか、他の劇場では断られたそうです。実はニュー・イヤー・ロック・コンサートを82年から87年にかけてパルコ劇場で行っていて、主演の内田裕也さんとつながりがあり、うちで上映することになりましたが、結果は大ヒットでした。内田さんはパルコのCFにも出演していました。いろいろなものがつながっていて、上映が実現した作品もあります。ナマの人間のつきあいがあって、それで生まれていったものも多かったです。他の劇場に断られた作品といえば、アレックス・コックス監督の『シド・アンド・ナンシー』(86)も別の劇場で決まらなくて、うちでかけて、結果的には大ヒットした作品でした。とにかく、パルコという箱に合うもので、自分たちがおもしろそうと思うものをかけていましたね。あの頃、赤字のイベントもありましたが、イメージ作りということで許されていました。今は黒字のようですが、冒険しなくなりました。僕たちは同じようなことをやるのが嫌いで、新人を発掘して育てたいという気持ちもありました」
新しい才能の発掘というのは、もともと、パルコが得意としていたことだ。増田社長はアート・ディレクターの石岡瑛子やイラストレーターの山口はるみ他、多くの才能ある人間たちにチャンスを与えることで、パルコのイメージアップに努めた。雑誌の『ビックリハウス』も萩原朔美や榎本了壱など多くの才人たちを輩出しているが、ゲリラ的におもしろいものに場を与えてきたパルコの劇場に対する姿勢自体がまさにビックリ満載の箱=家だったのかもしれない。
増田社長は演劇好きで、劇的な要素のあるものを好んでいた。自伝『開幕ベルは鳴った/シアター・マスダへようこそ』(東京新聞出版社)の中で「“パルコの中に劇場があるのではなく、劇場の中にパルコがある”。渋谷パルコに西武劇場を作った時の基本理念はこれでなければいけないと思った。(中略)ショッピングセンターとしては立地条件に恵まれていないパルコのイメージの中心に、しゃれた文化の発信基地としての劇場がなければいけない」と書いている。
この言葉を証明するかのように、80年代は渋谷に3つあったはずのパルコは、今はふたつだけ。75年にオープンしたパート2は耐震問題のせいで、07年で閉店となった。思えばパート2は劇場がないファッションビルだったが、生きのびたパート1にはパルコ劇場、パート3にはスペース・パート3があった。こうした劇場の持つ活気や熱気が、パルコというビル、ひいては渋谷の公園通りの個性を作っていった。
スペース・パート3の場合、常設館でないことがハンディとなり、都内にミニシアターが増えると、他の常設館へといい作品が流れていった。また、ロングランできないことやイベント会場ならではの簡易な椅子にも批判が出た。こうした状況をふまえて、90年代後半にスペース・パート3は、シネクイントという常設館に生まれ変わり、ヴィンセント・ギャロ監督・主演の『バッファロー'66』(98)などの大ヒット作を生むことになるが、この時もギャロをパルコのCFに出演させて話題作りを考えた。
劇場名は変わっても、映画館という箱にとどまらない動きをとることで、作品の多様性をアピールし、新たなページを開くことになったのだ。