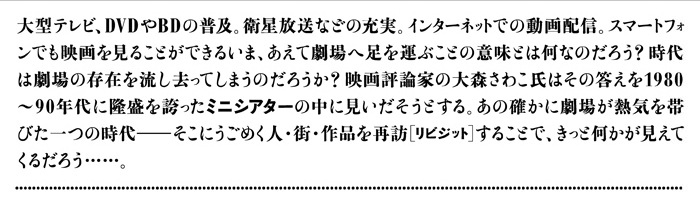1981年に渋谷で3つめのパルコが誕生した時、そのビルの8階に映画も上映できる多目的ホール、パルコ・スペース・パート3が設けられた。
ミニシアターが、まだ珍しかった時代。このホールは渋谷の先駆的なミニシアターの役割も果たし、ルキノ・ヴィスコンティやグレタ・ガルボの映画祭が話題を呼んだこともあった。
しかし、85年のシネセゾン渋谷、86年のシネマライズといったミニシアターが近くに出来ると、スペース・パート3の当初のインパクトは薄れていく。
「この劇場の仕事をするようになって、まずここは映画の常設館ではないんだな、ということを思い知らされました」
そう語るのはKUZUIエンタープライズで映画宣伝を担当した後、パルコの映像担当となった堤静夫チーフ・プロデューサーである。
入社した頃(93年4月)、ジャン=ジャック・ベネックス監督の『ベティ・ブルー/インテグラル』(92、GAGA配給)を上映していて、すごい人気だったが、そのホールではロングランが出来なかった。
「最初から7週間と決まっていたんです。毎回、人があふれるほどの人気でしたが、スペース・パート3は多目的ホールなので、最終日の翌日から映画に関係のない展示会が入っていてどうにもなりません。こんな大ヒット作に恵まれたのに、すごくもったいない、なんとかならないだろうか、と思い始めました」
ホールとしての限界を感じていたが、すぐに常設館には移行できなかった。
「まわりを説得して実現するのに、結局、5年ほどかかりました」
これまでスペース・パート3では映画の上映以外に、展示会、芝居、セールなど、さまざまなイベントが行われていたが、芝居チームにはパルコのパート1に〝パルコ劇場〟があるから、という理由で納得してもらい、他のチームも辛抱強く説得することで、常設館を作る計画が進んでいった。
ひとつの大きな転機となったのが、目の前のシネマライズで96年に上映された『トレインスポッティング』の成功だ。この作品はパルコが配給権も持っていて、スペース・パート3で封切ることもできたはずだが、当たりそうな予感があったので、あえて常設館のシネマライズに話を振ったという。その結果、33週間上映という異例の大ロングランとなり、当時の渋谷のミニシアターの興行記録を塗りかえた。もし、スペース・パート3が常設館なら、『トレスポ』の運命も、また違ったものになったかもしれない。
この映画のヒットから2年後の98年、従来の多目的ホールから映画の常設館への移行が決まり、椅子をこれまでの移動式から固定式のものに変え、床や音響施設などにも手を加えた。
翌年7月にスペース・パート3はシネクイントとして生まれ変わることになったのだ。
ミニシアター界で遅れをとってきたパルコの逆襲がこうして始まる。
この世紀、最後に渋谷に打って出るミニシアターとして、「どういう位置づけにするのか、劇場のコンセプトを考え直した」と堤プロデューサーは語る。
「僕はいわゆるヨーロッパのアート系映画が嫌いだったんです。ヴェンダースの映画とか、何がいいのかさっぱり分からない。『パリ、テキサス』(84)にしても、ライ・クーダーが音楽なので見ましたが、どうも……。シネマライズでかけていたレオス・カラックスやウォン・カーウァイの映画も、ピンとこなかった。でも、KUZUIで入れていたジョン・ウォーターズ監督の『ヘアスプレー』(88)は大好きで、思えばこの作品はスペース・パート3にかけていたんです。そこでエンタテインメント性もあるアメリカのインディペンデント映画を上映する劇場にしたいと思いました」
劇場の方向性を決めた後、オープニングの候補作を30本ほどリストアップして各社にアプローチしたが、海のものとも山のものとも分からない新劇場に対して各社の反応は鈍く、「自分で見つけるしかないと思い始めました」。
そこでスタッフ一同、改めて情報を集め直して候補作を探した。そんな中にヴィンセント・ギャロの監督・主演作、『バッファロー'66』(98)があった。
上映権を持っていたのはカルチャー・パブリッシャーズ、テレビ東京、キネティックの3社。キネティックはシネ・ヴィヴァン・六本木の初代支配人だった塚田誠一さんの新会社で、当社はこの映画に出資もしていた。
別の会社が宣伝すると聞いていたところにキネティックが現れ、最初は共同作業に対して不安もあったが、パルコとのミーティングの後、キネティックの若手スタッフたちが堤プロデューサーに駆け寄ってきた。
「この映画を絶対にヒットさせたいので、私達を信じてもらえませんか」
彼らの力強い言葉にひどく打たれるものを感じ、その熱意に賭けることにした。この作品をオープニングに決めた直後、パルコのCM担当の宣伝部からはこんな話も持ちかけられた。
「アメリカのエージェントから、ヴィンセント・ギャロって奴をお宅のCMで使わないか、という話が来ているけど、ギャロって知ってる?」
驚きながら、堤プロデューサーは答える。
「知ってるも何も、ギャロの主演・監督の映画で、来年、劇場をオープンするんですよ」
そんな風にとんとん拍子にCMの話も進んだ。
「これまで映画の側から、この人を使ってほしいと話を持っていって決まったことは一度もなかったので、この時は本当に驚きました」
『バッファロー'66』の宣伝では、ギャロを前面に押し出したプロモーションを考えたが、アメリカではパブリシティに非協力的な人物として知られていて、この監督デビュー作が公開された時は配給元のライオンズ・ゲイトと意見の対立があり、宣伝にはいっさい協力していないことが分かった(それも影響したのか、アメリカでの興行は成功ではなかった)。
実際、ギャロが来日してみると、かなりむずかしい性格だったという。
当時の彼には〝スター〟と呼べるほどの知名度はなかったが、来日時は「表紙に出られる雑誌しか取材に応じない」とゴネたこともあったという。
そんな彼のハードルの高い要求にも耐えながら、宣伝グループは必死に売り込みを続けていった。
「8カ月の宣伝期間がありましたが、毎週、会議を続けましたね。みんな死に物狂いでした。過去にオープンしたミニシアターは、シネマライズにしても、文化村のル・シネマにしても、一本目は大ヒットではなく、2本目や3本目から当たっています。でも、この時はオープニングからヒットさせるよう社から命じられていて、すごいプレッシャーでした」

一方、ギャロが出演するパルコのCMは劇場のオープニングに合わせてテレビで放映されることも決まり、マスコミでの売り込みも順調に進んでいった。
「結局、まわりから少しずつ盛り上がっていき、紙媒体だけで約1000本の記事が出ました。もう、最後は計測不能です、と宣伝チームは言っていました(笑)」
当時は公開前のヒット予測のバロメーターと言われた前売り券の売り上げも好調で、スペース・パート3時代には100枚か、200枚売れば成功のはずが、『バッファロー'66』は1500枚という異例の売り上げとなっていた。
シネクイントのオープニングとなった初日の99年7月3日、天候は雨だった。
「でも、天気は関係ないんですね。劇場は8階にあったんですが、そこから地下1階まで階段に列が出来ました。毎回、満席で、その長い列が2週間か、3週間ほど続きました。当時は指定席の制度もなく、ウェブでの予約もできなかったので、朝から来て劇場に並ぶしかなかったんです」
封切られた年の7月は暑く、エアコンも大して効いていない。
「自動販売機の飲み物が午後の1時か、2時ごろには売り切れになって、その時期の都内の自動販売機での売り上げが1番とも言われました(笑)。僕たちは近くのコンビニに水を買いに行って皆さんに渡したんですが、それさえも追いつかない状態でした」
結局、最初の6週間だけで興行成績は1億円を超えた。
ミュージシャンとしても活動するギャロは、その後、来日して俳優のルーカス・ハースと難解な実験音楽を、クラブ・クアトロを埋めつくした聴衆たちの前で披露したこともあった。
さらにトヨタの自動車、セリカのCMにも起用された。
「映画の入りが少し落ちてきた頃に、ライブや別のCMの話題が出てきて、とにかくギャロ騒動がおさまらない。次に上映が予定されていた作品は公開時期が入ったチラシを何度も刷り直していて、本当に気の毒でした」
99年7月に封切られた後、翌年2月まで34週間の興行となった。2億5000万円の興行収入で、約15万8000人を動員した。
「数字的には『トレインスポッティング』がそれまでの渋谷のミニシアター興行の記録でしたが、それも抜くことができて、よっしゃー、って気分でした」
実はクイントがオープンした〝99年の夏〟は、渋谷のミニシアター界の興行にとって特別な時期だった。シネマライズを訪ねた時、賴香苗専務はこの年についてこんな発言を残したものだ。
「あの年は渋谷の夏がすごく熱くて、いい時代でした。うちは本興行の『ラン・ローラ・ラン』(98)とレイトショーの『π』(97)が当たっていたし、お向かいのシネクイントは『バッファロー'66』、シネセゾン渋谷は『ロック、ストック & トゥー・スモーキング・バレルズ』(98)がヒットしていました。自分たちのところだけではなく、渋谷が映画で盛り上がっていて、すごくうれしかった。どこも若い感覚の映画を上映していて、本当に勢いがあった。あれは〝奇跡の夏〟だったと思います」
ちなみにシネマライズの本興行の『ラン・ローラ・ラン』は20週の興行で、1億1000万円の興行収入、7万人の動員。同劇場の『π』はレイトショー1回だけの興行にもかかわらず、20週上映となり、3400万円の興行収入、2万人以上の動員となっている。また、シネセゾン渋谷の『ロック・ストック・トゥー・スモーキング・バレルズ』も13週上映され、この劇場の歴代観客動員数で13位となっている。
今はひとつのミニシアターで10週間上映できれば、大ヒット作と呼ばれる時代。しかし、99年の渋谷・宇田川町周辺のミニシアターからは多くの驚異的なロングラン・ヒットが生まれている。当然、街にも若い観客たちがあふれていたわけで、この数字からも20世紀最後の渋谷の夏の異様な活気が伝わってくる。
その台風の目となった空前のバッファロー・ブーム。この映画のヒットの要因は何だろう?
「よく聞かれるんですが、あの映画はまず不器用なふたりのラブストーリーだと思うんですよ。恋人役のクリスティーナ・リッチはどこか幸薄そう。ふたりは別れるのかな、と思ったら、あの意外な結末で……。日本人が好きそうなラブストーリーだったんでしょうね。ギャロなんて、普通に考えると、ちっともイイ男じゃないし、性格もむずかしいけど、すごい人気でした。『バッファロー'66』の場合、音楽やスローモーションの使い方などが、映画としては新しかったのかもしれません。ただ、大ヒットの決定的な理由はよく分かりませんね」
当時、キング・クリムゾンやイエスなどの名曲を収録したオリジナル・サウンドトラックがタワーレコードやHMVといった渋谷のレコード店で大人気となっていた。劇中でヒロインがキング・クリムゾンの70年代の曲「ムーン・チャイルド」をバックにして、ボーリング場でたどたどしいタップダンスを踊る時の可憐さは忘れがたい。
この作品の当時の新聞に載った記事を拾ってみると――。
「監督・主演のヴィンセント・ギャロは異能の人として若いファンの支持がある。誘拐劇に始まって、家族の姿を描き、恋物語にたどりつく、この初監督作をギャロは『最高の映画』と断言する。画家としてキャリアがあり、またある時はオートバイレーサー。カルバン・クラインの広告に登場したモデルで、前衛画家の故バスキアと一緒にバンドも組んだ。〔中略〕しばしばあるように、マルチタレントは最後に映画監督へ、ということなのか。『分かってもらいたいのは役者が監督になったんじゃないってことだ。生涯に一度きりでいいから、最高最上の映画の中で演技したかったんだ。それには自分のすべてをつぎ込むに限る』」(『朝日新聞』99年7月6日夕刊)
「主演も兼ねたヴィンセント・ギャロの外見こそ普段のままだが、主人公の性格は純朴で内気。先の来日時に見せた素顔がそのまま現れたような、愛らしい作品だ。〔中略〕特にラストで、おくてのビリーが、おずおずとレイラに口づけをする場面は、最近では出色の感動的なキスシーンだ。忘れかけた胸のときめきを思い出させてくれる(多葉田聡)」(『読売新聞』99年8月10日夕刊)
堤プロデューサーが言うように、シンプルな〝ボーイ・ミーツ・ガール〟もので、ギャロ扮する刑務所帰りのダメ男が両親に会いに行くため、ダンス・スクールにいたクリスティーナ扮する女の子を誘拐して、妻のふりをさせる。「俺をたてろ!」「俺のいうことに逆らうな!」と、亭主関白的な態度を見せる男と彼に誘拐され、その言いつけに従う女。しかし、映画の後半になると、男の純情さが見え、純朴な女はそんな彼を愛し始める……。
多彩な才能を持ち、爬虫類のような顔をしたギャロの凶暴な不良性と内側に秘めた純情さ。それが分かりやすい形で出た監督デビュー作で、相手役を演じる子役上がりのクリスティーナの太めの体形もご愛嬌。主演が完璧な男女ではないからこそ、初々しいラブストーリーになっていた。
99年にオープンしたシネクイントにとって、この作品はいまだ、歴代記録ナンバーワンだが、ひとつには90年代の渋谷という街が持っていたパワーが発揮されることで、この予想外の大ヒット作も生まれたのだろう。
ミニシアターでの1作目は大ヒット作にならない、というそれまでのジンクスを覆して、『バッファロー'66』はロングランとなり、それまで後手にまわっていたパルコ・スペース・パート3改め、シネクイントの力も世間に知らしめた。
翌年の2000年にはロンドンの地下鉄をテーマにしたオムニバスのイギリス映画、『チューブ・テイルズ』(99、アミューズ)が15週のロングランとなった。こちらも『バッファロー'66』同様、本国では埋もれた作品だったが、ちょうどミステリーの『リプリー』(99)が公開されてジュード・ロウ人気が盛り上がった時に封切られることで、彼の監督作も含んだオムニバスということで注目された。

そして、この作品をシネクイントに提供したアミューズ・ピクチャーズ(後の東芝エンタテインメント、現在はショウゲート)が次にシネクイントに持ちかけたのが、ミステリーの『メメント』(00)だった。当時は無名の新人だったクリストファー・ノーランの監督作だ。
その後、『バットマン』3部作(05~12)や『インセプション』(10)といった大作を撮り、今やハリウッドを代表する売れっ子監督のひとりとなったノーランの出世作である。堤プロデューサーはこの作品の話が来た時のことを振り返る。
「初めて見た時、字幕がまだ入ってなかったんです。そのせいか、うちのスタッフたちはみんな乗れなくて、うちのイメージじゃないという声もありました。ただ、何か気になるので、字幕入りをもう一度、見せてもらいました。すると、ぐっと分かりやすくなっていて、『これはすごい映画じゃないか』ということになりました。すごく頭のいい人の書いたホン(脚本)だと思いました」
主人公は記憶喪失の男(ガイ・ピアース)で、彼は妻殺しの犯人を追っている。しかし、記憶が10分しか続かないため、ポラロイドで撮影した写真や自分の体に描いた数字や名前を頼りに事件の捜査を続ける。
そんな主人公の行動が時計の針とは逆回転の時間軸で描かれ、見る者を大いに混乱させる。カラーとモノクロを交互に使った映像構成も大胆で、こちらを最初から最後まで挑発し続ける知的なミステリーだ。
「公開前にクリストファー・ノーランに内容を簡単に説明してもらうナレーションを書いてもらい、それを上映前に、毎回流しました。内容が分からない、といわれるのが怖かったんです。でも、そんな不安は不要でした」
シネクイントでの封切りは01年の11月3日だった。
「初日はどこかに不安がありました。実際、1回目と2回目の入りはそうでもなかったんです。ところが、3回目の午後からすごい入りになったんです。その後はどんどん口コミで人気が広がり、ありゃりゃという感じで、毎週、興行が上がっていきました」
結局、25週の上映となり、1億5000万円の興行収入をあげ、約9万3000人の動員となった。難解そうに思えた作品の内容を考えれば快挙ともいえる数字で、この映画に関してはリピーターも多かったようだ。
「その後、クリストファー・ノーランはシネクイントから出ていますね、と言われるようになりました。劇場というより、配給会社の力だと思いますが、とにかく、彼の才能を世間に認めさせた作品ですよね。『バッファロー'66』もそうでしたが、この作品もうちだけの単館上映。こういう作品を都内で単館上映できる幸せな時期でした。単館公開すると、劇場に人があふれかえる熱気のある興行が実現できるんです」
都内の単館上映が実現したおかげで、『メメント』はシネクイントの歴代興行の第2位となっている。
「今ではシネコンが増えたので、映画のブッキングがいくらでもできます。もし、『メメント』のような作品がいま出てきたら、何館かで同時に上映して、そこそこ入って消えていく。そんな興行になったかもしれません。お客さんにとっては都内のいくつかの映画館での同時上映の方が便利かもしれませんが、その分、上映期間は短くなるし、作品への思い入れも半減します。かつては同じ映画を地方で上映していても、渋谷で見たいという観客がいたし、かなりのこだわりを持ってミニシアターでは上映していたわけです」
ちなみに『メメント』が当たっていた頃、向かいのシネマライズでは『アメリ』(01)を上映中で、こちらもすさまじいヒットとなり、35週の興行となっていた(シネマライズの歴代興行のナンバーワン)。渋谷のミニシアターの勢いは21世紀初頭も続いていた。
そんな勢いの中でシネクイントはよりエンタテインメント性の強い作品を上映することで、アート志向の強かったシネマライズとは別の路線を歩み始める。
エンタメ路線のひとつの突破口になったのが01年に上映されたSF映画のパロディ『ギャラクシー・クエスト』(99)だが、『スタートレック』の風刺版とも思える内容のコメディで、12週間のロングランとなり、配給元だったハリウッド系のメジャー会社、UIPのスタッフも大喜びだったという。
この作品の公開時は劇中の宇宙服を着た主人公たちの構成をなぞらえ、「男性5人の男と女性1人のグループで、女性が金髪で来場した場合、1人が1000円になる」という割引を行った。また、同じ年に14週のロングランとなったタイ生まれのスポーツ・コメディ『アタック・ナンバーハーフ』(00)はニューハーフのバレーボール選手の活躍を描いた作品だったので、「バレーのユニホーム姿の6人組は1000円になる」という割引を導入したところ、場内はジャージ姿の観客たちであふれ返ったという。オープン当初からシネクイントは他の劇場との差別化を図るため、上映作品にちなんだ扮装をしてきた観客は1000円(通常は1800円)で入場できたが、こうした遊び心が発揮された興行が、若い層をターゲットにしてきたシネクイントの特徴のひとつでもある。
若い感性の邦画の興行も積極的に行ってきた。歴代興行の第3位は犬童一心監督の代表作『ジョゼと虎と魚たち』である。03年の12月に封切られ、17週の興行。辛辣な言葉を吐く足の不自由な女の子(池脇千鶴)とナイーブな大学生(妻夫木聡)との純粋な愛の物語で、主演ふたりからベストの演技が引き出され、心にしみるラブストーリーとなっている(原作は田辺聖子の短編小説)。日本の人気バンド、くるりの担当した音楽も印象的だ。
この作品は翌年04年の4月まで上映となっているが、堤プロデューサーに言わせると、04年は邦画の当たり年で、『下妻物語』(10週上映)や『スウィングガールズ』(7週上映)もかけられ、どちらも大ヒットとなった。
「この年は邦画が絶好調でした。『下妻物語』は東宝に初めて声をかけていただいた作品で、まだ、映画が出来上がる前にシナリオを読んだら、すごくおもしろかったので、少しだけ作品に出資しました。出資までしたのは、これが初めてでしたが、その後はこうしたケースが増えていきました。出資も含めて東宝のような大手の邦画が上映できるようになると、選択の幅が広がっていきました」
こうして若者向きの邦画にも強いミニシアターというイメージが定着していく。歴代の興行成績を振り返ってみると、ベストテンのうちの半分が邦画である(『ジョゼと虎と魚たち』『告白』〈10〉『下妻物語』『デトロイト・メタル・シティ』〈08〉『ハッシュ!』〈01〉『嫌われ松子の一生』〈06〉)。11位以下も『刑務所の中』(02)『さくらん』(07)『キサラギ』(07)とエンタメ性も含んだ邦画がズラリと並ぶ。
21世紀に入ってから洋画以上に邦画が興行界で力を持ち始めたが、そんな傾向がシネクイントのヒット作からも読み取れるし、邦画に強いイメージも作り上げることで、21世紀を生きぬくミニシアターとしてのパワーも獲得できたのだろう。

◉2014年公開の『トーキョー・トライブ』も、好調だった
洋画に関しては、ダニー・ボイル監督のホラー映画『28日後…』(02)のヒットでつながりができた大手の20世紀フォックス配給の良作も積極的に上映している。特に幼い娘を少女のミスコンに送り込もうとする落ちこぼれ一家の再生をユーモラスに描いた『リトル・ミス・サンシャイン』(06)公開が実現できたことを堤プロデューサーは誇りに思っている。
「最初にアメリカのサンダンス映画祭で見た後、配給元のフォックスに連絡を入れました。派手な作品ではなかったんですが、すごくおもしろくて、ぜひ上映したいと思いました。観客動員はおどろくほどすごい数字ではありませんでしたが、なんとか9週上映しました。上映中に作品賞を含むいくつかのアカデミー賞の候補になりました。もし、最初から賞にからむと分かっていたら、映画会社もチェーン系公開にしたかもしれないし、賞にターゲットをあわせた時期に封切ったかもしれませんが、賞が発表された頃、すでにうちの劇場で上映中でした。この時、作品賞を獲ったのは『ディパーテッド』(06)でしたが、クオリティは『リトル・ミス・サンシャイン』の方がずうっといいと思いました。この作品に関しては興行成績うんぬんではなく、この映画をうちで上映できて本当に良かったね、とみんなで話が盛り上がりました」
06年にかけた『リトル・ミス・サンシャイン』に続き、現代の男女の軽妙なラブストーリー『(500)日のサマー』(09)もフォックスの配給作品で10年に上映された。どちらも映画業界内で評判がよかった。いかにも売れ線の作品だけではなく、玄人受けする質の高い作品も上映してきたわけだが、とにかく、どんな時も「見て楽しめる作品」ということを基準に選んできた。
「過去のミニシアターにはどこか上から目線のところもあったかもしれませんが、それはイヤだったので、目線をお客さんに合わせようと思って始めました。自分たちがおもしろいと思うものを上映し、むずかしいと思うものはやらない。むずかしいものは自分たちも分からないことがあるからです」
エンタメ性を打ち出した大衆的な作品のセレクションにこだわることで運営を続けてきたが、かつての観客と今の観客はどこが違うのだろう?
「そうですね……今の観客には自分で作品を見つけようとする動きがありませんね。だから、他とは違う作品の上映にこだわってきたミニシアターが衰退していったのかもしれません。初日を見ていても、劇場に駆け込んでくる、みたいな熱気がありませんね。何日も〝待ってました〟みたいな感覚がないんです。『バッファロー'66』の頃のように、今は映画館に並んで待つという熱いものが欠けています。それに複数の映画を同時上映しているシネコンに慣れた若い観客が増えたので、たとえば、目的の映画が混んで見られない場合、その作品にこだわるのではなく、別の映画でいいや、となってしまうようです。うちの場合、〝ここは1館しかないの?〟と言われることがあります」
都内のミニシアターの中には、中高年やシニア層をターゲットにした映画館もあるが、シネクイントは今も若者を意識した作品をセレクションしている。
「若者向けのものをずうっと選んでいくのは確かに疲れますが、だからといってシニア向きの作品は上映していません。渋谷の場合、センター街という深くて黒い川を渡ることをシニアはいやがるので、シネクイントに来ないと思います。それに『下妻物語』や『告白』の中島哲也監督がこんなことを言っていました。『どうせ映画を撮るんだったら、若い奴らを喜ばせたい。そうすれば、その人生に影響を残すことができるから』。だから、大変なんですが、若い層を意識しつつ、今後も独自のカラーを出していきたいと考えています」
シネクイントがスタートして15年。渋谷が熱かった〝99年の夏〟に産み落とされたパルコ発のミニシアターとして、その挑戦と模索が続いている。

◉シネクイントは渋谷区宇田川町14-5、渋谷パルコ・パート3の8Fに所在
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。