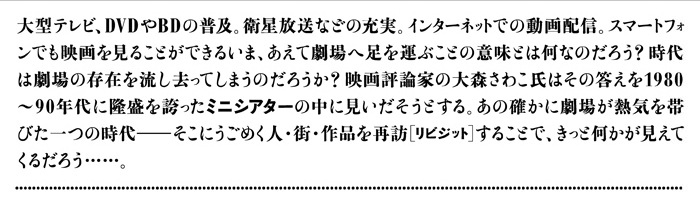80年代、渋谷の宇田川町の周辺には複数のミニシアターがあった。
公園通りの近くのパルコ・パート3の中にはミニシアター的な役割も果たしていた多目的ホール、スペース・パート3(1981年オープン、後のシネクイントとなる)、その目の前にシネマライズ(86年オープン)、駅に近いビル、ザ・プライムの中にはシネセゾン渋谷(85年オープン)。
宇田川町周辺にはレコードショップやライブハウスが集まっているせいもあり、こうした劇場では若い層を狙った都会的な作風の映画が上映されていた。
また、駅の反対側の桜丘町にあったユーロスペース(82年オープン)は独自のインディペンデント路線を歩み、よりマイナーで実験的な作風のものを上映していた。
当時のこうした渋谷のミニシアターとは異なる路線を打ち出し、東急沿線に住む大人の女性層をターゲットにした映画館が80年代最後の年にオープンすることになった。
東急本店に隣接した2つのミニシター、ル・シネマの1と2である。他のミニシアターとの大きな違いは、この劇場がBunkamuraという複合文化施設の中にある点だ。
Bunkamuraにはオペラ、バレエ、クラシックコンサートや演劇が上演できる2つのホール(オーチャードホール、シアターコクーン)と美術館(ザ・ミュージアム)もあり、さらにパリの有名なカフェの初の海外業務提携店であるドゥ マゴ パリも入っていた。
「最初にBunkamuraのコンセプトを聞いた時、とても便利で、都合がいい場所ができるな、と思いました。ビルの中にいろいろな施設が入っているので、カルチャー好きはそこでいろいろな体験ができるからです」
オープン当初の印象をそう振り返るのは、ル・シネマの番組編成を25年にわたって担当してきた中村由紀子プログラミング・プロデューサーである。
Bunkamuraがオープンした89年はひとつの歴史の転換点となった年だ。海外では11月にベルリンの壁が崩れて、東西の冷戦が終った。日本では1月に元号が昭和から平成になった。当時の日本にはバブル経済の最後の勢いが残っていた。
だからこそ、Bunkamuraのようにゴージャスな文化施設の誕生も可能だったのだろう。
ミニシアターも併設されたカルチャービルといえば、セゾングループが作った六本木のWAVE(83年オープン)もすでにあったが、こちらは文化全体というより、映像とサウンドにこだわったカルチャービルだった。
しかし、東急本店の駐車場跡地に建てられたBunkamuraはもっと敷地が広くて大がかりだったし、デパートに隣接して作られることで、そこに来る大人の女性層を意識した文化施設がめざされた。
発案者は生前、東急電鉄の社長と会長をつとめた五島昇。プレ文化村計画が動き始めたのは82年で、具体的な建設計画は84年に発表され、その5年後、遂にオープンにこぎつける。
「五島会長は残念ながらBunkamuraがオープンの時は亡くなられていたんですが、あの頃、企業は文化に注力しなくてはいけない、という考え方があったと思います」
中村プロデューサーは当時をそう振り返る。
この渋谷の新しい施設には関係者以外からも大きな期待が寄せられていた。パルコの責任者として渋谷の街作りに貢献してきた増田通二社長が86年にこんな記事を新聞に発表している。
「東急さんは、東急百貨店の屋上にある『東横劇場』を廃止し、本店裏に『東急文化村』と呼ばれる施設の建設を進めている。(完成後は)渋谷は他の盛り場に水をあけることができるでしょう」(『朝日新聞』86年10月10日朝刊)
このコラムのタイトルは「街は劇場だ」。演劇やイベントのためのスペースも併設した3つのパルコの渋谷進出によって、特に宇田川町の周辺は活気のあるエリアとなったが、増田社長は「劇場があることで街も栄える」というのが持論だった。だからこそ、自社とは関係のない東急の新プロジェクトにもエールを送ったのだろう。
もっとも、そんなパルコを東急側は別の視線でとらえていた。
「パルコなどの作り出した文化はあくまでもCMなどのイメージ中心のものだというのが我々の考え方だった。そうではなく、もっと本格的な文化を作り出したい。東横店西館にあった東横劇場は下に地下鉄銀座線が通るので、その騒音が聞こえてくるようなホールだった。本格的な文化を提供するにはちゃんとした劇場やホールがどうしても必要だった」と(当時の)東急百貨店の三浦守社長は語っている(Bunkamura編『喝采 SHIBUYAから』〈文化出版局刊〉より)。
パルコは確かにCMの印象が強く、そのターゲットはサブカルチャー的なものを好む若者たちだ。
しかし、東急が作ったBunkamuraは前述のように大人の女性層を意識した方向がめざされた。ひとつには高級住宅街として知られる松濤地区に隣接して立っているという立地条件もあったのだろう。
「渋谷は公園通りの近くにかつては危ない雰囲気も漂っていたセンター街があり、原宿に続くポップな路線があったり、神泉のあたりはかつて花街だったり、いろいろなものが混在した街です。そんな中で大人もくつろげるスペースをめざしたのがBunkamuraではなかったかと思います」
中村プロデューサーはこの施設の方向性についてそう語る。
映画館のプレ・オープンは89年9月3日。ル・シネマ1で上映されたのはフランスの人気監督、クロード・ルルーシュ監督のフランス映画『遠い日の家族』(85)。また、ル・シネマ2ではドイツの怪優、クラウス・キンスキーが天才的な音楽家、パガニーニに扮した『パガニーニ』(89)。後者はコンサート・ホールも併設されたBunkamuraの個性を考慮に入れることで選ばれた作品だ(当初の客席数は164席と128席。現在は150席と126席になっている)。
それまでヘラルド映画のビデオ部門で、シネマスクエアとうきゅうの上映作品のビデオ化にもかかわった中村プロデューサーであるが、Bunkamuraに入ったのはオープンの半年前。入社後はすぐに作品選定にかかわった。
「最初の2本は当初から4週間と決まっていました。その後、東京国際映画祭の会場にBunkamuraが使われることになっていたからです。ただ、この2本のオープニング作品も予想以上に当たりました。ひとつにはBunkamuraというこれまでなかった施設が新鮮で、みなさんに興味を持っていただいたおかげだと思います」
東京国際映画祭の後、10月7日からグランド・オープン作品として上映されたのが、フランスの女性彫刻家、カミーユ・クローデルを主人公にした伝記ドラマ『カミーユ・クローデル』(88、ヘラルド・エース配給)だ。

「Bunkamuraができる前に東急百貨店の催事場で『カミーユ・クローデル展』が開かれたこともあって、私自身もそれを見たことがありました。カミーユの伝記映画の話を聞いた時、この作品でグランド・オープンできたら素晴らしいだろうな、と思っていましたが、それが実現できました」
カミーユは彫刻家ロダンの愛人としても知られており、彼への愛と創造者としての葛藤をかかえながら、やがては精神を病んでいく。情念のままに生きるヒロイン役を演じるのはフランスの人気女優、イザベル・アジャーニ。ロダン役はフランスを代表する演技派男優で、後にル・シネマの大ヒット作、『シラノ・ド・ベルジュラック』(90)にも出演したジェラール・ドパルデューである。
「あの頃のアジャーニは脂が乗り切っていて、日本にキャンペーンで来日した時も本当にきれいでした。カミーユはロダンと同じ時代を生きたがゆえに運命の歯車が狂ってしまいます。でも、それが不幸だったかどうかは分かりません。この時代を生きなければ語り継がれることがなかったかもしれないからです。当時の興行は圧倒的に女性客が多く、主婦層が中心でした。平日の朝や昼に、こんなにお客様が来るんだな、と驚かされました」
最終的にこの作品は35週(のべ41週)にわたるロングランとなり、1億5000万円の興行収入を上げ、11万人を動員した。ル・シネマの歴代興行成績の第4位である。
「この作品の興行を見て、Bunkamuraはこういうお客様をターゲットとして考えればいいのだな、と思いました。そこで女性の生き方を描いた作品を中心にした番組を組むようになりました。映画だけではなく、ザ・ミュージアムも女性の作家にこだわる傾向がありました。そこで美術館と連動して、Bunkamuraで一日過ごしていただけるように考えていきました」
『カミーユ・クローデル』が当たった89年から90年にかけての日本はまだ経済状況も豊かで、好奇心がいろいろな方向に広がっていた。特に86年4月からは男女雇用機会均等法も施行され、社会に対する女性の意識も変化した。
「当時はカルチャーの部分にも女性の意識や志向性が反映されていたと思います。ブランド物への好奇心も高まり、見たい、知りたい、着たい、食べたい、と自分の欲望に対して人々が貪欲になっていきました。また、自分が知らないことに対して、見なきゃ、知らなきゃという危機感もあり、分からないことに対して分からないと言えない。むしろ背伸びがかっこよく思えたものです」
そんな時代を背景にして『カミーユ・クローデル』は大ヒットとなったわけだが、今、再見すると、ひたすら自身の情熱や情念に忠実に生きるヒロイン像に公開当時の社会が持っていた〝熱〟を重ねて見てしまう。
アジャーニの主演作は95年2月には『王妃マルゴ』(94、ヘラルド・エース配給)もかけられ、こちらも26週(のべ37週)にわたるロングランとなる。1億3000万の興行収入で、歴代の第6位だ。主人公は奔放な愛に生きた16世紀の実在の王妃で、彼女を取り巻く人間模様を華麗さと残酷さが合体したダークな映像で描き出した歴史大作だ。
「ここではアジャーニも目立ちますが、彼女だけではなく、実は男優たちもよかったんです。ジャン=ユーグ・アングラードやダニエル・オートゥイユも出ていて、彼らは当時の売れっ子でしたが、アジャーニの相手役を演じたのはヴァンサン・ペレーズでした。あの頃、〝目で妊娠させる男優〟なんて呼ばれ、女性に人気がありました。イケメン映画としても楽しめる作品なんですよね」
そのペレーズがフランスのゴージャスな大スター、カトリーヌ・ドヌーヴの相手役をつとめたラブストーリーが『インドシナ』(92、ヘラルド・エース配給)。こちらは92年10月にかけられ、30週(のべ36週)の大ヒットとなり、1億5000万円の興行収入。歴代の第3位となっている。
こうした華やかな女性路線が成功することで、ル・シネマは多くのヒット作を生み出していった。
そんな中で中村プロデューサーが特に忘れがたい監督として上げたのが、ポーランドのクシシュトフ・キェシロフスキとフランスのパトリス・ルコントだ。
キェシロフスキは91年10月にまずは『愛に関する短いフィルム』(88、KUZUIエンタープライズ配給)がかけられ、92年6月に『ふたりのベロニカ』(91、同)、さらに94年7月からは「トリコロール3部作」(同)が公開され、女性たちに圧倒的な人気を得た。
フランスの国旗の3色になぞらえてつけられたタイトルで、『トリコロール/青の愛』(93)にはジュリエット・ビノシュ、『トリコロール/白の愛』(94)にはジュリー・デルピー、『トリコロール/赤の愛』(94)には『ふたりのベロニカ』で監督のミューズとなったイレーヌ・ジャコブが主演。個性の異なる3人の女優たちがそれぞれの愛の形を見せてくれる。特に興行が良かったのは『青の愛』で15週の上映となった。
その才能に惜しまれながら、キェシロフスキは、「トリコロール」シリーズの日本公開から2年後の96年に54歳で亡くなった。
「心臓に持病がある監督で、これから、という時に亡くなったのが本当に残念でした。彼の映画はホン(脚本)も確かに素晴らしいのですが、何よりも映像で物語を語る作家だったと思います。シンプルなストーリーをひじょうに情感豊かに描いていて、何年かたってから彼の作品を見直すと、また違う思いがわいてきます。『ふたりのベロニカ』を久しぶりに見た時は、そのみずみずしさに涙が出ました。『青の愛』の時はジュリエット・ビノシュと一緒に監督が来日したんですが、側でふたりを見ていると、ビノシュが監督を全面的に信頼していることがよく分かりました」
この3部作はポスターにも力を入れていて、『青の愛』は石岡瑛子、『白の愛』は内藤忠行、『赤の愛』は横尾忠則が担当し、上映時には表参道のスパイラルビルの中のスパイラルホールで、アートポスター展も開かれ、好評を博した。
一方、『髪結いの亭主』(90)以降、日本のファンを獲得したパトリス・ルコントの魅力について中村プロデューサーはこう語る。
「おそらく、世界中で日本が1番彼の映画を支持してきた国ではないかと思います。たぶん、あの湿り気が受けたんでしょうね。ヨーロッパの監督には珍しく、日本的な色気を持っている監督だと思います。だから、『髪結いの亭主』というちょっとレトロで日本的なタイトルがはまったんでしょう」
91年12月にかけられた『髪結いの亭主』は19週の上映で、1億円の興行収入を上げ、歴代興行成績の10位に入っている。この時の映画のキャッチコピーは「かほりたつ、官能」。映画ではアンナ・ガリエナ扮する大人の色香を漂わせた髪結いの女とジャン・ロシュフォール扮する中年の亭主との愛が描かれるが、結婚10年後に意外な結末が訪れ、男と女の愛の不可解さについて考えさせられる。ガリエナは日本にも何度か来日して、〝大人のイイ女〟としてその魅力をふりまいていた。
ルコント作品はこれまで8作品がル・シネマにかけられていて、歴代興行成績の9位に93年封切りの『タンゴ』(92、19週上映)、20位に99年封切りのヴァネッサ・パラディ主演の『橋の上の娘』(99、17週上映)、23位に96年封切りの『パトリス・ルコントの大喝采』(96、7週、のべ14週)と、多くの作品が好調な成績を残している。

また、フランス映画としては92年にかけられたジャック・リヴェット監督の『美しき諍い女(いさかいめ)』(91、コムストック配給)もル・シネマの忘れがたい一本だろう。世捨て人の画家(ミシェル・ピッコリ)と彼のモデルだった妻(ジェーン・バーキン)。新たに画家のモデルとなる若い女性(エマニュエル・ベアール)。そんな3人の愛と芸術をめぐる葛藤を描いたオノレ・ド・バルザック原作のドラマである。
リヴェットは本国では高い評価を得ていて、日本ではこの作品でやっと本格的に認められたが、さらに女性の裸体の修正問題を揺さぶった作品としてもマスコミでは話題を呼んだ。
「東京国際映画祭にも出品するということで、修正に関しては配給会社の方がすごくがんばって下さいました。上映されたのが大劇場ではなく、小さなキャパのアート系シアターだったことが、もしかすると幸いだったかもしれませんね」
当時、コムストックの宣伝部は映倫にも出向いて、修正に関して闘ったという。作品自体もこの年の「キネマ旬報」のベストテンの外国映画部門の1位に選ばれ、興行成績も好調だった。
「長尺もので1日3回しか上映できなかったのですが、当時、かなりヒットしまして、10週以上は上映しました。この頃は連日満席が続いていて、それが当たり前に思えた時代でした」
90年代のル・シネマは絶好調で、歴代興行成績のナンバーワンもこの時代に生まれた。97年11月に封切られたジャック・ドワイヨン監督のフランス映画『ポネット』(96、エース・ピクチャーズ配給)である。
母の突然の死を受け入れることができない少女、ポネットが主人公で、当時、4歳のヴィクトワール・ティヴィソルがヴェネチア映画祭で最年少の主演女優賞を受賞したことも話題を呼んだ。
「あの作品はやはり〝子供のパワー〟あってのヒットですね。ドワイヨンは当時シネアスト系に好まれる監督でしたが、監督の名前は前面に出さず、アートで売ることはやめました。むしろ、ヒロインの少女のひたむきさを押し出しました。どうしたら、死んだママに会えるんだろう、と思っている少女のいたいけな表情を大事にして、少女の顔をアップにしたポスターを作りましたが、そこに物語を感じさせる力があったと思います。出てくる子供たちは素なのか、演技なのか分からない凄さがあって驚かされました」
昔から映画界では「動物と子供の映画は当たる」と言われてきたが、ミニシアター作品では子供を売りにしていた作品がそれほど多くない。それゆえ、当時の観客たちには、むしろ新鮮に思えたのかもしれない(子役が特に印象的だったミニシアターの大ヒット作には『ミツバチのささやき』〈73〉や『ニュー・シネマ・パラダイス』〈89〉もある)。
『ポネット』は33週間の大ロングランとなり、2億円を突破する興行成績を上げ、12万8000人を動員した。
中村プロデューサーはこれを「最も観客層の幅が広かった作品」と位置づけている。
「とにかく、老若男女の観客層で、下は中学生、上は年配の方まで、本当にいろいろな方が来て下さいました。観客の層の広さが歴代1位という興行成績に結びついたのでしょう」
『ポネット』は少女の可愛さだけを売りにした作品ではなく、母と娘の物語でもあり、フランス人の哲学的な死生観も入っている。その奥ゆきの深さが目の肥えた客層に受けたのだろう。
ル・シネマはフランスだけではなく、イギリス映画の秀作も上映してきた。歴代成績12位と健闘しているのがイギリスの文芸映画『鳩の翼』(97、20週上映、エース・ピクチャーズ配給)だ。今はハリウッド映画でも活躍する人気女優、ヘレナ・ボナム=カーターが大胆なヌードも見せて悪女的なキャラクターに挑戦し、初のアカデミー賞候補になったコスチューム劇。サンディ・パウエルがデザインした衣装の優雅さにも目を奪われる。
原作は文豪のヘンリー・ジェームズで、舞台はヴェネチア。女ふたりと男ひとりの屈折した愛が美しい映像で描かれ、ホロ苦い結末が訪れる。
「文芸映画が強かった時代が確かにありましたね。名作と呼ばれていても、意外とみんなが読んでいない小説があり、『鳩の翼』もそうした作品のひとつだったのかもしれません。そこでせめて映画版は見ようと思って劇場に来て下さったのでしょう。イギリスの俳優たちは舞台出身の人が多いので、どこか高貴なイメージや信頼感があり、いつの時代も安定した人気を得ている気がします」
イギリス映画としては、ゲイの作家、リットン・ストレイチと女流画家、ドーラ・キャリントンの風変わりな愛と人生を追った『キャリントン』(95)、カズオ・イシグロ原作の切ない愛のドラマ『わたしを離さないで』(10、ソニー・ピクチャーズ)といった文芸ものも好調だった。後者は公開時にNHKで放映されたカズオ・イシグロの特別番組も評判となった。
「『わたしを離さないで』は原作をすでに読まれた方が多かったようで、シャンテとの公開で7週間の上映となりました。おそらく、お客様は知性や気品を英国映画に求めているのでしょう。英国の場合、ガーデニングや紅茶なども人気もあり、そういう文化や作法を求める観客層がいて、劇場的には数字が読める部分もあります」

一般的にはフランスを中心にしてヨーロッパ映画に強い劇場という印象が強いが、実はアジア映画にも数々の忘れがたい作品がある。
その筆頭に挙げられるのがチェン・カイコー監督の代表作『さらば、わが愛/覇王別姫』(93、ヘラルド・エース配給)だろう。94年2月に封切られ、26週(のべ43週)のロングランとなり、1億7000万円の興行収入。この劇場の歴代2位で、9万6000人を動員した。
今世紀初頭の中国で京劇の役者としてコンビを組むふたりの男の愛と人生に迫るドラマで、女形の役者を演じたレスリー・チャンにははっとする美しさがある。また、男たちの間に割り込む元娼婦役のコン・リーも力強い存在感を発揮する。
中国の〝第五世代〟と呼ばれた監督のひとり、チェン・カイコーのパワフルな演出と歴史のうねりをとらえた圧倒的なカメラワーク。骨太のドラマと「午前10時の映画祭」でも上映されている。
「この年のカンヌ映画祭のパルムドール(大賞)を『ピアノ・レッスン』(93)とともに受賞した作品ですが、幸運にも映画祭の前に上映を決めていました。ヘラルド・エースの原正人社長〔当時〕に〝ちょっと、見てみない?〟と、まずは連絡をいただきました。最初、見た時は字幕もなく、詳しい内容は分かりませんでしたが、その後、カンヌ映画祭で大賞を受賞できたのはうれしい驚きでした」
ヨーロッパ志向の強かったル・シネマにとって、この作品は初めてのアジア映画だった。
「この作品で華々しいアジアデビューをさせていただきましたが、26週のうちの17週はル・シネマの1と2で上映しました。お客様はどちらかといえば男性客が多く、ひとりで40回、見たという方もいらっしゃいました。当時は中国に対する情報があまりなくて、劇中に登場する文化大革命のこともそれほど明かされていなかったようです。芸術家同士で告発し合う場面も出てきますが、中国の〝第五世代〟にとって、この部分は創造のための核になっていて、中には強制的に農業を強いられた人もいました。長い年月にわたる物語なので、年齢を重ねた後に見た方がさらにぐっとくる作品ですね」
初めて日本のミニシアター(シネマスクエアとうきゅう)で上映されたカイコー作品は『黄色い大地』(84)だったが、ヘラルド・エースはこの監督の作品を配給し続け、会社名がエース・ピクチャーズと変わってからは、レスリー・チャン、コン・リー主演のラブストーリー、『花の影』(96)も配給。このカイコー作品もル・シネマで17週(のべ22週)の上映となり、歴代の第14位だ。
日本でも人気を得ながら、2003年に46歳で自ら命を絶ったレスリー・チャンについて中村プロデューサーはこう回想する。
「『さらば、わが愛/覇王別姫』のレスリーは京劇の美しさを見せてくれました。彼が亡くなった時は本当にショックでした。自分のファンをすごく大事にする人で、ファンの列が切れるまできちんと握手していた姿が忘れられないです」
21世紀に入ってからはクラシック音楽をテーマにしたカイコーの人情劇『北京ヴァイオリン』(02、シネカノン)もル・シネマに登場し、15週間の上映。歴代の第19位となった(カイコー作品は3本、20位内に入っている)。
また、チェン・カイコーと並ぶ、〝第五世代〟の監督のひとりであるチャン・イーモウ監督の『初恋のきた道』(99、ソニー・ピクチャーズ)は24週上映され、歴代の5位。コン・リーに代わって、チャン・イーモウ監督の新たなミューズとなった新人女優、チャン・ツィイーの純情可憐な演技が評判を呼んだが、この作品については「男性客が多くて、見た方が号泣されていました」と中村プロデューサーは語る。
一方、女性層を意識して成功したアジア映画が、2001年にかけられたウォン・カーウァイ監督の『花様年華』(00)。カーウァイ映画に縁の深いマギー・チャンとトニー・レオンが主演で、心の奥に秘められた愛が主人公の眼差しや指の動きなどで官能的に表現された大人のためのラブストーリーだ。
「カーウァイ作品はシネマライズで『天使の涙』(95)、『ブエノスアイレス』(97)等が上映されていましたが、ル・シネマでもいつか上映したいと思っていました。『花様年華』は女性層狙いだったのでうちにまわってきましたが、本当に美しい映画でした。主演のふたりは西洋人にはない魅力があり、あれこそアジアン・ビューティと思います。マギーの着ていたチャイナ・ドレスは素晴らしかったし、トニーも色っぽいですね」
結果的には15週上映となり、映画ファンに今も根強い人気を誇る作品となっている。この時は銀座テアトルシネマでも上映され、ル・シネマにとっては、今につながる単館拡大興行のはしりとなった。
アジアの映画人は他に韓国の鬼才キム・ギドク監督(『春夏秋冬そして春』〈03〉、『弓』〈05〉、『嘆きのピエタ』〈12〉)、中国のジャ・ジャンクー監督(『罪の手ざわり』〈13〉)等も登場し、特に男性ファンに強く支持されているという。
ただ、これまで邦画は一度もかけたことがない。その理由を尋ねてみると、「映画に分けへだてはないので、特にこだわってそうしてきたわけではないのですが……」と淡々とした答えが返ってきた。
「特に最近のように洋画と邦画の興行的な立場が逆転してしまうと、小さな国の作品は公開されずに終わってしまうケースも出てくるので、なるべく、その受け皿になりたいという思いがありまして、今に至っています」
その結果、邦画ではなく、洋画中心の興行を行ってきたようだ。そこには知らない国のことも映画で知ってほしいという願いも隠されている。
「ネットの環境が整って世界とつながってしまうと、情報収集が以前より簡単になり、その分、若い人が外に出て行かなくなった気がします。しかし、見るのと聞くのは大違いです。映画はその窓を開いてくれる最高の語り部で、映画と向き合うことで、その国の宗教や家族、習慣なども知ることができます。それをきっかけにして、もっと興味を深めて、その先に行っていただけると本当にうれしいです。そのためにこの仕事をやっているのかもしれません」

これまでのル・シネマの25年間を振り返ると、女性層を意識しながら旅やグルメが登場する映画も上映されてきた(今年の秋はポルトガルの旅行者を主人公にした『リスボンに誘われて』〈13〉が好調だった)。
また、複合施設の中のミニシアターという立場も考慮して、クラシック音楽やバレエ、絵画といった要素が入った作品もかけられている(初めてかけたドキュメンタリーはバレエが題材の『エトワール』〈00〉。最近では人気ピアニスト、マルタ・アルゲリッチのドキュメンタリー『アルゲリッチ 私こそ、音楽!』〈12〉も上映)。
さらに中高年から若いカップルまで幅広い人気を誇るウディ・アレン監督の『ミッドナイト・イン・パリ』(11)や『ブルージャスミン』(13)もヒットしている。
近年は前述のジャ・ジャンクー作品のように、シネアスト系の観客に支持されてきた先鋭的な作風の監督も上映して、以前より幅広いセレクションを行うことで、新しい観客層も獲得してきた。
「気づいたら25年間が過ぎていたんです。出会う作品がどれも新しいし、その作品を育てる新しい仲間たちとも出会ってきました。それがこの仕事の喜びのひとつでもあります」
この〝作品を育てる〟という発想は効率第一主義で上映作品を決める〝シネコン〟にはないものかもしれない(ヒットしない作品はすぐに切り捨てられる)。ただ、ミニシアターも以前より上映サイクルが早くなっている。
「ロングラン作品が出て、年間で数本しか上映していない年もありましたが、今はかつての倍以上の本数を送りだしているので、1本ずつにかける時間が短くなってしまいます。だから、作品がひとり歩きするような状況になるのはむずかしくなりました。ただ、最近でいえばシネスイッチ銀座の『チョコレートドーナツ』(12)みたいに小さな映画が口コミを通じて意外な広がりを見せているし『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』(13)以降、うちもいい流れになっています」
かつて『パガニーニ』でオープンを迎えた劇場は、25年後、同じ音楽家を描いたもうひとつの『パガニーニ』の上映も経て、新たな勢いをつかんでいるようだ。
観客層はシニアが中心で、以前からのファンがそのままついているという。そこで若い層を呼び込むため、学生は平日1100円というサービスも導入している。
「今はみんなが行くから自分も行くという見方が主流になっていますね。悪い意味でのグローバリゼーションでしょうか。でも、本当はその作品を自分がどう感じるのか、その発見を大事にしてほしいです。新しいものと出会った時に感じるときめきや喜び。それこそがカルチャーや芸術にふれることの醍醐味だからです。ネット社会はシロとクロがはっきりしていて、中間がないと思いますが、実は中間にこそ、本当のおもしろさがあるはずです」
あいまいさの中にこそ、真実が宿る。確かにそれが芸術の神髄かもしれない。
中村プロデューサーは「映画との出会いは人との出会いであり、それが世界とつながるきっかけになり、自分の周辺をも豊かにしてくれる」と考えている。映画に対する広い視野とやわらかな好奇心こそが、ル・シネマの25年間を支えてきた大きな原動力だったのだろう。
〝大人がくつろげる渋谷のスペース〟として、Bunkamuraは今も穏やかな活力を失っていない。

◉Bunkamuraル・シネマは渋谷区道玄坂2-24-1のBunkamura6階に受付カウンターがある
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。