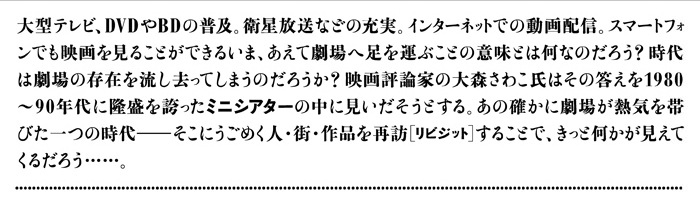昨年の秋、映画会社から1本の電話がかかってきた。それは東映の宣伝部からで、会社名を告げられた時、邦画の新作プロモーションかな、と思った。ところが、話を聞いていると、予期しなかった監督の名前が出てきた。
「今度、テオ・アンゲロプロスの新作をうちで公開することになりました」
えー、と思わず声を上げる。
アンゲロプロスはギリシャ出身の巨匠監督で、80年代・90年代のミニシアターでは芸術志向の観客たちに熱く支持されていた。4時間の超大作『旅芸人の記録』(75)が日本では神保町の岩波ホールで公開されて10万人を動員する大ヒットを記録。それが80年代以降のミニシアター誕生に影響を与えたともいわれている。
その後は『アレキサンダー大王』(80)、『シテール島への船出』(83)、『霧の中の風景』(88)、『こうのとり、たちずさんで』(91)、『ユリシーズの瞳』(95)、『永遠と一日』(98)といった作品が『旅芸人の記録』と同じフランス映画社配給で、六本木のシネ・ヴィヴァン・六本木や銀座のシャンテシネといったミニシアターで上映されて話題を呼んでいた。
ところが、2004年の『エレニの旅』の後に撮った『エレニの帰郷』(09)は日本公開が実現しないまま、監督は12年1月24日に新作を撮影中に事故死。この悲しいニュースは映画ファンに衝撃を残した。
この訃報から2年が過ぎ、今年の1月に遺作が遂に日本でも上映されることになったという。それにしても、なぜ、『仮面ライダー』や「『相棒』シリーズ」の東映で? その素朴な疑問に宣伝部の担当者は答えた。
「実はうちの岡田(裕介)社長がアンゲロプロス映画の大ファンで、ある時は彼の本を作りたいとまで思っていたそうです」
黒澤明やデイヴィッド・リーンと並んで、アンゲロプロスを20世紀最高の映画監督と考えている社長は、彼の遺作が数年間、オクラであることに心を痛め、今回、採算を度外視して公開を決意したという。その話を聞き、2度驚いた。今もそんな気骨のある挑戦をする人がいたとは……。

また、今回の上映に関してフランス映画社の柴田駿社長の助力もあったという。その名前を聞いて、アンゲロプロス映画の育ての親ともいうべきフランス映画社の作品群へも思いをはせる。
1976年に「BOWシリーズ」というフランス映画社のレーベルが作られ、日本で未公開だった世界の名作が次々に公開された。最初に上映されたのはジャン・コクトー原作、ジャン・ピエール・メルヴィル監督の『恐るべき子供たち』(50)とジャン・ヴィゴの『新学期・操行ゼロ』(33)。どちらも海外では傑作として評価されていたが、日本へは輸入されていなかった。千石の三百人劇場で公開されたが、古い映画であるにもかかわらず、新鮮なおもしろさがあった。
80年代にフランス映画社の事務所は銀座にあり、新作の試写会は銀座四丁目交差点の近く、東和の第2試写室で行われていた。小さな部屋にふわふわした長椅子が置かれ、ひとりの体が動くとその列に座った数人の体も連動して動く。だから見る時はきちんと背筋を伸ばして座っていたせいか、何か厳粛な雰囲気があった
この時代、フランス映画社は前述のアンゲロプロスの作品群やジャン=リュック・ゴダールの『パッション』(82)『カルメンという名の女』(83)、アンドレイ・タルコフスキーの『ノスタルジア』(83)、ヴィクトル・エリセの『ミツバチのささやき』(73)などをオープンしたばかりのシネ・ヴィヴァン・六本木にかけて評判を呼んだ。
そして、80年代前半から中期の六本木や渋谷でのミニシアターの勢いを見て、映画の老舗の街だった銀座も重い腰を上げる。87年にシャンテシネやシネスウィッチがオープンした。
こうした劇場ができるとフランス映画社はシネ・ヴィヴァン・六本木からシャンテシネへとメインの上映館を移し、特にヴィム・ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』(87)がミニシアター映画の歴史に残る記録的なロングランとなった。
他にも同社はジム・ジャームッシュ(『ストレンジャー・ザン・パラダイス』〈84〉)、アキ・カウリスマキ(『コントラクト・キラー』〈90〉)、ジェーン・カンピオン(『ピアノ・レッスン』〈93〉)等、世界中の新しい才能を日本で紹介。「BOWシリーズ」はミニシアター界の最も知的なブランドのひとつとなり、メジャーな商業映画とは違う映画の楽しみ方を伝える役割を果たした。長年、日本では未公開で、柴田社長やパートナーで副社長だった故・川喜多和子さんの熱意で上映が実現した作品もあった。
しかし、近年は配給作品もめっきり減り、看板監督のひとりだったアンゲロプロスの『エレニの帰郷』も未公開だったが、今回、銀座に本社のある東映での公開が決まった。社長の監督への思いによって数年間オクラだった映画の公開が実現したといういきさつは、かつて、ミニシアターに夢を懸けていた映画人を思わせるものがある。
しかも、この上映を記念してアンゲロプロスの過去の10作品を集め、「アンゲロプロス監督回顧上映(レトロスペクティヴ)」も11日間に渡ってモーニングショーの形式で行うという(新宿バルト9 、梅田ブルク7で開催)。『エレニの帰郷』の公開だけでも快挙だが、過去作品まで上映するとはかなり本格的な入れ込みようだ。東映からの電話を切った後、その公開のいきさつも含め、この遺作に興味がわいてきた。
アンゲロプロス監督はこれまで祖国ギリシャの歴史的な背景を盛り込みながら、圧倒的な映像美で人生の旅人たちの姿を見せてきた。黒澤明や大島渚といった日本の巨匠たちもその演出力を高く評価し、個人的に交流もあったという。『シテール島への船出』が86年にシネ・ヴィヴァン・六本木で公開された時、大島渚はこんな文章を新聞に寄せている。
「やはりもう一度と思って、シネ・ヴィヴァンへ足をはこんだ。『シテール島への船出』を見るためである。平日の第一回目だというのに客席は満席に近かった。パリのサンタンドレ・デザールで見た時は半分も埋まっていなかった。テオ・アンゲロプロスへの信頼は日本で定着したらしい」(『毎日新聞』86年3月4日夕刊)
日本ではアート系映画ファンの間で圧倒的な支持を受け、公開される新作のほとんどが映画雑誌のベストテンに入っていた。作家の池澤夏樹が字幕を担当し、パンフレットや雑誌にニュー・アカデミズム系の蓮實重彦が文章を書き、教養人好みの難解な監督というイメージが確立されていった。ちなみに紀伊國屋書店によってリリースされたブルーレイには作品ごとに小冊子がつけられ、詩人の白石かず子、作家の辻邦夫、評論家の加藤周一などが公開時の新聞やパンフレットに寄稿した文章が転載されている。
私自身はケレンやいかがわしさも入っている作品が好きなので、これまでアンゲロプロス映画に個人的な思い入れはなかった(その昔、『アレキサンダー大王』を見た時は身の置き所がなかった……)。

今回の新作『エレニの帰郷』は白紙の状態で見ようと決意して試写に出かける。30年間ほとんど変わっていない銀座の東映ビルに到着すると、試写室の前には『仮面ライダー』最新作のポスターがあり、その隣にアンゲロプロスのポスターが見える(不思議な感覚!)。
しかし、いざ映画が始まってみると、その世界に引き込まれ、本物の重厚な映像を見たという充実感が残った。試写に同行した編集者たち(彼らもテオ映画のファンではなかった)も同じ意見で、見終わった後、作品をめぐって話が盛り上がった。
この映画の前日に最新の特撮技術を駆使したあるハリウッド大作を見たばかりだったので、両者の映像の感触の違いについても考えさせられた。『エレニの旅』のブルーレイの特典映像として収録されたインタビューで、アンゲロプロスはこんなことを語っている。
「私はデジタル処理された人間やセットではなく、生身の人間とだけ愛を交わしたいと思っています。それが昨今のCGを駆使したデジタル映画と私の映画の違いなのです」
もし、CGを使った特撮映画がおいしいながらも、添加物も加えた飲み物だとすれば、『エレニの帰郷』には、質のいい葡萄をたっぷり使い、丁寧に熟成させたワインのような味わいがあった。
20世紀を生きぬいた監督の母親へのオマージュ的な作品で、20世紀を描く「トリロジア(三部作)」の2作目にあたる。1作目『エレニの旅』は1919年から49年までのギリシャが舞台で、養女として育ったヒロイン、エレニの愛の旅が描かれている。2作目は53年から90年代の終わりまでのエレニの人生が映画監督である息子、A(ウィレム・デフォー)の視点でとらえられ、前作とはまた独立した作品として見ることができる。
今回のエレニ役を演じるのは『ふたりのベロニカ』(91)、『トリコロール/赤の愛』(94)で知られるイレーヌ・ジャコブで、彼女が愛し続けるスピロサには『汚れた血』(86)や『美しき諍い女』(91)のミシェル・ピコリ、彼女を愛し続けるヤコブには『ベルリン・天使の詩』や『永遠と一日』のブルーノ・ガンツ。アンゲロプロス映画としては、いつになく豪華なキャストで、自身の居場所を求める人々の旅が研ぎ澄まされた映像で綴られている。
原題は“The Dust of Time”で、50年代から90年代までのさまざまな歴史の断片が散りばめられる。スターリンの死、ウォーターゲート事件、ベトナム戦争、ベルリンの壁の崩壊……。監督であるAの部屋にはザ・ドアーズのジム・モリソン、レゲエ界のスター、ボブ・マーリー、革命家のチェ・ゲバラなどのポートレートが貼られている(若くして他界したポップ・アイコンばかり)。Aは妻との結婚生活が破綻し、幼い娘エレニの心の問題にも悩む。
Aはアンゲロプロスの分身でもあり、ローマ、北カザフスタン、シベリア、ニューヨーク、トロント、ベルリンなどを舞台にして、彼の両親の物語と時代の変化が幻想的なイメージを重ねることで描かれる。生と死、愛と別離、孤独と和解、絶望と希望。人々が抱える時間の向こう側にさまざまな意味を読み取ることができるが、それは20世紀を生きた人々の壮大な心の旅の記録でもある。ギリシャの近代史を知らない人間には分かりにくい部分も多々あるが、「分かる」か「分からない」を超え、見る人の心と体の奥に浸透していくような魔術的な映像力があった。
後半、ヒロインと2人の男、ヤコブとスピロスが老いた姿を見せながら、3人で船に乗り込む場面がある。思えば3人を演じる俳優たちは80年代・90年代にミニシアターの数々の人気作品で主役を演じていた。ブルーノ・ガンツは今年73歳、ミシェル・ピッコリは今年89歳、イレーヌ・ジャコブだけは今年48歳とまだ若く、あえて老け演技を見せているが、かつての初々しかった面影は消えている。彼らの姿に時間の経過がはっきり刻まれ、そこに思わずミニシアター文化の変化も重ねてしまった。
監督自身もすでにこの世を去ってしまったわけだが、新作(「トリロジア」の最終章)を撮影中に亡くなったことが、妙に感慨深いと思う。生前、旅をテーマに映画を作り続けた彼はこんな言葉を残しているからだ。
「映画作りも(私には)旅といえます。ロケ地を転々としているからではありません。撮影中に起きることこそが旅だからです。そのような旅が自分自身と対峙していることを忘れてはいけません。どんなことをしていても、旅は最終的に自らの内面へと向かう旅になるからです。生身の肉体ではなく、自らの内なる存在が旅をするという意味です。そう考えることで旅はより豊かになります」(『エレニの旅』ブルーレイ特典映像のインタビューより)
監督は撮影中に遂に生身の肉体を捨て、魂だけが存在する世界に旅立ったのかもしれない。
試写から数日後、アンゲロプロス映画の普及に力を尽くしてきたフランス映画社が経済的な苦境に立ち、数々のフィルムが裁判所に差し押さえられたというニュースが伝わり、なんとも悲しい気持ちになった。そんな状況の中で遺作の公開が決まっていたのは幸運だったと思う。
監督の生前の置き手紙ともいえる『エレニの帰郷』。日本の観客たちは巨匠の最後の旅をどんな気持ちで受け止めながら劇場を後にするのだろう……。

◉東映は古くから銀座3丁目にオフィスを構え、『エレニの帰郷』の試写会はこのビルでも行われていた。同じビルには、2スクリーンを持つ映画館・丸の内TOEIが入る
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。