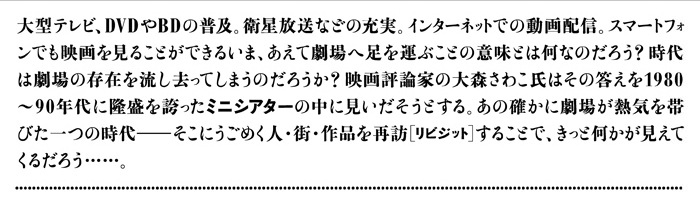テオ・アンゲロプロス監督の映画が新宿の劇場で上映されることになった。
近年までは銀座のシャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)で上映されることが多かったが、新作にして遺作の『エレニの帰郷』(09)は新宿三丁目にある東映系のシネマ・コンプレックス、新宿バルト9で上映される。
初日にどんな観客が来るのか、とても興味があった。しかし、近年はそうしたアート系映画の熱が日本の洋画界から消えつつある。
その初日の様子を見るため、封切日の1月25日の朝、バルト9に向かう。近年、新宿には新しいシネコンが増え、東京で最も集客率の高い映画の街になりつつある。バルト9は大衆的だった新宿東映があった場所に立っている。今ではファッションビルと映画館とが一体化したおしゃれなビルに生まれ変わった。白を基調としたすっきりしたデザインで、古ぼけた映画館の面影などみじんもない。
伊勢丹の近くにある松竹系の映画館、新宿ピカデリーも数年前に21世紀の建物として生まれ変わり、バルト9同様、さまざまなプログラムを上映するシネコンとして人気を集める。新しいビル(白っぽいビルが多い)が増えたせいか、新宿三丁目周辺のイメージが昔よりクリーンになった。いかがわしい歓楽街の猥雑さが消え、空気が浄化されているような印象さえある。
街の変化を体で受け止めながら、バルト9の入口に入ると映画の発券機があり、エレベーターへと昇る人々の列ができている。映画館の入口は9階。ドアがあくと、広いロビーにチケット売り場があり、さまざまなポスターが貼られている。サンドラ・ブロック主演のハリウッド大作『ゼロ・グラビティ』(13)や邦画は『永遠の0』(13)、さらに『仮面ライダー×仮面ライダー 凱武&ウィザード天下分け目の戦国MOVIE大合戦』(13)も上映中。長い列ができていたのはアニメファンに人気の『劇場版THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』(13)。渋谷のミニシアターで公開中のアメリカのインディペンデント系作品、『ビフォア・ミッドナイト』(13、リチャード・リンクレイター監督)も上映されている。
作品に劇場固有の特色があるわけではなく、大作から小品まで何でもあり。そこがアート系映画を3館の劇場で上映していたシャンテシネとの大きな違いだ。そのフロアの壁を見ても、シネコンの上映作品の幅の広さがうかがえる。
ロビーの壁にはすでに上映中の「アンゲロプロス」レトロスぺクティブの作品群が紹介されていて、代表作10本の場面写真がある。テレビ画面では『エレニの帰郷』の予告編も流れている。そのそばを見ると、ピンクのふわふわの着ぐるみを身にまとった日本のアイドル系タレントの主演作の大きな広告がある。
個性より多様性。それがシネコンの在り方だ。そして、興行成績が悪いものは容赦なく小さな館へと移され、1日の上映回数も減っていく(入りがひどいと、上映も終了する)。
ミニシアターでも、ヒットしない映画は長くは上映されないが、ここまで徹底した効率主義ではなく、80年代にミニシアターがスタートした頃は、どんなにヒットしなくても4週間は上映を続けるという映画館が多かった。シネコンの場合、どうしても大型予算を投じた大作や話題作だけが生き残りやすく、大衆性のないアート系映画に数字的な勝ち目は薄い。

◉再開発が進む新宿はかつての猥雑さが薄れ、ファッション・ビルが目立つ街になった
『エレニの帰郷』が上映されるのは5番スクリーン。劇場に到着するとすでに関係者たちも顔を見せていた。そして、東映の宣伝部や劇場関係者にまじって、見覚えのあるコート姿の男性が立っている。アンゲロプロスの作品群を配給してきたフランス映画社の柴田駿社長だ。 「お久しぶりです」
思わず、そう声をかける。
今回の映画は、東映の配給だが、配給協力としてフランス映画社の名前もある。東映の岡田裕介社長はもともとアンゲロプロス監督の大ファンで、一度でいいから会いたいと考えていたという。そこで柴田社長に相談したが、タイミングがうまく合わず、監督は不慮の事故で突然の他界。そんな縁もあって、今回、柴田社長の協力を得ながら、東映での配給が実現した。
その日の初回の上映は午前10時20分から。5番スクリーンの前には列ができている。スクリーン前の廊下はかなり狭いが、その真ん中にはアンゲロプロスのための献花台が用意されている。台にはパネルサイズにひきのばされた監督の大きな写真が飾られ、その前には白いカーネーションが20本ほど置かれている。初日の前日、1月24日は監督の命日。今年は日本式にいえば三回忌を迎えた。そこで東映の岡田社長は劇場に献花台を作ることを提案し、それが初日の劇場で実現した。
遂に開場時間を迎えると観客たちが入場する。まずは献花台の前に進んで手を合わせる人がいる。中には自ら白いユリの花束を携えて献花台の前に立った人もいた。次々に入場する観客たちを写真の中の監督は見つめている。土曜日の朝の10時台の上映ということもあり、観客の年齢層は高めだ。200席を超えるスクリーンだが、入りは160席を超えている。
「悪くないですね」
そうつぶやく関係者の声が聞こえてくる。開映の時間が来ると、スタッフたちは劇場に入る。私もその後をついていき、壁際でスクリーンを見つめた。
レオナルド・ディカプリオ主演、マーティン・スコセッシ監督の『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』(13)やロン・ハワード監督の『ラッシュ/プライドと友情』(13)といった話題作の予告編に続いて、いよいよ本編が始まる。
東映配給、フランス映画社配給協力のクレジットが出る。献花台の前にあったものと同じアンゲロプロスの写真も一瞬だけ映し出された後、本編がスタートする。
以前、東映の試写室で見ていたが、それよりも大きなスクリーンなので、映像がさらなるインパクトを伴って迫って来る。最初の数分を見て、スタッフたちは外に出たので、私も後に続いた。近くのカフェで、お茶を飲むことになり、その輪に加わった。
日本で数年間、オクラだった監督の遺作を世に送り出すことができた。その直後のお茶会ゆえ、関係者たちの顔には安堵の表情が浮かぶ。
「フランス映画社の作品をいつも初日に見に来るという方が見えていましたね」
スタッフのひとりがそう言うと、柴田社長は答える。
「初日にはね、公開する映画のポストカードを配っていたんですよ」
どうやらそのカードがほしくて、初日の初回をめざして劇場に訪れた観客もいたようだ。初日の“追っかけ”を続けているファンはかなり年季が入っているようで、すでに社長とは顔見知りのようだ。特定の映画会社の“追っかけ”を続ける。これは大手の会社では考えられない現象かもしれない。会社の個性を打ち出し、誠意を持って、世界の名作や傑作を送り出す。そんな姿勢を40年間、貫いてきたフランス映画社だからこそ、こういうファンもついたのだろう。そんな話を聞きながら、私は劇場でもらった番組表に目を向ける。
「今回の映画、真夜中の24時からの上映もあるんですね」
すると柴田社長はおどけた口調で答えた。
「アンゲロプロス映画の歴史の中で、初めての真夜中の上映ですか……。昔、『ミッドナイト・アート・シアター』にかけたこともありましたが……」
ミッドナイト・アート・シアター、そのタイトルに私はすぐさま反応する。80年代、フジテレビの深夜でアート系映画だけを放映するテレビの洋画番組があり、そこではフランス映画社の数々の作品群が上映されていた。今のように多チャンネル時代ではなく、地上波では地味なアート系映画はなかなか放映されなかった。しかし、この深夜枠の番組では、アンゲロプロスやタヴィアーニ兄弟(『サン★ロレンツォの夜』〈82〉)といったフランス映画社の作品を始め、ヘラルドエースやシネセゾン等、ミニシアターに映画を供給していた会社のさまざまな作品を見ることができた。記憶の彼方にあった番組のタイトルを聞いて、一瞬、80年代へとタイムスリップしてしまった。
「なつかしいですね」と私が言うと、柴田社長は答えた。「『旅芸人の記録』(75)は上映時間が長いので、2回に分けての放映でした。でも、今回は、一本まるごと、真夜中に上映されます。アンゲロプロス初ですな」
かつてシャンテではフィルムで上映されていたので、映写技師がいないと映画がまわせない。しかし、デジタル上映には技師が必要ないので、どんな時間でも上映できる。
バルト9では25時や26時に始まる映画もけっこうあるが、聞くところによれば、テレビやラジオなど、マスコミ業界の人間やクリエイターたちが仕事を終えた後、この劇場に来ることもあるという。
また、シネコンでの上映について柴田社長の口からはこんなコメントも聞かれた。
「とにかく、初日まで映写の状態が心配でしたが、今日の初回を見たらいい状態で上映されていたので、ほっとしましたよ」
「シャンテと比べていかがですか?」と私が言うと――。
「スクリーンはこちらの方が大きいです」
ポツリ、ポツリとしか言葉を発しない社長だったが、その少ない言葉の中にアンゲロプロス監督への長年の思いが見え隠れする。

◉『エレニの帰郷』封切日の前日(1月24日)は監督の三回忌だった。劇場に設けられた献花台には白いカーネーションが用意されていたが、自ら白いユリの花束を持ってきた観客もいた
やがて、秋に来日したアンゲロプロスの一家について話が及ぶ。アンゲロプロス夫人のフィービー・エコノモプラスさんが鎌倉にある川喜多映画記念館を訪ねた時、東宝の歴史を振り返るポスター展が行われていたという。そこにはかつて俳優だった東映の岡田社長の若き日の出演作(『赤ずきんちゃん、気をつけて』等)のポスターがあり、それを見た夫人はそのポスターの前で写真を撮り、岡田社長にそれを見せたら社長は大慌てだったとか(当時の岡田社長はとてもハンサムで、甘い容姿だった)。一方、監督の幼い孫娘は東映のアニメ『ワンピース』の大ファンで、母親(監督の娘)のアンナ・アンゲロプロスさんにグッズをプレゼントしたら大喜びだったという。
また、夫人は「日本人ほど、テオの作品に理解を示してくれた観客はいない」と来日時に語っていたという。けっして分かりやすいとは思えない彼の作品群に熱心な観客がついたのは、フランス映画社の尽力が大きく、その誠意と熱意の賜物ともいえるだろう。
家族の来日時の話が盛り上がる中、隣にいたはずの柴田社長がいない。気づくと、店の壁に貼られたモノクロの写真に近い席に座りこんでいる。彼が一心に見つめているのはフランス写真家ロベール・ドアノーのモノクロ写真の数々だ。映し出されたパリの風景にどんな思いが重ねられていたのだろう?
お茶会はお開きとなり、私は宣伝部のスタッフと共に劇場に戻ることになった。初回の上映が終わり、観客たちが次々に場内から出てくる。初回の上映で一番にやってきたという女性を宣伝部の方に紹介していただき、映画に対するコメントをいただくことにした。
「アンゲロプロスの作品は『旅芸人の記録』からずうっと追いかけて見てきました。今回、彼の過去の作品の回顧上映も行われましたが、すごくいい企画だと思います。彼の作品を多くの人に知ってほしいからです」
そんな風に監督への思いを熱く語る方だった。
「今回の映画はいろいろなことを思い出しました。ブルーノ・ガンツが出る場面は『ベルリン・天使の詩』(87)を思い出しました。また、作家のエドワード・サイードの本で書かれたことも頭をよぎりました。年を重ねると、この映画で描かれたように現在の中にふと過去が出てきたり、未来のことがよぎったり、という感覚がよく分かります。年代を追いながら縦軸と横軸が交わるという構成がよかったです」
これまで岩波ホールやシャンテシネなどでアンゲロプロス作品を見てきたという。
「狭い空間の中で焦点がぐっと寄ってくる。そんなところがミニシアターの魅力で、私はミニシアターが好きです。ただ、この映画館もスクリーンが大きくて迫力がありましたね」
その話の中にミニシアターと過ごしてきた豊かな時間の流れが垣間見える気がした。
献花している観客にも声をかけてみた。以前、浜松に住んでいたという男性は、浜松でアンゲロプロス作品を見ていたという。
「『シテール島への船出』(83)など見ていました。時間の描き方が独特で、監督の映画が好きになりました。その後は東京で見るようになりました。今回は最後の作品ということで、本当に残念な気がします」
廊下の方に出て行こうとしたマスクをかけた男性にも声をかけると、彼も、また、監督のファンだった。
「DVDやブルーレイも持っていて、ずうっと見てきました。監督のファンでした」
「今日の映画はどうでしたか?」
「本当によくて……」
それは涙声に変わり、マスクの向こうで言葉が途切れる。後で聞いた話だが、最初の上映が終わった瞬間、劇場関係者がドアを開けると、場内は静まりかえり、泣いている人もけっこういたという。今回の作品は監督の遺書でもある。複雑な気持ちを観客たちに引き起こすのも無理はない。
1回目の上映だけでは多くの観客の声が拾えないので、2回目の上映後も取材を続けることにした。2回目は朝の上映より、ぐっと客層が若返った印象だった。これまでひとり客が多かったので、カップルの観客にも声をかけた。男性の方はアンゲロプロスのファンで、ずうっと見てきたようだ。しかし、女性の方は別のタイプの映画が好きで、お互いの好みの監督を一緒に見ることを楽しんでいるという。
「今回の映画が見られて本当によかったです。ミニシアターの映画はよく見ています。最近、ミニシアターが減っているのが悲しいですね。他に興味があるのはアキ・カウリスマキ、ケン・ローチといった監督です」
バルト9は夜の上映も充実しているので、クリエイティブ系の人も多く訪れるという話を聞いたことがあったが、次に出会ったのは自身も映像を作っているという男性だった。
「自分も映像を作る人間なので、この監督の時間の作り方はおもしろいと思います」
ミニシアターについて尋ねてみると、こんな答えが返ってきた。
「そうですね、作る立場からいうと、上映される場所はそれほど関係ない気がします。やはり、作品ありきです」
その後、壁のそばに立った男性にも声をかけることにした。開口一番、こんな返事が返ってきた。
「フランス映画社の追っかけなんですよ」
あ、と思う。お茶会の席で話題になっていた人に遂に出会えた。
「いつもフランス映画社の映画は初日の初回に見ていた、という方ですか?」
「はいそうです。『木靴の樹』(78)の頃からです」
『木靴の樹』が岩波ホールで上映されたのは70年代の後半だ。ということは、35年以上におよぶ“追っかけ”人生だ。
「川喜多和子さんにお会いしたこともありますよ」
そこに“追っかけ”の長い歴史をふと垣間見た。フランス映画社の副社長だった和子さんが病気で亡くなったのは90年代の前半。すでに20年も前の話だ。長い年月にわたって支持者がいることが配給会社にとってはひとつの励みだったのではないだろうか?
「今回、東映で監督の映画が公開されたこと、どう思いますか?」
「正直、最初は裏切られた気持ちだったんですよ。以前から『第三の翼』というタイトルで映画雑誌に紹介が出ていたので、公開を楽しみにしていたんです。ところが、なかなか上映されず、上映が決まったら、東映配給で、タイトルも『エレニの帰郷』で……」
そばにいた東映のスタッフが、邦題は分かりやすさを考え、『エレニの帰郷』になったと説明する。
「今は公開されて本当に良かったと思っています。一番好きなアンゲロプロス作品は『狩人』(77)です。彼の作品は日本人のリズムに合うんじゃないかな。ゆったりしていて……。まるでお能のリズムですよね。それでいて、謎めいた映像で。あのリズムとミステリアスな部分が、彼の映画のツボですね」
封切り後は何度も映画館に通うそうだ。
「ゴダール監督の『ソシアリズム』(10、フランス映画社配給)は29回も見てしまいました。今回のアンゲロプロス作品も、また通うと思います」
◇
その後、東京は30年ぶりの大雪に見舞われた日もあったが、そんな悪天候の時期も乗り越え、最終的に『エレニの帰郷』はバルト9では7週間の興行となった。後半は朝の1回のみの上映だったが、それでも健闘したと思う(その後、千葉などの劇場でも上映が続いている)。
初日に感じたのは観客たちの熱だった。フランス映画社のように個性ある配給会社が、こうしたファンたちを育て、彼らは20年間、あるいは30年間と好きな監督たちの新作を見るため、ミニシアターを訪れていた。今回はミニシアターではなく、シネコンでの上映だったが、それでも彼らは劇場にやってきた。
かつて銀座のミニシアターが育てたこうしたファンたちをシネコンはさらにつなぎとめていけるのか? 効率第一主義のシネコンにそもそも“育てる”という感覚はあるのだろうか? 巨匠の遺作の初日の風景は映画の未来に関するさまざまな思いさえもかきたてた。

◉新宿・バルト9の外観。巨大な看板広告が目を引いたかつての映画館とは様相が異なる
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。