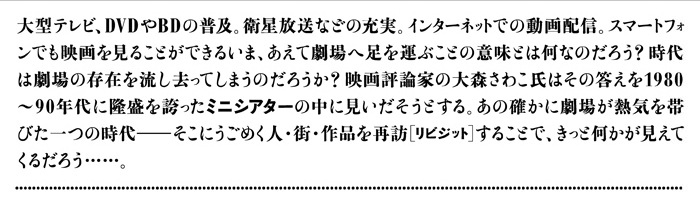渋谷のミニシアター、ユーロスペースの北條誠人支配人と話していて、ある素朴な疑問が頭をよぎった。ミニシアターと呼ばれてきた劇場と他の劇場にどんな違いがあるのだろう? 劇場で映画を上映するという行為は、ミニシアターであれ、シネコンであれ、同じはずだが、そこに違いがあるのだろうか? そのひとつの答えになりそうな言葉が支配人の口から出てきた。
「僕は映画を上映する人間も表現者だと思うんです」
その言葉の中にミニシアターを運営する側の覚悟を見た気がした。支配人は劇場を表現の場所ととらえながら、そこでビジネスが成立する方法を考える。
「劇場のオープン後、一番大事なことは劇場のスケジュールを埋めることです。次に大事なのは劇場を運営するための売り上げをあげること。そして、3番目に劇場の個性について考えることになります。最初の2つをクリアしないと個性は出せません。そこが自主上映のシネクラブとの違いです。あちらは個性を優先する運動体で、こちらはビジネスです。さらに合理化を進めると、シネコンにまでいきつくのでしょうが、ミニシアターはそれとも違い、どの作品を選ぶのかという責任を背負っていると思います。これまでの経験からいうと、上映作品を選ぶ時は、気持ちが幸せでないとだめですね。ダウンしている時に上映作品を焦って決めると、後で作品に対して気持ちが乗らないこともあります。そういうことも含め、上映する側も表現者だと思います」
この発言を聞いてミニシアターの背負ってきた大事な役割についても考えた。
80年代以降のミニシアターは〝スターより監督で映画を見る〟という楽しみ方を観客に伝えてきた。そして、支持する監督が新作を撮るたびに自分の劇場で上映し、その監督のホームグラウンドとなってきた。たとえば、神保町の岩波ホールはエルマンノ・オルミ(『木靴の樹』〈78〉)、(いまはなき)恵比寿ガーデンシネマはウディ・アレン(『ブロードウェイと銃弾』〈94〉)、渋谷のシネマライズはハーモニー・コリン(『ガンモ』〈97〉)といった監督たちの新作を好んでかけてきた。こうした劇場がごひいき監督を大切に育てることで、その監督のファンも日本で育っていった。
ミニシアターはふだんの商業ベースにのりにくい監督たちの作品を日本で広めるという大事なミッションを背負っていたのだ。
ユーロスペースにとって、特に縁の深かった監督を3人あげてもらうと、フランスのレオス・カラックス、フィンランドのアキ・カウリスマキ、イランのアッバス・キアロスタミといった名前が出てきた。
「カラックスの場合は、ベルリン映画祭で堀越社長がその才能に目をつけ、作品を配給することになりました。監督2作目の『汚れた血』(86)をまずはシネマライズで上映して、その後、ユーロでデビュー作の『ボーイ・ミーツ・ガール』(83)を上映しようと決めていました」
そんな言葉で思い出したのが、80年代後半にユーロの事務所を訪ねた時のことだ。堀越社長が「今度、すごい映画を買ったんだよ」といってビデオで抜き焼きを見せてくれた。それが『汚れた血』の映像だった。舞台は近未来のパリで、エイズを思わせる難病が蔓延する中、孤独な金庫破りの少年がセキュリティの厳しいビルから開発中の治癒薬を盗み出そうとする物語で、彼とふたりの女性との愛がからむ。
映像の構成が凝っていて、黒と白の画面の中で、赤と青だけを強調するような色彩にしたり、ガラスに映る影のような残像を取り入れたりしている。少年役を演じるドニ・ラヴァンという新人俳優も奇妙な顔立ちで、ゴツゴツした野獣のような顔立ちながら、その中に繊細さを宿している。セリフにはフランス風の詩的な文学性があり、愛する女性に向けて「もし、君とすれ違ったら、世界とすれ違うことになる」という観念的な(?)セリフも登場する。ヒロインを演じていたのが黒髪のジュリエット・ビノシュと金髪のジュリー・デルピー。その後、国際的な活躍をするようになったふたりの個性的な女優の原石の魅力を見ることができる作品でもあった。
ユーロは88年の2月にこの作品をシネマライズ渋谷にかけたが、当時、作られた日本の予告編のコピーを拾うと──。
「ヌーヴェル・ヌ―ヴェル・バーグ元年。ゴダールの再来。フランス映画界がついに産んだ〝恐るべき子供〟、レオス・カラックス監督作品。愛は感染する。少年は金庫を、少女は掟を破った」
ヌーヴェル・バーグとは、50年代後半にフランソワ・トリュフォーやジャン・リュック・ゴダール監督がフランス映画界に巻き起こした新しい映画運動だったが、それから20年が過ぎて、さらに新しい(ヌーヴェルな?)才人が登場したということだろう。
北條支配人によれば、シネマライズでの興行は4週間で終わってしまったが、その後、ユーロでムーブオーバーの上映が行われた時はまずまずの成績で、夏に監督のデビュー作『ボーイ・ミーツ・ガール』が上映された時は11週間で1万5000人を動員。じわじわと監督の知名度が浸透していったようだ。
「90年代の『ポンヌフの恋人』(91)の製作が資金難に陥った時は、日本で1億円の出資を募り、完成にこぎつけましたが、あの時は宣伝に半年の期間をかけ、一般の観客にも人気が降りてきたという印象がありましたね」
92年に日本で上映された『ポンヌフの恋人』はシネマライズで27週間という画期的な興行となる。その後も、『ポーラX』(99)、『ホーリー・モーターズ』(12)と寡作ながらも、自分の個性を打ち出した作品を撮り続けるカラックスだが、こうした作品もユーロが配給を手がけ、フランス映画界の超異端児ともいえるこの監督を支え続けている。
アジアの監督でいえば90年代のイランのアッバス・キアロスタミ監督との出会いもユーロには大きな意味があった。
「当時、イランの映画なんて誰も見たことがなかったので、新鮮な印象があったのでしょうね。うちの劇場のスタッフのひとりが、カンヌ映画祭で『友だちのうちはどこ?』(87)が売りに出ているのを見て、公開が実現しました。
そのスタッフとは、後に金沢でミニシアター(シネモンド)を作ることになる土肥悦子さんで、彼女は90年代に東京や金沢などで開催されたイラン映画祭の実行委員会事務局長もつとめている。
子供の純真な心を見つめた『友だちのうちはどこ?』は最初、銀座のテアトルシネマ西友にかけて好評を博した。93年12月にはこの作品の3年後の後日談にあたる『そして人生はつづく』(92)との2作品を連続上映して、9週間で1万2000人を動員。こうした作品では子供たちが主人公になっているせいか、どこかほのぼのとした雰囲気があったが、そのシンプルな持ち味を生かしつつも、監督がさらに成熟した作風を見せたのが『桜桃の味』(97)だ。こちらはカンヌ映画祭で、最高賞のパルムドールを獲得している(日本の今村昌平監督の『うなぎ』と同時受賞)。
自殺志願の中年男が主人公で、車を走らせながら、通りがかりの人々に、自分が自殺した後、遺体に土をかけてほしい、と持ちかける。死を近くに感じることで、むしろ、生へと近づいていく。そんなことを考えさせる作品だ。『友だちのうちはどこ?』とは異なる大人の視点も話題になって、98年1月から20週間の興行となり、3万9000人を動員。これまでのユーロの歴代興行成績では3位となっている。
その後もヨーロッパで撮った『トスカーナの贋作』(10、主演=ジュリエット・ビノシュ)や日本の加瀬亮が出演した『ライク・サムワン・イン・ラブ』(12)といったこの監督の作品も同劇場で公開している。
フィンランドの人気監督、アキ・カウリスマキの場合は、当初は別の配給会社が買い付けていたが、90年代以降はユーロが支持する監督のひとりとなった。シンプルながらも色彩に凝った映像、古いブルース音楽へのこだわり。そんな画面作りの向こうに社会の底辺で生きる人々のユーモアと悲哀感が見える。
「カウリスマキ監督の映画を最初に入れたのはKUZUI エンタープライズで、『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』(89)が上映されました。その後はフランス映画社やシネセゾンなどが買っていたんですが、途中で監督の転機となる事件が起きました。その頃から新作を誰も買わなくなったんです」
その事件とは監督の大半の作品に主演してきた個性派男優、マッティ・ペロンパーの死だった。95年に44歳の若さで他界。毒のあった彼を失うことで、監督の作風も変わり、以前よりさっぱりした(お茶漬けのような?)味になっていく。
「『浮き雲』(96)はペロンパの死後、撮った作品でした。期待しないで見たら、いい内容だったので、うちの劇場で公開したんですが、結果的にはかなりヒットして、ここからカウリスマキの第2の黄金期のスタートなりました」
『浮き雲』はユーロでは97年に上映されて、10週間、1万5000人動員。『街のあかり』(06)は07年に上映されて、9週間、1万6000人動員。また、第2の黄金期の代表作となった『過去のない男』(02)はユーロよりキャパの大きな恵比寿ガーデンシネマで上映して成功した。また、昨年公開された『ル・アーヴルの靴みがき』(11)も好調で、この監督の日本での根強い人気を印象づけた。
「かつてのミニシアターの世界では、お互いが持っている作品をどう見せるのかとみんなで考えていました。カウリスマキ監督でいえば『街のあかり』のように小さな作品はうちの劇場にかけましたが、カンヌで賞をとった『過去のない男』などはもっと客席の多い恵比寿ガーンシネマにかけてうまくいきました。ミニシアター同士が共同体を作ることで独占化されず、うまくいっていたんでしょう。カラックス作品にしても大きめの作品はシネマライズで、地味な『ボーイ・ミーツ・ガール』はうちで上映しました。キアロスタミ作品も集客が望めそうな『友だちのうちはどこ?』は銀座のテアトルシネマで上映しています」
ユーロと他の劇場との協力関係もあって、3人の監督たちは日本のミニシアター・ファンの間で根強い人気を獲得してきた。
「カラックスにはアートの魅力と映画愛があり、キアロスタミには哲学があり、カウリスマキには人生の味わいがありました」
◉アキ・カウリスマキ作品では『白い花びら』(98)もユーロ上映作
ユーロのおかげで日本の映画ファンが知ることができた監督たちは他にもいる。ロシアのヴィターリー・カネフスキー(『動くな、死ね、甦れ!』〈89〉)、スペインのペドロ・アルモドヴァル(『神経衰弱ぎりぎりの女たち』〈87〉)、フランスのフランソワ・オゾン(『焼け石に水』〈00〉)などなど。そんな中でも、興行的に快挙ともいえる結果を生んだのがチャン・イーモウ監督のデビュー作『紅いコーリャン』(87)だった。89年の1月に封切られ、24週間の興行となり、3万9000人の集客があった。ユーロの歴史の中では『ゆきゆきて、神軍』(87)の次にヒットした作品となっている。
当時、中国や台湾から新しい才能が登場し、チェン・カイコー(『黄色い大地』〈84〉)やホウ・シャオシェン(『悲情城市』〈89〉)などの才能も高く評価されていく。『紅いコーリャン』は彼らと並んでその演出力を評価されていたイーモウの骨太の演出が鮮烈な印象を残す傑作で、88年のベルリン映画祭でグランプリに輝いた。小さな村でコーリャンを使った酒作りに励む夫婦の物語で、セリフに頼らず、風景の中にいる人間たちの営みをどこか神話的な語り口で見せる。
「『紅いコーリャン』に関しては問題になった場面(人間の頭皮がはがれる場面)もありましたが、うちの劇場がマイノリティだから上映できた、というのはあると思います。振り返ってみると、その時、一番力を持っているエリアや国などにいい形で入って、その力のあった瞬間に立ちあえました。80年代のニューヨーク・インディーズ映画やカラックスなどのヨーロッパ映画、80年代後半以降のアジア映画、90年代の日本映画。こうした癖のある映画はもうからないので、大手の配給会社が買い付けなかったんです。だから、こちらも権利が安いうちに作品を発掘して広めることができました。それがミニシアターの役目だったし、こちらも楽しかった。ミニシアターの観客もおもしろがっていました。ところが、今はこうした作品に大手が手を出すようになってきたし、一方、癖のある作品も昔より減ってきました」
支配人は作品選びに関して、それを送り出す〝世代〟にもこだわっているようだ。
「日本映画でいえば、僕が若かった頃に塩田明彦や青山真冶、中田秀夫などの作品を上映できたのはラッキーだったと思います。同世代からこそ、こうした作品をピックアップできたし、その魅力を観客にも伝えやすかった。でも、50代となった僕が20代、30代の監督たちと一緒にやろうというのは、どこか無理もあるような気がするので、若い映画人とコミュニケーションをとれる人が出てきてほしいです。また、かつては天井知らずで、買い付けにしてもこのままの勢いで続けられるんじゃないか、という幻想がありましたが、今は天井が下がってきたので、大きくやることよりも、持続可能なシステムにしなくてはいけない。細く長く好きなことを続けられる形を作らなくてはいけない時代ですね」
今のユーロは3分の1が若い観客で、残りの3分の2は中高年やシニアの客層だという。それを将来は5分と5分にしていくのが北條支配人の夢だ。ちなみに今年の春に上映されたレオス・カラックス監督の新作『ホーリー・モーターズ』は往年のシネフィルではなく、若い観客層がやってきたという。「愛は伝染する」とは、『汚れた血』の初公開時のコピーだったが、ユーロが25年間かけて育てた監督への愛は静かに伝染しつつある……。

◉かつてユーロのあった渋谷・桜丘町の東武富士ビル。
右の階段を上ると2Fにユーロがあった。現在、ユーロスペースは「KINOHAUS」というシネマコンプレックスビルに所在。ほかにシネマヴェーラ渋谷、オーディトリウム渋谷、映画美学校などが入っている。東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 3F(劇場)4F(事務所)/☎03-3461-0211】
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。