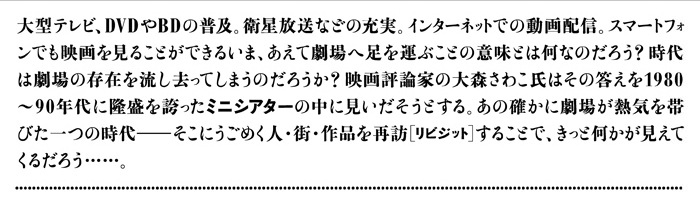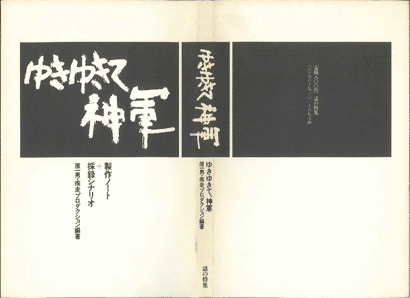一本の映画がかかることで、その劇場の運命が変わることがある。
1987年8月1日、渋谷のミニシアター、ユーロスペースで『ゆきゆきて、神軍』(原一男監督)が封切られ、大反響を呼んだ。
「確かにあの映画はユーロを変えましたね。この映画で渋谷のアングラ劇場から全国区の劇場になりました。今でも『神軍』のユーロといわれますからね」
この劇場の北條誠人支配人は、当時のことをそう振り返る。彼は87年以来、26年以上に渡って支配人をつとめている。
『ゆきゆきて、神軍』は昭和天皇にパチンコ玉を発射した罪で刑務所に入ったこともある60代前半の元・日本軍兵士、奥崎謙三をめぐるドキュメンタリーである。奥崎は激戦をきわめたニューギニアの36連隊に所属して、戦争の悲惨な現実を身を持って体験した。帰国後は昭和天皇の戦争責任を厳しく追及するため、前述の事件も起こした。この事件の前には別の殺人事件で13年以上に渡る刑務所暮らしを送ったこともある。
そんな彼は「田中角栄を殺す」と大きな文字で書かれた車に乗って、過激なコメントを拡声器で放送する──「無知・無理・無責任のシンボルである天皇に私はパチンコ玉を発射しました」。さらにパトロール中の冷静な態度の警察を挑発する──「人間なら腹を立ててみよ!」
言葉だけではなく、時には暴力さえもいとわない奥崎は“歩く爆弾”だ。
彼はニューギニアで不可解な死を遂げた同じ部隊の兵士たちのことが頭を離れない。表向きは戦死となっているが、そうとは信じがたい。その真相を探るため、彼は兵士の遺族を従え、元上官や伍長の家を訪ね歩く。
彼の突然の訪問に困惑しながら、彼らは世間体を取りつくろうが、奥崎の執拗な追及によって40年前の出来事が明かされる。人が人ではいられなかった戦場の(食をめぐる)おそるべき事実に観客としては言葉を失う。封印された戦場の闇へと突き進む奥崎の存在感もすごいが、彼を追い続ける原監督の演出にも圧倒される。
いま、振り返ると、“ミニシアター史上、最も危険な映画”の一本であったこの作品の上映にユーロは挑戦したのだ。
◉『ゆきゆきて、神軍』のチラシのコピー。ポップさと不穏さが共存するデザインは映画の雰囲気を見事に表している
「うちの堀越謙三社長と山崎〔陽一〕さんがベルリン映画祭でこの映画を見て、東京に戻ってから、話が進んだようです。上映の話は他の劇場にも持っていったようですが、最終的にはユーロに落ち着きました」昭和天皇の戦争責任を叫弾するという奥崎の過激な姿勢が右翼の神経を逆なでする可能性があったので、どの劇場も上映をためらったのだろう。
当時、ユーロの事務所を訪問すると、封切り前には危険な発言も飛び出していた。北條支配人は映写も担当していたが、劇場スタッフたちは「もしものために北條に生命保険をかけるから」と冗談を言っていた。映写室に入る前にヘルメットをかぶってもらおう、いや、よろいを着せた方がいいかもしれない……。冗談はさらにエスカレートしていった。
「遊んでましたよね、あの頃」と支配人も当時のことをニガ笑いしながら振り返る。
「仮に襲われても映写室までは来ないと思っていましたけどね。ただ、消火器をまかれたり、スクリーンを切られる可能性もあったので、当時、消火器の中身は抜き、スクリーンが切られても、すぐに対処できるようにしてありました」
結局、恐れていた右翼の騒動は起きなかった。
「渋谷のアングラ館だから、見逃してくれたのかもしれませんね」
当時のユーロは85席。大企業がバックについた座席数の多い劇場だったら、騒動が起きた可能性もある。この作品に関しては劇場の小ささがプラスになった。そのかわり支配人は別の疲労感に襲われた。
「今、振り返ると、疲れた、という印象しかないです。真夏に始まった上映でしたが、四六時中、チケット売るか、パンフレットを売っている状態でした。パンフは『話の特集』に作ってもらったのですが、本当によく売れました。公開後、1週間目に高校の先生が見に来たことはよく覚えています。この映画をかけた地方の劇場もよく入っていたようです」
この年の8月から翌年3月まで26週間の記録的な大ロングランとなり、5万3000人を動員した。30年以上に及ぶユーロの歴史でも興行成績ナンバーワンである。
映画のキャチコピーは「知らぬ存ぜぬは許しません」。戦場で小指を失った奥崎が手を上げているポスターの写真からして、ただならぬ雰囲気があった。私もこの劇場で映画を見たが、場内は異様な熱気に包まれていた。奥崎の存在感はすさまじく、確信犯として“歩く爆弾”になりきる彼は、稀有なパフォーマーでもあり、場内ではたびたび笑い声も上がっていた。
「お客さんは普通の人が多かったです。若い人から中高年もいましたし、女性客もいました。映画が終わると充実感のある顔で出る人が多かったです。ものすごいものを見たという表情でした。ヒットした原因は、やはり、“怖いもの見たさ”でしょうか。それと見終わった後の充実感が口コミで広がっていったのだと思います。リピーターもいましたね」
『朝日新聞』(87年9月5日朝刊)に公開当時のことを伝える記事が残されている。話の特集社から出たこの映画に関する本の紹介記事であるが、その中から作品に関する部分を抜き出すと──。
「〔この作品は〕公開初日から一カ月余を経てなお、立ち見の盛況が続いている。〔中略〕主人公の破天荒なキャラクターと、衝撃的な内容とで、話題が話題を呼んでいるらしい。自己宣伝のため、カメラの前で演技する奥崎と、主体的に記録しようとする原監督とのせめぎあいが興味深い。奥崎は、元上官を殺す場面を撮ってくれ、と原監督にもちかけている。撮るべきか、撮らざるべきか。〔中略〕ニューギニアで〔撮影した〕フィルム没収に至るまでの奥崎の一人芝居は、もはや道化の様相を呈している」
ちなみに映画公開中に奥崎は拘留中で、劇中にも登場する奥崎の妻シズミの一周忌の9月の命日には、彼の発案で劇場の観客と関係者に神軍饅頭が配られたという。
「人類にいい結果が出る暴力なら、これからも大いに使いたい」という言葉を最後に残す奥崎の“究極”の日々の記録であり、撮る側と撮られる側の大きな葛藤を経て生まれたパワフルなドキュメンタリーでもあった(『ボウリング・フォー・コロンバイン』(02)で知られるアメリカのドキュメンタリー監督、マイケル・ムーアもこの映画を高く評価しているようだ)。
映画の公開からすでに25年以上が経過したが、当時の印象を支配人はこう語る。
「題材もすごいですが、監督の力もありました。その人物にしがみついて、映画を撮り続ける作り手が今はいないと思います。また、当時はまだ戦争責任を問う時代だったし、左翼的な勢いが社会にもありました。今はすべてがお金や効率優先ですが、あの頃は正義というものが、まだ、人々の間で信じられていた時代だったと思います。日本の政治の実権を握っているのも戦中派の政治家でしたしね。社会で映画がしめる位置も今とは違っていました。今は物を考えなくなったというか、戦争のことも風化してきて、時代が変わったことは否めないかもしれません」
そんな北條さんの言葉が取材後も頭に残っていた。この映画が封切られたのは42回目の「終戦の日」の直前だった。この年、8月15日の『朝日新聞』の社説はこんな文章で始まる──。
「いまの四十代後半以上の世代では、毎年八月になると、白く乾いたあの日の記憶がよみがえってくる人が少なくあるまい。古ぼけたラジオを囲む隣近所の人たち、ひどい雑音の中から流れる甲高い玉音放送が終わっても大人たちはうなだれたままで、せみしぐれだけがひびく──多くの日本人にとって戦争の終わりは突然であり、昭和二十年八月十五日は『空白の一日』だった」
今年は終戦から68年目。「白く乾いたあの日の記憶」といわれても、リアリティを感じることができない戦後生まれが大半を占める時代となった。
◉北條支配人の手元にあった単行本『ゆきゆきて、神軍』。8月1日初刷りの本書は、11月5日で既に5刷りに達している
◉あえて8月15日にぶつけたキネカ大森のにくい編成
取材後、この映画の現在における意味を考えていたが、そんな時、この作品が劇場で上映されることを知った。しかも、(よりによって)「終戦の日」の上映である。「キネマ旬報映画祭」というイベントが大森にある劇場、キネカ大森で行われ、その中の一本として上映が行われた(封切り時に同誌の年間ベストテンで2位になっていた)。◉あえて8月15日にぶつけたキネカ大森のにくい編成
80年代にはミニシアターのはりしだったキネカ大森は、今では普通の封切り館&名画座になったが、いつも意欲的なプログラムを組んでいて、私もたびたび利用している。
ふだんはギリギリに駆け込んでもすわれるので、こちらも悠長にかまえ、上映15分前に到着したら、チケット売りの青年に言われた。
「お立ち見ですが、よろしいですか?」
え、まさか! でも、どこか1席くらいはあるだろう、と甘く考えてチケットを買ったら、場内は観客でぎっしり埋まっていて、立てるスペースさえも少ない(ちょっと後に来た観客たちは入れず帰されていた)。目前の光景を信じられない思いでみつめつつ、入口で座布団を2枚受け取り、通路に座った。
席の数は79席で、かつてのユーロスペースの座席数に近い。87年の夏が戻ってきたような不思議な感慨にとらわれた。
映し出される映像は、どこまでも“昭和テイスト”で、それぞれの家の電話にかけられた派手な電話カバーや土間のある玄関など生活様式は古いが、そんな風化した風景の向こう側から、あの狂気をまとった言葉の数々が聞こえてくる。2005年に故人となった奥崎だが、現世での肉体は滅びても、過激なパフォーマンスは時を超えてスクリーン上に出現し、今も場内の笑いを誘っている。不特定多数の観客との笑い声の共有はDVDでは体験できないもので、その熱気によって映画の緊張感もさらに高まる。
奥崎がいた昭和の夏は、もう遠い気がしていたが、こうして劇場に来てみると、映画というものが持つ力を、まざまざと思い知らされた。原監督の映画がなければ、ほとんどの人が知るはずもなかったひとりの元日本軍兵士。しかし、一本の映画によって、彼の存在は不滅のものとなり、闇に葬られた戦争責任の問題をつきつける。
前述の取材の中で北條さんは「いまの時代はものを考えなくなった」と言っていた。「どうして考えなくなったんでしょう?」との突っ込みに対して、こんな答えが返ってきた。
「今はフィルムでなくなったから、という言い方もできるかもしれません。撮影も、上映もデジタルですよね。撮影に関していうと、フィルムの場合、持ってくる量に限界があり、何度もやり直しはできない。カメラの前で起きたことが勝負になるし、撮った後、加工もできないので、考える必要がある。でも、デジタルは何度もやり直しができます。また、上映に関しては、30キロ近い映画〔フィルム〕を別の劇場に宅急便で送る時に、5巻目が痛んでいますとか、8巻目は痛んでいます、とか書いてから渡していました。バトンタッチだったんですね。それを『映画のリレー』と呼んでいました。ところが、デジタルはいっせいに上映するので、そういう必要がないんです。今は渡す文化と届ける文化という意識はなくなりつつあります」
この発言を聞いた時、「映画のリレー」の消滅が残念な気がしたが、『ゆきゆきて、神軍』の奥崎の姿を現代の劇場で再見すると別の発見もあった。どんなに時代が変わっても、作品のクオリティまでは風化しない。
キネカ大森での上映にはさまざまな層がいて、学生風の青年から年配の女性まで本当に幅が広かった。上映中、私の斜め前の女性は「岸壁の母」が流れる場面で涙を流していた。また、上映後は受付の青年に「いやあ、映画魂を感じますね」と言い残して帰っていた男性客もいて、その顔は(北條さんが80年代の劇場で見たであろう)充実感に満ちていた。
68回目の「終戦の日」に見た『ゆきゆきて、神軍』。7月の選挙で自民党が圧勝して右寄りの空気が流れ、憲法改正の問題や自衛隊の存在意義が問い直される中、戦場の惨状を体験して、戦争責任を問い続ける奥崎謙三の激烈な言葉の数々は、ただの映画であることを超え、日本の歴史や人間の生死の問題を今も観客につきつけてくる。
映画はDCP(デジタル)上映なので、フィルムのリレーは存在しないが、それでも、「作品のリレー」、ひいては「文化のリレー」はそこにある。
いまだ地上波のテレビでは上映されていない危険物、『ゆきゆきて、神軍』。その上映を決断し、結果としてはロングラン上映を実現したユーロスペース。そんな劇場があったからこそ、この映画は貴重な命を得て、いまも別の劇場で生きながらえている。

◉現在、ユーロスペースは「KINOHAUS」というシネマコンプレックスビルに所在。ほかにシネマヴェーラ渋谷、オーディトリウム渋谷、映画美学校などが入っている。東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 3F(劇場)4F(事務所)/☎03-3461-0211
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。