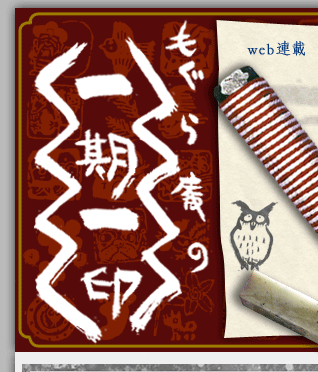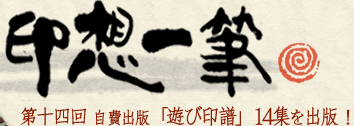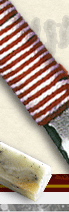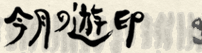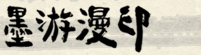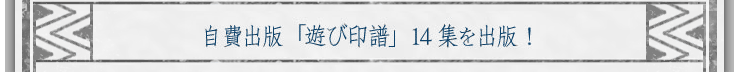※画像はクリックすると拡大画像を開きます。
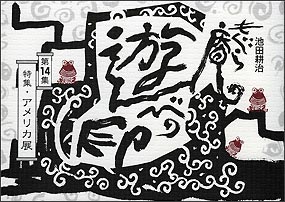 2010年元旦、自費出版「遊びの印譜」第14集を出すことにした。10月末の大阪の書斎展に間に合わすこともできたのだが、本を出すと「あて名書き→サイン→出荷」と用事が多くなるので時期が悪い。また年内だと歳末の恒例行事「賀状書き」と重なってくるので、のんびりしたお正月に出すことにした。 2010年元旦、自費出版「遊びの印譜」第14集を出すことにした。10月末の大阪の書斎展に間に合わすこともできたのだが、本を出すと「あて名書き→サイン→出荷」と用事が多くなるので時期が悪い。また年内だと歳末の恒例行事「賀状書き」と重なってくるので、のんびりしたお正月に出すことにした。
今回のメインはアメリカ展。私がアメリカ・オクラホマ大学に招待され個展をし、大歓迎を受けたこと・見たこと・出会った人たちのことなど書き残したいと思った。招待してくれた芸術学部のフィーラン教授の長い評もあり、私の作品をどう見て戴いたのか興味深い。他に有名人の印・屋号印・こだわりの印・犬猫の印・似顔印の他に、「ボツの印」を載せている。これは注文者と私の考えの違いや様々な理由で、日の目を見ずボツになっていく印たち。そんな印に限って愛着が深いので載せることにした。
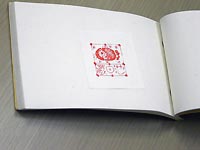 私が自費で本を作り始めたのは篆刻を始めたころ、もう30年以上になるだろう。初めて印に出会い彫り出した当初、あまりにも面白く次々と印ができるのがうれしかった。ほとんどの印は人にあげてしまって、自分の手もとには印影だけが残っていく。ある時、「こうして印影を残すことは自分の足跡になるのでは……」と、日々忘れていく自分の性格からそう思うようになった。それならば、今までためた印を印刷して一冊の本として残そう。今ならコピーで簡単に作れるのだが、当時はそれなりの苦労があった。さいわい同じビルに小さな印刷所があり、社長に頼んでみると快く引き受けてくれた。紙も和紙風の用紙を買ってきた。印刷する印影の色は赤。印刷屋は「何か赤色を刷る時についでに刷りましょう」ということだった。これも今のように印泥の色にこだわるという知識も意識もなく、赤だったら何でも良かった。 私が自費で本を作り始めたのは篆刻を始めたころ、もう30年以上になるだろう。初めて印に出会い彫り出した当初、あまりにも面白く次々と印ができるのがうれしかった。ほとんどの印は人にあげてしまって、自分の手もとには印影だけが残っていく。ある時、「こうして印影を残すことは自分の足跡になるのでは……」と、日々忘れていく自分の性格からそう思うようになった。それならば、今までためた印を印刷して一冊の本として残そう。今ならコピーで簡単に作れるのだが、当時はそれなりの苦労があった。さいわい同じビルに小さな印刷所があり、社長に頼んでみると快く引き受けてくれた。紙も和紙風の用紙を買ってきた。印刷する印影の色は赤。印刷屋は「何か赤色を刷る時についでに刷りましょう」ということだった。これも今のように印泥の色にこだわるという知識も意識もなく、赤だったら何でも良かった。
 印譜集というのは昔から「和とじ」のイメージがあった。だから印を勉強しながら、本の装丁は決まっていた。さて「和とじ」とはどこに頼めばいいのだろう。今のようにインターネットですぐ調べられるわけでもなく、また「和とじ」のできる人を探すのも大変だった。ようやく見つかってみると、思っていたより近くで普通の民家。気のいいおばあさんが内職で一冊一冊「和とじ」に仕上げていくのだ。だが手作りの為、 印譜集というのは昔から「和とじ」のイメージがあった。だから印を勉強しながら、本の装丁は決まっていた。さて「和とじ」とはどこに頼めばいいのだろう。今のようにインターネットですぐ調べられるわけでもなく、また「和とじ」のできる人を探すのも大変だった。ようやく見つかってみると、思っていたより近くで普通の民家。気のいいおばあさんが内職で一冊一冊「和とじ」に仕上げていくのだ。だが手作りの為、 仕上げ代が高いので簡単な方法の和とじにした。 仕上げ代が高いので簡単な方法の和とじにした。
そうして出来上がったのが自費出版本の第1集目だ。とりあえず300冊を作った。(先日書斎展に見えた京都の古いファンの女性から、「私は第1集からずっと持っていますよ」と言われたのには驚いた。振り返ってみると、彼女が高校生のころからの付き合いだ。ファンとはありがたいものだとつくづく思った)。
|