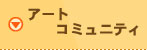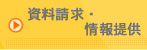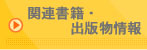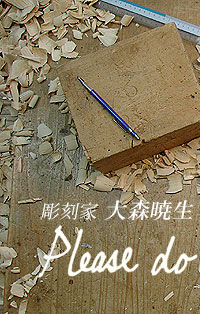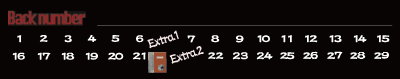| |
大森 校正とかチェック作業も完全に明け方とかなんで、能力がガクッと落ちるじゃないですか。だけど不思議な閃きも出てくるわけで。デザインの神様が降りてきたり(笑)。
桑名 もう出来ないですよね。インデックスページにしても、プリントアウトしたゲラを一枚一枚切り出して、その四隅をパンチで角を落として、それを束見本に挟んでひと見開きずつ撮ったんですもんね。誰がこんな企画提案したんだ?……って自分ですから。自分で自分の首を締めたようなもので(笑)。
大森 最後差し替えたページも、事務所の台所の前に撮影セット組んで撮りましたよね。
|
|
あと、いつだか深夜にNojyoさんが顔出してくれて、みんなを和ませてくれたり。
桑名 そうそう、激励に来てくれたね。でも、みんな徹夜続きで疲れていたから、いまいちノリが悪かったかもしれないよね(苦笑)。
桑名 あんまり引きすぎると、流し台の栄養ドリンクの空き瓶の山が見切れちゃうみたいな。あれは一枚、写真でおさえておきたかったですね(笑)。当時は何晩も徹夜してフラフラでした。それとプレッシャーですよね、「ホントに終わんのか?」みたいな。ただひとつ信じていたのは、「出来上がるんだ」っていう事だけ。笑い話で話せるからいいけど、ちょっとした合宿でしたよね。 |
|