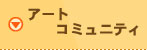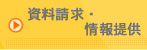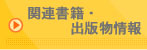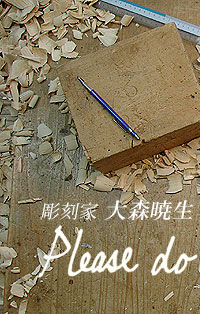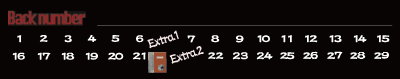あっという間の年の瀬です。
暖冬だとか温暖化だとか言われていても、さすがに東京も本格的な冬の寒さ。寒いと身体も縮こまり、制作も億劫になるもの。けれど彫刻家というものは美術大学にいた頃から、どこか体育会系のようなイメージが付きまとい、雨風雪の中、ドカジャンを着て鼻水垂らしながら鑿を振るう……そんな美学がどうも蔓延している。たしかにこの時期、自分も屋外で材木を品定めしたり、それをトラックから工房に荷下ろししたり、そして大木を前にチェーンソーや鑿を振るう姿は、さぞや男らしいガテンなイメージだろう。けれど本心は、出来るだけぬくぬくと暖かい環境で、ゆったり制作したいものなのだ。
そこで、コラムvol.20「木のはなし」でも少し触れたが、4年前に工房を新しく構えた際、薪ストーブなるものを導入してみた。“薪ストーブ”って響き、いかにも軽井沢の別荘族、そんな優雅なイメージが広がるけれど、実のところウチでは暖房設備と同時に“焼却炉”という重要な役割がある。木彫を一つ彫り上げると、そこから出る木屑は出来上がった作品の何倍もの量に膨れあがる。大作ならなおのこと。チェーンソーで荒取りした端材などは、ゴロゴロしているわ尖っているわ重たいわで、いわゆる指定ゴミ袋なんかに入れたらすぐに破れてしまうし、いくら詰めてもキリがない。しかもご存じの通り事業ゴミは有料なわけで、これが案外馬鹿にならないのだ。ならば木だもの、燃やしてしまえばいいのだけれど、東京都では平成12年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、個人での焼却炉の使用が禁止されてしまった。住宅の密集する都心でモクモクと黒い煙をあげるのはやはり難しいだろうとうなずける。
しかししかし、建築雑誌を開くとここ数年、住宅に薪ストーブを入れるのがカッコいいとあれこれ載っている。「えっ、薪ストーブならいいわけ?」そんなことがきっかけで、あれこれ調べた末、都内でも使用可能な機器の導入へと至ったのだ。
ウチには毎日のように様々なお客様がみえるが、冬時期、この薪ストーブはすこぶるウケが良い。そして本人、ウチの工房まで足を運んで下さった方への、ちょっとした“おもてなし”の気分なのだ。
つまり木っ端のゴミは片付くし、暖かいし、お客様は喜んでくれるし、良いことずくめ、“快適薪ストーブライフ”というわけ。
しかしながら……この薪ストーブライフを楽しむためにはひとつ大変な作業が待っている。
そう「煙突掃除」だ。
年に一回の大仕事。屋根に上って前の冬にこびり付いたススやタールを綺麗に落とさなければならない。これを怠ると煙突内火災というのを引き起こしてしまうので、大事な大事な作業なのだ。
この東京ではいわゆる“冬支度”なんて言葉も、今までそれほど馴染みがなかったわけで、この煙突掃除、「これから冬を迎えるなぁ」なんて気分がグッと盛り上がり、なかなかオツなもの。
というわけで、今回のコラムはウチの工房の煙突掃除の模様をドキュメントでおおくりしたいと思います。
|