 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
|
※画像はクリックすると拡大画像をひらきます。 |
 |
| 今年も恒例のアートフェア東京が無事に終わり、早一ヶ月あまりが過ぎた。 恒例というのも、アートフェア東京への出展も今回で四回目(旧「NiCAF '99」を含む)。初めて参加したときは三人展で、その後三回は個展で発表してきた。移り変わりの激しい今の現代美術界において、三回つづけて個展をさせて頂けた事は、ほんとうに恵まれた状況であると感じるとともに、多少なりとも自負としているところもある。もちろん、毎回多くの課題や宿題も残るのだけれど、それを次のフェアでまた再チャレンジすることの出来る状況はありがたいことだ。 アートフェアというもの自体、今では記事が載らない美術雑誌はないくらい、この日本でも定着してきたけれど、初めて僕自身がアートフェアというものを知ったのは「NiCAF YOKOHAMA'93」だった。予備校時代に教わっていた講師の先生がこのアートフェアに出品するというので、当時美術大学に入学したばかりの僕は、“アートフェア”というものが一体なんなのかも分からないままに会場であるパシフィコ横浜に向かった。するとそこには信じられない数の作品がズラッと並び、なにより各作品のスケールの大きさに驚かされた。中でも立体作品がとても多かった印象で、“美術展”というよりは“野外作品”を室内に持ち込んでしまったかのような迫力に圧倒されたことを、今でも強く覚えている。大好きな作家であるマグダレーナ・アバカノヴィッチさんの彫刻の実物を初めて見たのもこのフェアだったと思う。そして、アートフェアのその華やかさは、学生だった自分をすっかり虜にし、その時から自分の作品をこのアートフェアに出品する事が遠い憧れになったのだ。 |
 |
 |
| 六年後、その実現は突然にやってきた。当時、僕の作品を熱心に扱ってくれていたgaden.comさんが「NiCAF'99」において山内隆さん、金澤一水さん、そして大森暁生の三人展を企画してくれたのだ。アートフェアなど、遠い遠い存在だと思っていた自分はすっかり興奮し、「会場で一番目立つ作品をつくってやる」と鼻息も荒く臨んだのだ。 その頃は実家の片隅で制作しながら、少しずつ不動産屋を回りアトリエ物件を探していたのだけれど、“会場で一番目立つ作品”となるとこれはもう一日も早く広い作業場を確保しなければならない。不動産屋巡りもピッチをあげ、そうして見つけたアトリエが荒川区町屋に構えた最初の工房だった。「NiCAF '99」本番までに残された時間は約三ヶ月、一日十五時間寝る間も惜しんで創り上げた「ぬけない棘のエレファント」は、今でも自分の代表作になっている。 |
 |
 |
 |
 |
| さらに二年後の「アートフェア東京2007」。今度はギャラリー小暮ブースから個展での発表。この時はお隣の村越画廊ブースから発表されたミヤケマイさんとのコラボ企画。“遊園地”という共通テーマのもと、それぞれが互いの世界観で個展を創り上げた。2人の合作もそれぞれのブースにコソッと一つずつ忍ばせたりと、二人展とはまた全然違ったコラボ・ダブル個展。作品はいつも生真面目な大森暁生も、この時ばかりはミヤケさんの遊び心あふれる世界にすっかり影響を受け、架空の遊園地“BAT LAND”を夢中で創り上げた。これは今振り返っても面白い企画だったなぁ、と思う。 |  |
 |
 |
 そして今春、「アートフェア東京2008」。今回から毎年の開催になったようだ。この事をみてもアートフェアが国内に浸透してきた事を感じる。 そして今春、「アートフェア東京2008」。今回から毎年の開催になったようだ。この事をみてもアートフェアが国内に浸透してきた事を感じる。今回は新生堂ブースとギャラリー小暮ブース、自身初の2ブースからの出展。新生堂ブースでは2ブース分の空間を、画家の瀧下和之くんと大森暁生とで左右2つに分けて、それぞれの個展を展開した。 |
 |
|
|
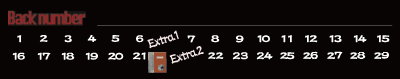 |
 |
|
|
|




