 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
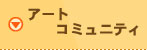 |
||||||||||||||||
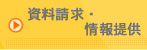 |
||||||||||||||||
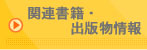 |
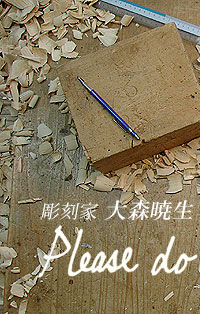 |
 |
 |
|
※画像はクリックすると拡大画像をひらきます。 |
 |
| vol.7 前編よりつづき |
| 今回の視察では2日目以降、日本とニューヨークを行き来しながらアートディーラーをされているTさんと現地で落ち合い、その方にいろいろと案内をして頂いた。心強い限りである。 |
 |
 |
| この大空間を生かした本場のアートを早く観てみたいと焦る気持ちを抑えながら、ギャラリーを一つひとつしらみ潰しに回る。つぎつぎ巡る……きっと次こそ……あれ……。そう、面白くないのだ。全然。いや面白いという表現は曖昧だね、感動しないのだ。何だろうこの感覚。もしかしたらそれは、“手数”としてクオリティーの稚拙なものが大半を占めていて、技術や技法としてその国の文化特有の熟成されたモノが見当たらないからなのかもしれない。もちろん現代のアートシーンでは、その部分が評価の全てでない事は充分に承知の上だけれど、歴史と時間を刻み込んだ倉庫という重厚な空間の中で、作品の“品格”が圧倒的に負けてしまっていた。だからだろうか、頭で思い描き、期待していた“本場ニューヨーク”とのギャップがどうにも埋まらない。僕だけではなかった。どうやらTさんも同じ感想。
ここ数年の世界的なアートフェアブームは大変喜ばしい事ではあるが、もしかしたら作品の“品格”までもがアートフェア特有のあの仮設ブースのレベルに揃ってしまったようにも思えるのだ。流行りやノリだけの作品は、仮設ブースでは上手に誤魔化せても“力を持った場”の中では簡単にそのメッキが剥がれる。この事は、アートフェアでの発表が多くなった自分自身こそ重々肝に銘じる事なのだ。 |
 |
 |
| 二人ともなんともしがたい気分のまま2日目の夕食へ。グランド・セントラル・ステーション内にあるステーキハウスで、なんとオーナーはあのマイケル・ジョーダン! 天井に星座が描かれた巨大なメインコンコースを見上げながらの食事は、なんとも気持ちが良い。この店で一番大きいサイズというステーキも、ほんとうに美味しくてペロリと完食。こうして2日目が終わった。
(2008.01.24 おおもり・あきお/彫刻家) |
 |
| vol.9 へ つづく |
|
|
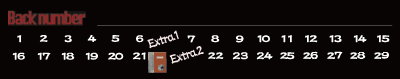 |
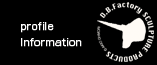 |
|
|
|

