 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
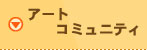 |
||||||||||||||||
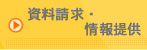 |
||||||||||||||||
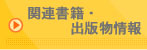 |
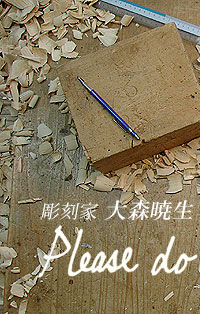 |
 |
 |
|
※画像はクリックすると拡大画像をひらきます。 |
 |
|||
| 11月初旬、『アート・トップ』1月号誌上での北川宏人さんとの対談のために、八王子にある氏のアトリエへ。今を時めく作家の一人である北川さんとは今回が初対面。多少の気負いは見せぬよう……。 以下、誌面上からの抜粋に加え、誌面では掲載出来なかった部分も含め、対談番外編としてお楽しみ下さい。 (心のつぶやき付き) |
| 大森:僕は立体の醍醐味というのは、昨日まで世の中に無かった塊が、目の前に出現するところだと思うんです。頭に思い描いた形が、エスキースなどで一度姿が見えてしまうともう飽きてしまうというか、薄れてしまうような気がするんです。 |
|
| 大森:ところで、制作の大変さというか手間というものを分かってもらいたい、みたいなところってありますか? |
|
| 北川:心情的にはどこかにはあるのかもしれませんけど、自分の手から離れていくものですからね。作品は作品、後になって注釈や説明など加えられませんし。 |
|
| 大森:そうですね。でも、日本人ってわりと分かってもらえないところ、見えないところに凝るみたいな。粋というか、そういうところがあるように思うのですが。 |
|
| 北川:それはそれで、格好良さもありますけどね。 大森:そういうところは、僕も変えたくはないんです。ただ、僕が木や漆を用いているのは、あくまで一素材としてであって、漆工芸などの伝統を受け継ごうという意識は薄いんです。 北川:落としどころが違うということは、既にフィールドが現代美術なんですよ。 |
|
 |
 |
|
大森:その現代美術なんですけど…、北川さんにとってコンテンポラリーってなんですか? 北川:たとえば、百年後に今を振り返ったとき、当時はこのような美術作品が存在していたとか、その時代に人類がなしえた創造物とはこういうものでした、というものを、いま現在進行形で作っているのが現代美術でしょ? 過去の職人たちが何世代にもわたって築き上げた技術を、後世に伝承していくものが伝統工芸だとすれば、コンテンポラリーアートは近代美術の概念とは違った、何か新しいものを生み出していなくてはならないと思います。 大森:今の時代に生きていて、今を作ってれば、何であれコンテンポラリーでいいと思うんです。けれど、どこかコンテンポラリーという言葉が一人歩きしているような気がするんです。 |
|
| 北川:言葉の使い方が表面的な感じはしますよね。 大森:そう、そうなんですよ。 北川:でも結局、それは美術業界の周りにいる人たちが勝手にしていることだから気にしなくていいのでは? |
|
| 大森:もちろん、それに合わせて作品を作るということはありえないし、自分の軸も揺るがないんです。けれど客観的な評価によって、嫌な言い方ですけど、損する・得するが出てきちゃってるところがあると思うんですよね。 つまり、工芸だろうがクラフトだろうが何だろうが、やっぱりきちっと作って感動させるものは、そんなもの全部飛び越える力を持っているのに、何かそういう部分をごちゃごちゃ言うことに、すごく抵抗感があるんですよね。 |
|
 |
 |
| 北川:その点、僕はある程度わりきって考えていて、どのフィールドで自分が評価されたいのかは自分で選ぶべきだと思う。そしてそのフィールドで闘うためには何が必要かっていう部分は自分で強化していかなければならないと思う。
僕の場合だったら、基本的には作りたいもの作る。でも、それとは別に評価もやっぱりしてほしいし、評価されないと作家として自立できないからね。じゃあ今の現代美術の中で、どういった打ち出し方ができるのかとか、自分に出来ることは何なのかを考えますよね。日本という国はグローバルな視点から観ると、いろんな意味で特殊だと思うんですよね。簡単に欧米化されている部分もあるけど、絶対に譲れない島国根性的な部分も持ち備えている。多くの要素が絡み合って、いまの現代人の姿がある。精神的な部分も含めて今の日本人独特の奇妙さとか特殊性や感性みたいなものを具現化したいんです。 |
|
| 大森:では、作品は日本人なんですか? 北川:そうですね、今はもう日本人です。最近は高校の制服を着ているネイティブな日本語を話すハーフの人達も増えてきてますよね。それも一つの日本という街の形だと思うんです。基本的には、僕は今の日本という特殊な匂いとか、積み上げられてきた日本人の感性、装いも含めて、それを表現したいんです。 |
|
| 大森:僕が作っているのは、最近はタイトルに「Gothic」を付けたりしてますが、そのおおもとは、日本のお祭りの御神輿だったりします。たとえば、御神輿などは装飾美の極みですが、日常に使う要素は薄い。けれど、まったく用が無いものかといえばそうでもなくて、用途はあるんだけれど精神的な用途というか。そのきわどいところにある装飾性とか、デコラティブな存在がすごく気になってしまうんです。 |
|
| 北川:面白いですよね、そういう切り口。 大森:最近、ファッションブランドと仕事をする機会もあるんですけど、ショーなどの衣裳って、絶対に街なんかを身につけて歩けないような衣裳があるじゃないですか。 僕の作品をブランドの洋服に置き換えれば、大きな作品がショー用の衣裳みたいなものであって、僕の方向性とか理念を全部入れるようなもの。小さな作品は例えばTシャツのようにそれらを還元させたものであって、買ってくれた人の生活の中に溶け込んでくれたら嬉しい。そういった制作のバランスが、自分でもすごくフィットしているし、これからも外したくはないなって思うんです。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 北川:作家として生き残る為にはキャリアアップも必要だし、現代の日本人独特の奇妙さとか、特殊性や感性を具現化したいとか話しましたが、特に小難しいことが分からなくても「いいねぇ」の一言で、ポンと買ってくれる人がやっぱり一番ありがたいですよね。 大森:そうですね。 北川:感覚的に僕の作品を嫌いな人はやっぱり嫌いだと思うんです。感覚的に面白いと思わない人にいくら説明しても無理だと思う。彫刻という言葉の括りも少し難しく捉えられがちなのですが、感覚的に僕の作品を好きでいてくれる人というのはもう見た瞬間に「ああっ!」って見入ってくれますからね。 万人に受け入れられるというのは無理な話であって、どこかの層に響けば……。かといって、人の興味というのはひょんなところから、何かのきっかけで火が点くこともあるしね。 大森:そういうきっかけになれたら嬉しいですね。 |
|
| 《対談後記》 北川さんは僕よりも4つ年上。同世代の心強い仲間であるが、北川さんから見れば若造の僕をどう思っただろう。作家はそんな端からの見られ方など気にしないのがカッコイイのだろうけれど、そういう事がすごく気になる自分……。 モノを作ることで一生食べて行きたいと、常々それが目標の自分。今はたまたま美術のフィールドが自分を相手にしてくれているだけだと思っている。だからそのフィールドが何処になろうとも、それはそれで厭わず、逆に言えばそれが出来れば“つくり手”としての本当の強さなんだと信じている。 だから今回の対談での「自分の勝負するフィールドを“現代美術”と割り切っている」という北川さんの言葉は新鮮だったが、そこを割り切って勝負することはまたひとつの強さなんだなぁ、と素直に感じた。 それにしても北川さんのアトリエの窓から見える八王子の景色、良かったなぁ。 (2007.12.24 おおもり・あきお/彫刻家)
|
|
((詳細は、好評発売中の『アート・トップ』1月号 巻頭特集「いま、立体作家が面白い!」対談をご覧下さい) |
| 北川 宏人(HIROTO KITAGAWA) 1967年 滋賀県生まれ 1989年 金沢美術工芸大学彫刻科卒業 1990年 渡伊 ミラノ、アカデミア美術学院彫刻科入学 1998年 カラーラ、アカデミア美術学院彫刻科卒業 2004年 帰国 国内外にて個展・グループ展多数 |
|
|
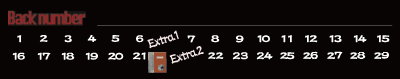 |
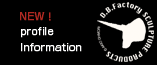 |
|
|
|


