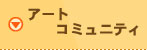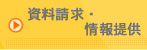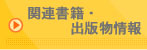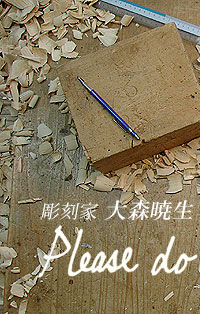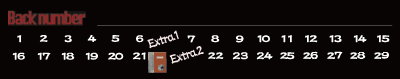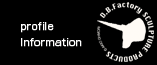|
|
| |
男というものは「道具」とか「ツール」という響きにめっぽう弱い。さらには「プロ用」とか「本格派」なんてフレーズが付こうものなら、もう手を伸ばさずにはいられない。たいしてエンジンもいじれないクセにクルマが大好きな自分は、外国製の自動車工具がピカピカと輝きながらずらっと並んでいるショーケースには、一度へばり付いたらなかなかそこを離れられない。そんな男達を「何が楽しいんだか、まったく……」と呆れ顔の女性達だって、キッチン用品や化粧用品売り場では同じように目を輝かせ始める。道具というモノへの憧れは男女を問わず、石器の時代から刷り込まれたDNAなのかもしれない。
そういえばこのコラムのトップも彫刻刀の写真だし、そろそろそれら道具の事など書いてみようか。 |
|
| |
 自分は木彫家なので、説明するまでもなく道具の一番の主役は彫刻刀である。 自分は木彫家なので、説明するまでもなく道具の一番の主役は彫刻刀である。
おそらく一般的な彫刻刀のイメージは、小学校の頃に年賀状の木版などを彫った、あの6本くらいのセットではないだろうか。我々の使っているものも基本的には一緒なのだが、質や大きさ、種類などがだいぶ違う。ひとくくりに「彫刻刀」と言っても、正確には「叩き鑿(のみ)」「小道具鑿」「彫刻刀」と分かれ、制作の各段階や箇所によって使い分けている。これらの道具は買ってくればすぐに使えるというものではなく、最初にキチンと「仕立て」というものを施さないといずれガタがくる。「研ぎも自分でするんですか?」とよく聞かれるのだが、そういった普段の手入れももちろんの事である。研ぎは刃が欠けたらするものと思われがちだが、ちょっとでも切れ味が悪くなると彫っていて気持ちが悪いし、なにより制作の精度が落ちるので、それこそ一日に何度も砥石のある流し台とを往復する。キチンと手入れをすることで、木彫道具はそれこそ一生ものとして使えるのだ。
日本の刃物の性能は世界でも一番で、聞いた話だが外国のクラフトマン達にとって日本の木工具を持つことは相当なステイタスらしい。ドイツのゾーリンゲンのナイフなどは男心をくすぐるが、切れ味は日本の彫刻刀の比ではない。
|
|
| |
そして彫刻刀と同じくらい、一生手放したくないと思うほど大事にしているのが木槌(きづち)だ。これは学生の時から使っているのでもう十四年くらいになるわけだが、これも買ってきたそのままではなく、柄や頭の部分を使いやすい長さ、重さに切っている。木槌は樫(かし)の木を使うのが一般的だが、樫は叩いているといずれ割れてきてしまう。けれど愛用しているこの木槌はサルスベリの木を使っていて、これが比重や叩き心地が絶妙、しかも丈夫。ほんとうに具合がいい。
その他、鉋(かんな)、手引き鋸(のこ)、罫引(けひき)、差し金(さしがね)……数え上げたらきりがない。
学生時代は実習で、粘土、石、金属、石膏……とありとあらゆる素材を扱ったのだけれど、現在木彫を中心としたスタイルになったのは素材の持つ魅力はもちろんのこと、これら木彫道具に惹かれた部分も大きい。 |
|
| |
これらの基本的な木彫道具はそれこそ何百年もほとんど姿を変えることなく使われてきたいわば手工具だが、現代の道具もそれなりに使用している。
チェーンソー。これは製材からある程度材料のカタチを整えるまでの工程に使う。室内で使うため電動のものだが(林業家などが使うチェーンソーはエンジン)使い続けるとヒートしてしまうので2台を交互に使う。
そしてバンドソー。厚さ20センチくらいまでのものなら、この機械でかなり精巧に製材できる。あとはドリルに、電動鉋、ジグソー、丸鋸、そんなところかな。 |
|
| |
工房にみえるお客様曰く、意外と大型木工機械が無いことに驚かれる。
そう、彫刻家は手工具にしても電動工具にしてもやっぱり手に持って使う道具がほとんどなのだ。だからこそ同じモノは2つと出来ないし、その時の気持ちや気分が作品にストレートに影響する。そこが難しさでもあるが何よりの面白さでもあるのだ。 |
 |
|
| |
そして道具が手に馴染み、自分の気持ちと一体となった時のその感覚は我々モノづくりに携わる者の一番の醍醐味かもしれない。そしてその瞬間、道具を扱う自分の「手」こそが、何より最高の道具である事は言うまでもない。
(2007.10.30 おおもり・あきお/彫刻家)
|
|
|