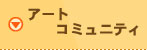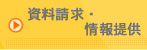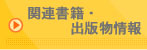|
 |
 |
 |
 |
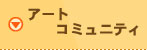 |
|
|
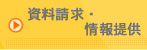 |
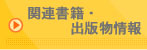 |
|
|
|
|
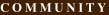 |
 |
≪前頁より続き≫
漢字は俗に五体と呼ばれる篆・隷・草・行・楷の書体の別がある。この中の篆書が古代文字であり、隷・草・行・楷の四体を近代文字と称してよい。さらに大まかに言うならば、隷草行楷の四体は一括して隷書と言ってしまってもよい。隷と楷とはほとんど同じ者、草行は隷書の分支なのだから。
そこで文字学も古代文字学と近代文字学との別が出てくる。字源学は古代文字学の一部なのである。それでは近代文字学とはなにかというと、これは隷書以後の書体・字体の変遷、特に隷変またそれ以後の異体字について考察する。平たく言えば俗字学である。これは昔から軽視されて来た者であり、今もなお軽視されているが、近ごろ漸く中国で専門の研究者が出はじめ、研究書も数種出版されるようになった。そもそも章句の末に拘わる者を迂儒とか腐儒とか呼んでバカにするのが常であるが、異体字の研究なんて、章句の末どころか、點畫の末に拘わる者であるから、学者先生たちからマトモに相手にしてもらえるような代物ではない。とはいえ実際にやってみると意外に面白く、ケッコウ病みつきになりかねない。だからお歴々の先生方はみな軽して遠ざけることになるのも当然なのである。 |
漢字は我が邦で使用されるようになってからすでに一千数百年になり、その間に本国とは異なる獨自の形も生じて来た。その多くは所謂る和様の書風が成立してからの者であるが、意外にも和様成立以前に我が邦獨自の異体字が出来て、それが後世まで傳えられている者がある。今それらの二、三を挙げてみよう。先づは「逃」の字。この字を「迯」に作るのは我が邦では近世に至るまでごくふつうの書き方であったが、シナにはその例を見ない。これは逃の草体を楷書にもどした形である(圖一)。この形がなんと光明皇后の杜家立成、空海の聾瞽指歸にすでに見えている(圖二)。「樣」の字は、我が邦では、永様、次様、水様といって、右下部を永・次・水に作る三通りの書き方があり、その順でより敬意を表わすことになっている。永・水はともかく、なぜ次になるのか。これは行書の形を楷書にもどしたのである(圖三)。永の行書の筆順12345を31425とすれば、次になるだろう。この形が最澄の越州録にあるが、シナには見ない(圖四)。
「違」を「 」に作るのは、これも後世ふつうの形である。おそらく韋の草体の右下に補空の點を打った形から轉訛したのだろう。シナでは唐代の墓誌にたった一つその例を見つけたのだが、あいにくその墓誌の名を忘れてしまった。 」に作るのは、これも後世ふつうの形である。おそらく韋の草体の右下に補空の點を打った形から轉訛したのだろう。シナでは唐代の墓誌にたった一つその例を見つけたのだが、あいにくその墓誌の名を忘れてしまった。 |
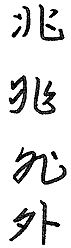


|
| |
《圖三》
 |
《圖四》

|
|
|