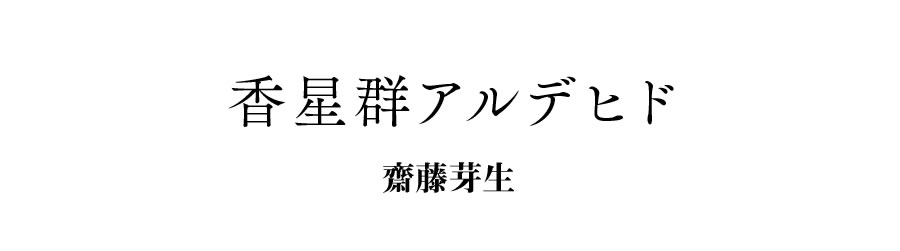3. 53
思えば長いことこの冬枯れの中に住んでいる。
白い舗道と乾いた建築の壁が延々と続いている。病院のプラスチック食器みたいな町だ。
建築の一つ一つは角が丸くて、冷たいくせに奇妙ににせの暖かみを感じさせる。
すべてが擬似的な雪の色の中にある。でも雪はここ数年降っていない。いっそ本当に雪でも降れば、少しは日々に潤いが訪れるかもしれないのに。
この荒れ地で心から親しめる人に出会うには、火星を探索するくらい時間がかかるだろう。
誰かの手を握ったり、また握り返されたりしてみたい。他人の手がどんな温度なのか、自分は全く知らない。今まで出会った幾人かの顔を思い出しても、その体温を確かめた経験はない。
年中手が冷たくて、いつも服の左ポケットに指先を入れている。今日はなぜか、コートのポケットの内側がいつもと違うような感覚がある。
左ポケットが二重になっているのだ。
布が破れたのでもなく、もう一つの袋が袋の中に出来ている。上から見ても袋は二つになっている。右は変わらず普通のポケットなのに。
二重の袋の片方の底を探ると、何か渇いた感触に当たった。皺くちゃのレシート。印字された商品を読んでみる。
ニジュウバ アンゼンカミソリ。買った覚えはない。
もう一度手を入れ、今度はもう少しかさばる紙屑を探り当てた。
捻り潰された煙草の箱。煙草は吸わないので、明らかに自分のではない。
コートを他人のと取り違えたのか。けれど糸のほつれにしても、着心地にしても、いつものコートに変わりはない。左ポケットだけが、底光りする奇妙な場所のように感じられる。
誰も遊ばない公園の脇を通りかかる。白い椿の樹形だけが定期的に整えられている。
どうやら今日はこの二重ポケットのその先が、見知らぬ誰かの住む世界と繋がってしまっているみたいだ。
この世界の出来事は、向こう側に届くだろうか。椿の白い花びらを一枚拾って、二重ポケットの底に忍ばせる。花びらから指が離れないうちは、別に何事も起こらなかった。それをもぎ取ろうとする向こう側の指を待ってみたけれど、そういうものには触れなかった。
けれど手を引き出そうとした瞬間、ポケットの花びらが消えた。確かにそれは、内側のポケットの奥に吸い込まれていった。
糸屑やら、値札シールを折り畳んだのやら、誰かの生活のごみが次々とつまみ上げられる。
飴の包みで帆掛船を折りポケットに忍ばせてみる。すっと消える。別の紙を舟型に細工したものが、ポケットの底に送られてくる。こちらのようには器用に作れず、見よう見まねで作ったような形をしている。
それを見て微笑が浮かんできてしまった。
見えない人との通信が始まった。初めのうちはもったいぶるのが楽しかった。
意味のないごみ屑ばかりを精巧に細工して送った。軽く笑ってほしかった。ほつれ糸を繋いで糸巻きのように巻いてみたり、使いみちのない便箋を切絵にしたり、落葉に顔を描いたものなどをポケットに忍ばせては、向こう側の世界に送り込んだ。
でも手紙など、一つの文字すらも送らなかったのは、相手についての決定的なことを知るのが恐いからだった。
あなたの名前は何ですか。私の名前は……です。
指先さえ触れられないやり取りに、かしこまった自己紹介を差し挟めずにいた。
相手が送り返してくるのは、ひねった飴の包みやどんぐりのように単純なものばかりだ。
けれど、ポケットの底になにかが浮かび上がる瞬間は、震えるような嬉しさを感じた。
黒いボタンが送られてきた。きっと上着からとれてしまったのだろう。携帯裁縫セットから針を取り出し、黒い糸を付けてボタン穴に突き刺して、送り返す。ボタン一つ縫い付けることさえ手伝えないのだから、そうするしかない。
どこかの店のレシートでつくられた紙飛行機を開きながらも、文字を読んで相手のことを知りすぎてしまうことが恐かった。けれど向こうはレシートの店名の記されてない部分だけちぎって折紙にしていたので、店の場所は結局わからなかった。
「ポテトサラダ」「モチモチアイス」。そんなものを食べたことだけはわかった。
相手の町にもきっと殺風景なストアがあり、普通の生活をしているのだろう。隣町のような世界とこの世界とは、どうしてこんなに近くて遠いのか。
ある日、相手からの返信が数日途絶えた。胸が騒いで、なにか文字を書き送りたくなった。
いかがおすごしですか?具合でも悪いのですか?
聞きたい言葉は山ほどあるのに、どんな言葉を記すのもなにか怖い。社交辞令も率直な質問も、気持ちにそぐわない。
欲しいものは?という言葉を、ボールペンで一言書き送った。
なぜよりによってそんな言葉を送ったのか、あとで赤面した。でも多分それは、例えば帰宅中の家族や恋人が駅前から「なにか買ってきてほしいものは?」と電話をかけてくる親しい感じを、自分がずっと憧れているからだ。
やがて久しぶりの返事が送られてきた。「53」とだけ、そこには書いてあった。
しばらく頭を悩ませる。53にちなむようなもの。トランプも確かそのくらいの枚数だ。住む場所のヒントかもしれない。なぜ、ごみのような紙に宇宙人の交信めいた思わせぶりな一言だけ、なんだろう。
その時ふと、53とは「ごみ」のことなのかもしれない、と思った。
このまま、ごみ屑籠に棄てあうようなささやかなやり取りだけを続けよう、と暗に言っているのではないか。
相手はたぶん自分よりも更に、もどかしい人なのだ。そのもどかしく揺れる吊橋を、一歩一歩渡ってゆこう、と決めた。
何かのかけらや木の切れ端で、心をくすぐり合うような関係が続いた。ユーモアを込めるわけでもない。暗号のようなメッセージを読もうとするのもやめた。
生きてるの。生きているよ。それだけで充分な気がした。
意味のないごみの手触りを認めあうことが、何よりもこの冷たい毎日に温度を届けてくれるのだ。
真昼、ふと何か冷たいものが頬に触れたので、はっとした。
雪が一粒、頬に落ちたのだ。十数年ぶりに見る雪だ。白い穴のような空から、解き放たれたように次から次へと氷の屑が落ちてくる。
この町にも雪が久しぶりに降った。相手に知らせたくて仕方がなかった。ごみ屑の友情はごみ屑なりに、次の熱を欲していたのかもしれない。
椿の植込みで、雪に降られながら座り続けた。寒いけれど、心は熱かった。
雪よ、早く積もれ。ほんの少し積もった頃、弾む心で、白椿の葉に乗せた雪をそのままポケットに忍ばせた。
けれど次の瞬間、心が凍りついた。
ポケットがもう二重ではなくなっていたのだ。
しばらく、何の言葉も、心に浮かばずにいた。初めから百も承知だった気もする断絶を、あらためて飲み込むだけだった。
ポケットじゅうが雪で濡れて冷たくなっていた。向こうの世界に吸い込まれるのではなく、ただ溶けて水になり、滲み入っただけの雪だった。
けれど、滲みてゆく冷たさの向こうに、他人の指が自分の指を探して同じように触れ返すじんわりとした体温を、確かに感じた。