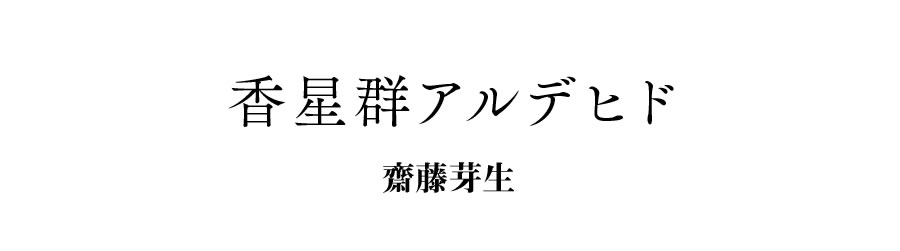1. 香星群
たなびく雲が色彩を反射する。
色とりどりの星が夕暮の中空に浮かんでいるのが見える。
浜辺の簡易チェアーに腰掛け、師匠は渋い顔つきで星を見上げながら、煙草を吸っている。
「俺の故郷に精霊流しの行事があって、あんな光だった。提灯を海に流すんだ」
「香りを扱う人が煙草なんか吸うんじゃない、って言ったのは師匠じゃないですか」
諌めると師匠は煩わしそうに顔を背けた。
煙が夕空の、星が描く水玉模様に向けて立ち上って行った。
夕空に浮かんでいるのは小型の人工星である。
ひと一人が丸いタンク一体をそれぞれ所有し、お互いの距離を充分に取りながら、干渉せぬように空に浮かんでいる。
彼らは他者との結びつきを捨てた。家族も煩わしくて捨てた。
犬の声、町の色彩、隣家の音、ウェブ上に見つけた自分への批判、食生活すらも、一切を断ち切りたくて、ああして地上を脱出するようになった。
経済的な格差がここまで来た時代だからこそ、こんな風景も生まれる。自分のような貧者は、相変わらず地上にいてあくせく働いている。
「気が知れない。あいつら阿呆じゃないか」
「でも私達はあの人達のおかげで喰っているようなものでしょう」
「喰っている、と言うのはよせよ」
自分の職業は、各星々へ「香気体」を運ぶ仕事だ。
世の些事が煩わしいとはいえあの孤独の星人達は、ひととしての最後の証しなのか、自分の体臭や記憶の匂いを取り戻したがっている。
香気体を自分の星タンクに充填し、時々自分の首元に向けて噴霧するのだ。
私は小さな自由操縦タンク「エルネスト」に香気体を搭載し、空と陸とを行き来する。
香気体は、私の師匠である調香師があらゆる天然香料や合成香料を駆使して作る。海辺にこぢんまりとしたプラントを所有している。
弟子の中でも私は科学的知識が薄いが、師匠が最も煩わしがる、空の星人からの注文を聞いてくるという営業の仕事を任されている。
「そもそも他人の顔を見るのがいやで、他人の出す音にも匂いにも耐えられないと言って、地上を捨てた奴らだ。金で孤立を買っている阿呆だ。今さら何の執着で、あの夏の日の匂いだの、昔付けてた香水の匂いだの、なんて言い出すのか」
師匠は愚痴を言う。その愚痴を聞くのも自分の役目である。
「女はまだいい。イメージで香りを注文してくるから、イメージで返せる。中年以降の男はたちが悪い。『若い女の腋の下の匂い』『うどんの匂い』とか、身も蓋もない。そんな香りを俺に作らせてどうするんだよ」
例えば、かつて相当の暮らしをしていたであろう老婦人も、今は絶食と孤立の果てに、俗塵から洗われた仙人のようになって空に浮かぶ。
香気に包まれた生けるミイラくらい硬直しつつ、丸いタンクから半身だけ出し、うわ言のように注文をつけてくる。
「クローゼットの三番目の引出に大切にしまってあったの。スミレのサシェよ。
これでも瞳が鳶色に澄んでいて、外人の女の子みたいだなんて言われて、手紙なんかよく
もらったの。あの頃の私の匂いよ。先生に再現していただきたいの」
こんな台詞を何倍にも延長したような繰言を延々と頷きながら聞き、見たことがあるわけではない老女の娘時代を誉め称え、メモにはただ一言「少女期追憶系スミレ」と記して、地上に帰る。
ジャスミンの栽培園に師匠はいる。
私は、少女期追憶系スミレ一件、と報告する。
バイオレットリーフ、アイリス、パルマローザ、ヘリオトロピン、トンカ、オイゲノール、ヘキサノールなどの文字や分量などをボールペンで書いて、師匠は突き返す。
私にはまだ、この香料の世界には全く手が届かない。
無数にある香料はひたすら嗅いで覚えて行くしかないのだが、いくつかの師匠のレシピの調合訓練で出来上がった化合物を無闇に嗅ぎまくっていたら、頭をはたかれた。
何度も嗅がず、一度で嗅ぎ分けろ、というのだ。難しい世界である。
これだけは触るなと言われている、磨き込まれた銀色の丸いタンクがある。中はどういう風になっているのか全くわからない。
夜遅く私が自室に戻る頃、彼は実験室にそれを持ち出し、様々なものを詰めては実験をするようだ。
香気成分を分離するガスクロマトグラフィーという装置の一種らしいが、これは彼が開発したものらしい。きっと化学工場で使っているものとは何か違う秘密の構造を持っているのだ、と漠然と思った。
ある夕映えの上空で、思い詰めた目をした老人が、「自分の心の焔をもう一度燃やしてくれる香り」というような香気体の注文をしてきた。
注文を受けてからしばらく師匠は実験室にこもっていたが、難易度が高いようで、何度も試作を廃棄した。
私は完成品を嗅がせてはもらえなかったが、師匠は、男ならきっと嗅げばノスタルジーに浸れる匂いだ、俺も嗅いだら何かが燃えてきたよ、これは傑作かもしれない、と感慨深げに言った。
「この香気体は、本当に文字通り燃えやすい。引火性が強いんだ。運ぶときには気をつけろ」
私が慎重にエルネストに香気タンクを装備していると、また師匠は言った。
「もう一つ、これを注文した人間の自殺に気をつけろ。知識があれば、自爆の爆薬になるから」
心の焔を求めていた老人は、完成した香気体を吸い込んで喜んでいた。
ふと漏れるその香気体は自分には魅力がよくわからないが、強いて言えば草いきれの上のエンジンオイルのような匂いに思えた。
先生によろしく、と言っておりました。そう報告しながら私はエルネストを浜辺の置場に繋いだ。ご苦労、と師匠は答えて、簡易チェアで煙草を吹かしていた。
なあ、と師匠は海をぼんやり見つめながら言った。
「お前は何で調香師の俺に弟子入りしたの」
「香りが好きだからです」
何故、と言われて困ったが、答えた。
「否応無しに包んでくれるし、逃げられないようにさせてくれるから」
「俺がか」
「違います。香りというものが、です」
その時だった。自分が後にしてきた上空の老人の星の辺りで、派手な爆音がした。
美しい薄紫の炎と菊型の煙が、空に咲いた。
様々な残骸が海の上に散って落ちるのが見えた。
やったな、と師匠は呟いた。
数十秒の後、私もやっと、先ほど送り届けた香気体に摩擦かなにかで起こした火花を引火させ、老人が自死をはかったことを悟った。
黙って足下に吸い殻をなすり付け、おもむろに立ちながら、逃げるぞ、と師匠が言った。
「どこへ」
「空だよ」
「師匠が悪いんじゃないのに」
「そういう意味じゃない。死んだ奴は勝手に死んだのさ。そういう意味じゃないんだよ」
「では」
「俺と逃げるんだよ」
改まって真直ぐこちらを見据え、師匠は言った。
支度しろ、と言うので、自室に戻って荷造りしようなどと考えた。
すると唐突に師匠が、服を全部脱げ、と言うのだった。呆れ果てていると、無理矢理押し倒され、服を脱がされた。
何かいけないことをされているような感覚はなく、一連の作業工程のように彼は瞬く間に私の服を剥いだ。そして全く裸を堪能するでもなく、私を急いで床から起こすと、背中を押して実験室の中にせき立てて行った。
「俺が何かお前にするとでも思ってるのか」
私は寒さなのか動揺なのか、膝をついたままぶるっと一つ震えた。師匠の心がわからなかった。
「まあでも、するのさ。いまお前が思っているようなことじゃないけれど」
「何で服を」
「その方が香りが濃く出るからだ。お前に合ったサイズに装置を作ったから居心地はいいはずだ」
ガスクロマトグラフィーの銀のタンクを開け、私に入るように促した。逃げようとすると膝を使って中に押し込まれた。
「なあ、俺はお前が嫌いじゃないぜ。一緒に行くと決めただけだ。でもまあ、じゃあな」
そう言って、師匠は私の入ったタンクの蓋を閉めた。
予想に反して、実はタンクの中には特別、複雑な部品も機械もなかった。
それは本当に私が丸く収まるための暖かい寝床のようなものだった。
師匠は、トランクのように私入りの分離装置を持ち上げ、自分の脱出用に密かに用意していたらしい星タンクに自分も収まると、地上を脱出した。
私は自分のサイズにぴったりの丸い装置の中に詰められて、ぼんやりと自分の体温や体臭に感覚を集中させた。
生まれる前の胎児などというよりは種子に近い感覚で、例えば地上に再生した自分が咲き誇ったときの花の香りをじっと想像してみた。
そうすると汗の匂いや息の匂いも、自然にそのような花の匂いに変わっていくような気がした。
不思議と未練は無かった。愛車のエルネストだけに心の中でお別れを言った。
装置の機能で次第に真空になっていく窒息感に変な幸福を噛み締めながら、タンクの中で自分の半生の淡い想い出を反芻し、静かに肉体の匂いをポンプに向けて発散していった。