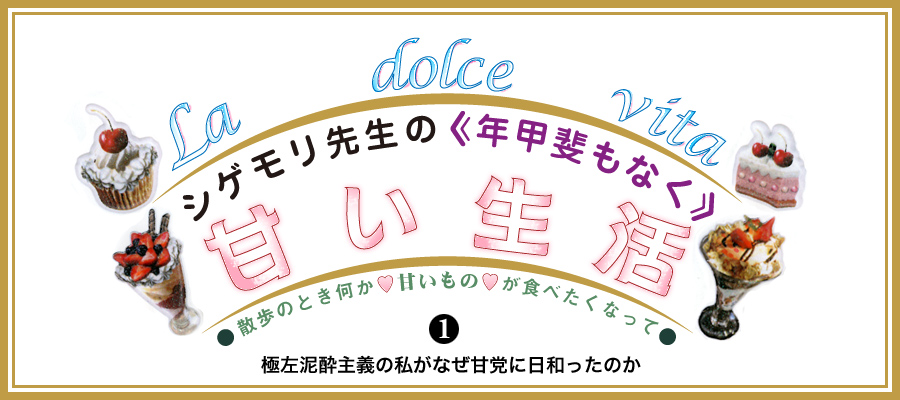「甘い生活」(La dolce vita)──ある程度ご年配の方とか映画ファンなら馴染みぶかいタイトルでは。(フェデリコ)フェリーニ監督、主演がマルチェロ(マストロヤンニ)、それに華を添えるのがアニタ・エクバーグ、アヌーク・エーメ。
音楽は、フェリーニ映画といえば、この人、ニーノ・ロータ。あの、ジェルソミーナの「道」、それと「太陽がいっぱい」。「ゴッドファーザー」の映画音楽もニーノ・ロータでした。
「甘い生活」では、ぼくはフランス的エスプリを感じさせる(?)アヌーク・エーメより、これぞ雌属といった顔とボディのアニタ・エクバーグがお好み(といっても、老いた彼女の表情の恐さといったら……ブルブルモノです)。
ところで、じつは、これから始まる、ぼくの「甘い生活」は、この映画とはまったく関係がない。文字どおり「甘い」
「艶ごともそれなりに経験し、世間智を身につけた大人」のことを「
若いころから酒とは存分にお付き合いしてきたためもあってか、甘いものは無意識に遠ざけていたような気がする。お酒を飲む前に甘いものを口にしたら、どんな銘酒もアウトですものねぇ。お酒に失礼でしょう。
ところが、あれは三十代もなかばの頃だったでしょうか、神田・連雀町(新しい地番では淡路町何丁目とか言うでしょうか)の、先日、火事になってしまった!「かんだ・やぶそば」の座敷にあがり、若き悪友編集者たちと“板わさ”とか“そば寿司”をつまみに銚子を何本か空けながらダベっていると、隣りのテーブルの、そう年の頃は七十五は過ぎたかな、白髪で血色のいい、いわゆる艶福家的な風体の紳士が、こちらに声をかけてきた。紳士の前には奥さん? いや違うかな、ま、どちらでもいい、六十すぎの、品のいい、落ち着いた感じの婦人が座っている。
で、その紳士が「あなたたち、よく飲みますなぁ、このあと、どこへ行くんですか?」というご下問。
一瞬、こちらは「え?」と思った。いきなり「このあと、どこへ?」と聞かれてもねぇ。しかし、一呼吸のあと「ま、この近くの居酒屋にでも移動でしょうかね」と受け流すと、
(日本酒を飲んだ、すぐあとに甘いものですかぁ)と思ったが、紳士と婦人のよき人品骨柄の印象もあってか、なにか飲食の奥儀の一端を知らされたような気がして、二人が店を出てしばらくして「このあと、その店へ行ってみるか」ということになった。

◉ 歴史的建造物に指定されている美しい木造建築の「竹むら」。外には季節がら「氷しるこ」の札が。

◉ つい定番の白玉あんみつを注文してしまった。
で、その揚げまんじゅうで有名な美しい木造建築の「竹むら」へ行くと、例のお二人がまだ座敷にいて、「おう、いらしたか、感心、感心」と笑顔で出迎えてくれた。思えば……これが、我が「甘い生活」へのきっかけだったのかも。
妙に大人の左党ぶって、「甘いもの? 真っ平ごめんこうむる! 酒飲みが甘いものなど喰えるか!」などという、男性的ポーズから自由になれるようになったのかもしれない。
もともと、「甘いもの」は「美味しいもの」だったのではないか。
「甘い」は「美味しい」。子供の頃を思い出せば腑に落ちる。
駄菓子屋へ親からせしめた5円とか10円玉を握りしめて、駆けつけ、店先で必死にあれこれ迷った末に買った、ゼリーや水あめの、あの美味さったら! 幸せ一杯で、体の芯から、「甘めーっ」「うめーっ」叫びたいくらいの気持ちだった。
時は流れて、バブルの前後、ぼくもはや中年に達していた。多少自由になる小遣いがポケットの中にあるような状況になると、
ちょうどそのころ、グルメブームとやらが到来、日本にも、そこそこまともな店ができはじめていた。シェフの名で客が呼べるような店である。ワインを飲みつつコースを食べ、最後にデザート。このデザートの味を楽しむようになった。
さらには、デザートのレベルで、その店の料理全体を評価するようになった。ナマイキである。ほんと少し前までは、フランス料理といったって舌平目のムニエルとかポトフ。イタリア料理? ピザかスパゲティ、あと、せいぜいラザニアぐらい(すべてパスタではないか!)しか思い浮かばなかったのに。
なにがデザート、なにがドルチェか。ましてや、あの店のパティシエは、どうのこうのだと!? 笑止千万! 我ながらグルメ的一夜漬け力をマスターしたものである。
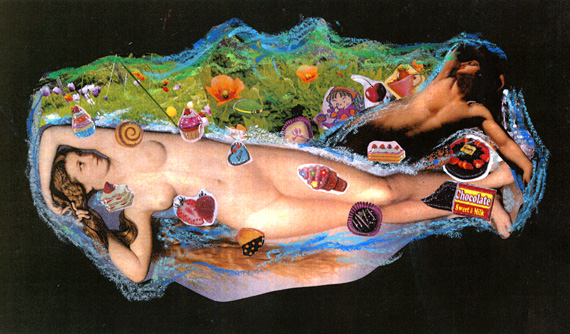
「Sweets Memories」コラージュ:安土利夫
となると事の次第は洋食系・西洋菓子系だけということではなくなる。西にどこそこの“きんつば”が美味と聞けば入手し、東にどこそこの“ドラヤキ”が
“最中”だって、あれこれ食べくらべた。最中に関しては、もちろん餡の歯ごたえと香りは当然重要だが、ぼくは皮の香りと歯ごたえ、これも重視したい。いい最中の、それも、できたばかりホヤホヤの最中をハクッと噛んで口に入れると……、その瞬間だけは、この憂き世を忘れてしまえる。羽化登仙の気分になれるのだった。
この「甘い生活」のブログでの連載は、ぼく自身の中ではすでに数年ほど前から、また具体的な打ち合わせをしてスタートを依頼されてから半年が経過したのだが、なぜか第一歩が踏みだせなかった。 と、いうのも、(いまさら、ただのスイーツ記事を書いても意味がないな、と思ったり、洋中心でいくか、和の伝統菓子はどうする? 世に何百、何千とある甘いものから、なにを選び味わい紹介するか? その基準は?
あるいはまた、これまでに出た甘いもの本も連載開始前に少しはフォローしなければ)などなどとウロウロしていたのである。
ところで、先週末、他のブログ(文源庫の「Web遊歩人」)で随時連載している歳時記の周辺を訪ねる「季語道楽」の件で、柳橋の老舗甘味屋「にんきや」で季節がら久しぶりに“白玉あんみつ”でも食べようかと思った。
連続の真夏日とかで気候35℃、太陽がいやがらせのようにヂリヂリと照りつける。電車に乗ってから(まてよ)と思った。この暑い中、浅草橋駅から柳橋近くの店まで行って、「休業」とかだったら目も当てられない。(そうそう、電話で確認してから行こう)と思いついた。最近はスマホを使いこなしているのだ。
で、検索したら、想定外なことが! 休業どころか、しばらく前に閉店してしまっているではないか!
あの安藤鶴夫さんもごひいきだった店。
柳橋だから、かつての花柳界。花柳界には芸者がいる。芸者がいれば半玉もふくめ、甘いものに人気がある。この「にんきや」も、その昔は天秤で町内を売り歩いていたという。明治・大正風物の雰囲気ですね。
その「にんきや」が忽然と消えた。花柳界・柳橋の記憶をからくもとどめる老舗だったのに。
遅かった油断があった、甘かった。
いや、甘くはなかった、白玉あんみつ食べられなかったのだから。
で、このあとぼくのとった行動は──。気分はリベンジ。急遽、コースを少し変え、御茶ノ水へ。駅から5分、神田明神だ。大鳥居のすぐ脇、名店・甘ざけの天野屋。炎天でも5分くらいなら歩ける。甘酒は本来、夏の季語で熱いのを飲むのが常道なのだが、少し汗をかいたあとの、この店の“冷し甘酒”がいい。心も体もホッとする。昔懐かしい小ぎれいな古物商のような店内から眺める中庭の風情がいい。冷し甘酒のグラスも涼しい(この店には“氷甘酒”もあります。冷しは450円、氷は500円だったかな)。

◉ 甘酒の「天野屋」

◉ 涼しげなグラスに冷たい甘酒。添えられたこうじ味噌は売店で買える。◉ 小さな庭も心地よい。
とにかく「にんきや」の閉店がぼくの気持ちにスイッチを入れたようだ。「風たちぬ、いざ始めやも」。グダグダ考えているんじゃなくて、ともかく幕を開けねば。和でも洋でもいい、新しい人気のスイーツもよければ創業・文政○○年の菓子でもいい、とにかく(年甲斐もなく)「甘い生活」、の体感報告をスタートせねば。さて、どの店のなにから始めるか──。やっぱり、これまでシゲモリ先生ご愛顧の、勝手知ったる甘いものから始めよう。
銀座か。と、すると先日夕方4時少し前に行ったら、案の定というか、すでに売り切れで、麗しい店員さんに「何時までに来たらあるの?」と愚痴めいたことを言ってしまった「和光」のケーキショップのカヌレ・ド・ボルドー。まずは、これを入手してから、その足で、あのスペインバーに寄って……。
よし、銀座からスタートしよう。年甲斐もなく? いやいや、少しは「女の都」(つまり甘いもの屋)にも出入りし、彼女らと、あれこれ飲んだり食べたりしてこの歳になったからこその「甘い生活」だ。次回は、銀座で「甘い生活」。
(第1回おわり)