第10話 二度と帰らぬ青春の日々――旧雨社のこと
東京は上野、不忍池。
春には桜が霞のように咲き誇り、夏には玉のような蓮の花が水面を彩る。晩秋、吹き始めた木枯らしに桜の紅葉が散りゆく中、破れ蓮をぼんやり眺めつつ歩くのも、それはそれで風流なものだ。
この池の真ん中に、小さな島が浮かんでいる。弁天島である。琵琶湖の竹生島にならって弁財天が祀られたこの小島からは、不忍池の全体を眺め渡すことができる。ちょっとしたビュー・スポットなのである。
江戸の昔から、この島で休憩を楽しむ行楽客は多かったらしい。『江戸名所図会』を見ると、島の周りにびっしりと、小屋が立ち並んでいることがわかる。実際の弁天島は絵で見るよりはだいぶ狭く、これほどの建物が密集できるとは思えないが、それは名所図会らしい誇張なのだろう。
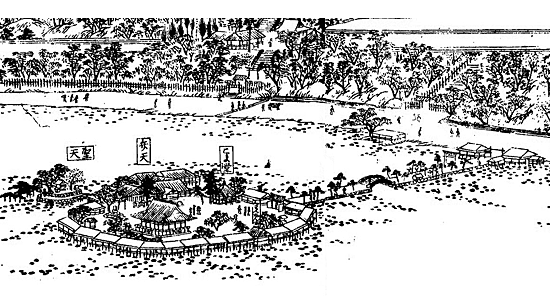
その理由について、荷風は「これは主人
さて、1873(明治6)年ごろのこと、毎月15日になるとこの三河屋に集まって酒宴を開く、風流韻士の一団があった。不忍池の景色をほしいままにしつつ、酒を飲んでは、自作の漢詩漢文を読み合って、一時の歓楽を尽くすのである。その名を、「
この会合の発起人は、四国は松山の人、藤野
藤野は、幕末の騒乱の際、親藩であったために難しい立場に立たされた松山藩をうまく舵取りし、明治の新時代へとソフトランディングさせた、傑物である。維新後は、東京府に出仕したり、新政府の修史局で歴史書編纂に携わったりした。
そんな彼は、20代のころ、故郷を離れ江戸に出て、
たとえば、荷風の母方の祖父で、『下谷叢話』の主人公、漢詩人として知られる鷲津
寮で寝起きを共にした彼らは、漢籍の読解や漢詩文の執筆に切瑳琢磨し、それぞれの才能を磨いていった。時は
それから、いろいろなことがあった。黒船来航から大政奉還、戊辰戦争を経て廃藩置県に至る時勢の奔流を泳ぎ切った藤野は、今、40代の半ば、老いの入り口に立っている。振り返ってみれば、昌平黌で学んだあのころが、たとえようもなくなつかしい。
そこで、かつての学友たちに声をかけ、漢詩文の会を催すことにしたのである。
では、その会の名称「旧雨社」には、どんな由来があるのだろうか。
中国文学の歴史に不滅の攻防を放ち続けている詩聖、杜甫。しかし、彼の実人生は、苦難の連続であった。
20代のころは、よかった。官僚になるための科挙の試験にいっぺん落第したくらいは、なんでもなかった。30代も、最初のうちは楽しかった。才能を磨くために全国を旅し、李白を初めとする多くの詩人たちと交友を結んだのだから。
しかし、生活の後ろ盾だった父が亡くなると、状況は一変した。杜甫は長安の都に滞在して就職活動をするが、一向に成果は出ない。妻子をかかえて、日々の暮らしは困窮するばかりであった。
そして、751年、杜甫は数え年で40になった。この年の秋は天候不順で雨が多く、彼は体調を崩して寝込んでしまう。そのとき、見舞いに来てくれた友人に対して、杜甫は「
それによれば、この時は湿気のあまり、本には
「旧雨来たり、
昔は雨が来たが今は雨が来ない、というわけだが、しかし、たった今、雨降りばかりだと嘆いてみせたばかりだ。これでは文脈が通じない。
実は、この「雨」は、掛けことばなのだという。当時の中国語では「雨」と「友」とは発音が似ていた。ちなみに、現在の北京語の発音をローマ字で記せば、「雨」はyuで、「友」はyouとなる。そこで、この一文は、「
若いころ、無神経なほどに親しく付き合ったあの友人たちが、なつかしい。体調のすぐれぬ杜甫は、降り続く雨を眺めながら、その思いをかみしめたことだろう。あのころにはもうけっして戻ることはできないのだ……。
ここから、昔の友と今の友を指す「旧雨今雨」ということばが生まれた。それは、杜甫のこの思いが、多くの人々の共感を呼んだからに違いない。でなければ、詩聖、杜甫の作品群の中ではさして有名でもないこの文章から四字熟語が生まれ出ることなど、なかったのではなかろうか。
その共感は、明治の日本にも受け継がれた。藤野正啓たちの「旧雨社」という名前も、杜甫のこの文章に基づいているのである。
幕末維新の激動の時代を生き抜き、ようやく老いを迎えつつあった人々にとって、江戸の華やかなりし青春の日々がとりわけなつかしいものであったことは、よく理解できよう。だからこそ、彼らは月に一度、不忍池の三河屋に集まったのだ。
ただ、藤野にとっては、「旧雨」への思いはまた格別なものがあったようだ。なぜならば、彼の青春であった江戸遊学は、ある日突然、断ち切られてしまったからである。
藤野が晩年になって記した「海南手記」という自伝が、その遺稿集『海南遺稿』に納められている。この自伝、もちろん漢文で書かれているのだが、その中に、次のような話がある。
1850(嘉永3)年の5月9日のこと。藤野は、三田にある松山藩の中屋敷から呼び出しを受けた。行ってみると、藩主の跡継ぎから、海防策について考えるところを文章に記して差し出せ、とのご下問である。自分の文才がお耳に達したに違いない。若い藤野は、その感激に打ち震えながら、中屋敷を後にした。
帰途、彼は、日比谷の肥前佐賀藩上屋敷を訪ねた。かつて昌平黌の同じ寮にいた友人が、ここで学問を教えているのである。友人は温かく藤野を迎え、酒を飲みながら自分の教え子たちに藤野を紹介し、彼の才能を褒めそやした。お世継ぎの目に留まり、友人からもヨイショされる。藤野がいい気分になったのも、無理もなかろう。
加えて、この日は彼の誕生日でもあった。いやが上にも、杯は進む。いったい、何杯飲んだかわからない。泥酔した藤野は、佐賀藩上屋敷を出た。そうして、そのまま記憶を失ったのである。
目が覚めたとき、彼は、地べたに座らされ、柱に縛りつけられていた。見張りの者に理由を尋ねると、乱暴狼藉を働いたからだという答え。藤野は、越前福井藩の上屋敷で、囚われの身となっていたのである。
やがて、上役らしき人物がやってきた。その武士は藤野の酔いが醒めたのを確認すると、縄を解き、座敷へと上がらせた。そして、昨夜の彼の行状を語ってくれたのである。
それによれば、泥酔した藤野は、刀を振り回して犬を追いかけながら、福井藩上屋敷の前を通りかかったという。見かねた門番が刀を納めろと言ったが、ますます暴れ回るばかり。そこで、数人がかりで取り押さえたのだった。
そう言われて着物を見ると、血まみれになっている。額には、二寸ばかりの傷もある。それに気づいたとき、藤野はおぼろげに、昨夜のできごとを思い出したのだった。
なんということだろう。得意の絶頂にあったその夜に、このような失態をしでかすとは。
彼はとりあえず、汚れた着物を着がえようと、昌平黌の寮へと使いを走らせた。すぐに駆けつけてくれたのは、親友の重野安繹たちであった。藤野は事の顚末を語り、友人たちに次のように問いかけた。
「
酔って狼藉を働いただけでも、武士の名を汚す行為だ。まして、縁もゆかりもない他藩に迷惑をかけ、自藩の名に傷を付けたのだ。場合によっては腹を切らねばならない。そう覚悟していた藤野に向かって、重野たちは答えた。
「何ぞ必ずしも死を
昨晩、帰寮しなかったことは、俺たちが何とか取り繕おう。病気で休んでいることにするから、傷が治ってから戻って来ればよい。だから、死ぬ必要なんてない、と。
失態を咎めもせず、親身になって力を貸してくれる友に、藤野はどれだけ感謝したことだろう。
しかし、藤野の失態は、すでに藩主の耳にも達していた。三田の松山藩邸に身柄を移された藤野は、その夜、帰郷を命じられた。だが、彼は数日の猶予を申し出る。世継ぎから命じられた海防に関する論文を、書き上げるためである。
いよいよ江戸を発つそのときの藤野の心中は、いかばかりのものだったろう。身から出た錆とはいえ、自分の青春がこんなにも突然に、あっけなく終わってしまったことに、茫然としていたに違いない。
江戸の友人たちとも、もう二度と、顔を合わせることはあるまい。
旧暦の5月といえば、梅雨の季節だ。そのとき、藤野の上に雨が降り注いでいたとすれば、彼は杜甫の「旧雨今雨」を思い出していたかもしれない。
それから四半世紀が過ぎた。奇しくも時代の奔流が、藤野に名誉挽回のチャンスを与えた。運命は、もう二度と見ることはあるまいと思っていた江戸へと彼を導き、今は「東京」と名を変えたその街で、藤野は暮らしている。
重野安繹や鷲津宣光を始め、多くの友人たちとの再会も果たした。彼らと漢詩文の会を催すことは、藤野にとって、自らの失態によって打ち切られた青春を取り戻す、という意味を持っていたことだろう。
ただ、そんな藤野正啓が酒に懲りた形跡は、まったくない。独酌のときは日に5〜6合、客人があればその倍、飲みに出掛ければさらに倍は飲んだ、と例の自伝にある。
旧雨社については、そのメンバーたちを一人ひとり紹介した『旧雨社伝』という文章が残されている。その藤野の項は、おそらく、親友の重野安繹の筆になる。それによれば、藤野は相変わらず、泥酔することがあったらしい。不忍池からの帰り道、会合で集めたみなの詩文の原稿を、道端でなくしてしまったことがあったという。
「同社、伝えて以て笑いと
大事な原稿を無くされても、笑って済ませるとは。本気で許していたのか、それともあきれ果てていたのか。
いずれにせよ、いかにも互いの青春を知る友らしい対応である。
