第1話 天から降ってくるもの――雨と漢字のなりたち
雨の中を出かけるのは、イヤなものだ。
靴の中にまで雨水がしみこんできたときの、あのぐちゃぐちゃした感触。風に傘を取られてしまったときの、あのぶざまな格好。通りすがりのトラックにたまり水でも引っ掛けられようものなら、もう、やりきれない気分になってしまう。
一方で、部屋の中で雨だれの音を聞いているのは、心地がいい。ガラス窓の向こうに降る雨をぼんやりと眺めているのも、気持ちが安らぐ。窓を開けて風に混じる雨の匂いを吸い込んでみるなんていうのも、なかなかオツなものだろう。
要は、自分さえ濡れなければいいわけだから、相当に自分勝手なのだ。
そんな自分勝手な態度で、雨にまつわるよしなしごとを、適当に書き綴っていこうと思う。ぼくは自称「漢和辞典編集者」なので、題材にするのは、雨に関する漢字や、雨が描かれた漢詩や漢文などである。
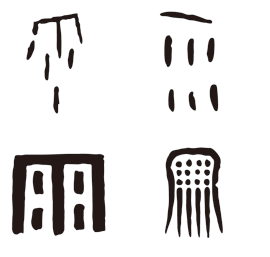 よく知られているように、漢字の原点は、絵であった。さかなの絵が「魚」となり、ウマの絵が「馬」となった、という具合に。
よく知られているように、漢字の原点は、絵であった。さかなの絵が「魚」となり、ウマの絵が「馬」となった、という具合に。そういう目で眺めてみると、「雨」という漢字の4つの点々が雨だれを描いたものであることは、容易に想像がつく。では、それ以外の部分は、いったい何を表しているのだろう。
真ん中に縦棒が通っているから、傘なのかな、と考えてみる。しかし、傘の内側に雨だれが降り込んでいては、用をなさない。とすれば、窓の外に雨が降っている情景か。漢字を生み出した古代中国の人びとも、雨に濡れるのがイヤだったのだろうか。
紀元100年ごろに書かれたという『
その「雨」のところには、次のように書いてある。
「水の雲より下るなり。『一』は天に
「象」という漢字には、形を写すとか、描くとかいう意味があり、その場合には「かたどる」と訓読みする。『説文解字』によれば、「雨」とは、水が雲から落ちてくるという意味であり、「一」の部分は天を描いたもの、「冂」は雲の絵なのだ。
あれっ、縦棒はどこに行ってしまったの? と思いはするけれど、相手はなにしろ1900年も前の文献なのだから、細かいことは気にしない方がいい。実際、甲骨文字だとか金文だとかいういわゆる古代文字を見ると、図のようにいろんな形がある。右下のように、えらく威勢のよさそうな「雨」の字だってあるのだ。
なんにしろ、「雨」の4つの点は雨だれの絵であり、それ以外の部分は、空なり雲なりを表しているのだろう。
はるかなる天から降り落ちてくる水滴。漢字を創った人びとは、その壮大なイメージを「雨」の1文字に込めたのである。
さて、「雨」という漢字の意味は、何だろうか?
改めてそんな質問を投げかけてみるのは、漢字には、1文字でいろいろな意味を表すものが多いからだ。たとえば、「雪」は、「ゆき」以外に、「汚れをすすぐ」という意味も持っている。「雪辱」がその例である。
そこで「雨」についても意味が気になるのだが、辞書を調べてみても、まあ、「あめ」以外の意味は見当たらない。比喩的な意味がないではないが、「雨」は、「あめ」一筋の漢字だと言っていいのだ。
ただ、漢文ではちょっと変わった使い方をすることがある。たとえば、
「天久不雨(天候はというと、長い間雨が降らない)」
というような文。この場合の「雨」は、「雨が降る」という動詞として使われている。だから、漢文訓読では、この文を、
「天、久しく雨ふらず」
と読む。「雨」1文字で、「あめふる」と訓読みするのである。
「雨」を動詞として使うなんて! と思われるかもしれないが、これ自体は、それほど驚くことではない。英語のrainだって、名詞にも動詞にもなる。日本語のように、名詞と動詞の形がはっきり異なる方が、めずらしいのだ。
ただ、次のような例を見ると、ちょっとびっくりするかもしれない。
「天大雨雪」
この場合の「雨」は、「雪が降る」という意味で使われている。そこで、訓読では、
「天、大いに
と読む。同様に、「大雨雹」という表現もあって、こちらは「大いに
「雨」は、もっと意外なものを降らせることもある。『漢書』という歴史書には、紀元前17年、信都という町で「雨魚」、つまり、魚が天から降ってきた、という記録がある。竜巻か何かで、巻き上げられたのだろうか。
また、司馬遷の『史記』には、紀元前367年、
それだけではない。『後漢書』という歴史書によれば、紀元後149年、北地の
つまり、動詞としての漢字「雨」は、天から降ってくるものであれば、何に対しても使うことができるのだ。超自然現象だってカバーしてしまうのである。
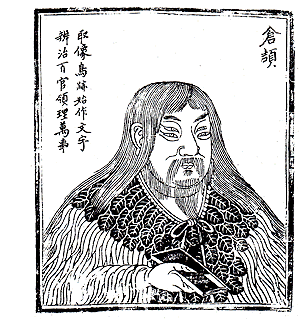 そんな超自然現象の中には、漢字の誕生にまつわるエピソードも含まれている。
そんな超自然現象の中には、漢字の誕生にまつわるエピソードも含まれている。漢字がいつごろ誕生したのかは、歴史の闇のその奥のできごとだ。ただ、伝説としては、漢字を発明したのは
蒼頡は、目が4つもあったという、常人を超える眼力を持ち合わせた賢者であった。彼はあるとき、動物の足跡を見ていて、その形からどんな種類の動物のものか区別できることに気づいた。そこにヒントを得て、初めて漢字を創り出したのだという。
そのとき、超自然現象が起こったというのだ。紀元前2世紀ごろに書かれた『
「昔、蒼頡、書を作りて、天は
「粟」は、アワを代表とする穀物のこと。蒼頡が漢字を発明すると、空からアワが降ってきた。ここでは、それを表すのに、漢字「雨」を用いているのである。
それにしても、なぜこんな超自然現象が起こったのか。
『淮南子』の注によると、幽鬼たちが夜、声を上げて泣いた理由は、こうである。
文字が発明されると、知識の世界が拡大する。そこで、幽鬼たちは居場所がなくなるのを恐れたのだ、と。これは、文字の発明の正の側面を表したものだといえるだろう。
一方、同じ注によれば、天が穀物を降らせた理由は、次のようになる。
文字を使えば、偽りをも書き記すことができる。人びとはその偽りに心を奪われ、農業をおろそかにするようになる。そこで、天はやがて食糧不足が生じることを知り、穀物を降らせたのだ……。
こちらは、文字の負の側面である。『淮南子』が伝える伝説の中で、文字がもたらすマイナスの方がプラスよりも先に描かれていることは、なにやら意味ありげにも思われる。
ただ、それはそれとして、ぼくが気になるのは、やはり、「雨」の1文字である。天はなぜ、穀物を天から降らせなくてはいけなかったのだろうか。
食糧不足を心配してくれるのならば、穀物を豊かに実らせてくれれば、それで十分だ。いっそのこと、毎年毎年、豊作を約束してくれたら、なおのことありがたい。天からアワ粒が降ってくるなんて、奇抜なことをしてくれなくったっていいのだ。
だとすれば、この奇抜な方法自体も、天の意思表示だったと考えるべきだろう。
雨は、広い地域にまんべんなく降る。富める者の上にも貧しき者の上にも、平等に降り注ぐのである。
また、雨は一過性のものだ。よく言われるように、やまない雨はない。
文字の発明は、偽りの発明でもあった。蒼頡は、パンドラの箱を開けたのだ。これから先、人びとは、偽りのはびこる世界を生きていかねばならぬ。その中で、強き者と弱き者が生まれ、欲望と欺瞞に満ちた幾多もの歴史が、くり返されることだろう。
その悲しい旅立ちの日に、天は、あらゆる人びとに一回きりの餞別を贈った。それが、天から降ってくるアワ粒だったのではなかろうか。
それきり、人びとは、天に見捨てられてしまったのかもしれない。
