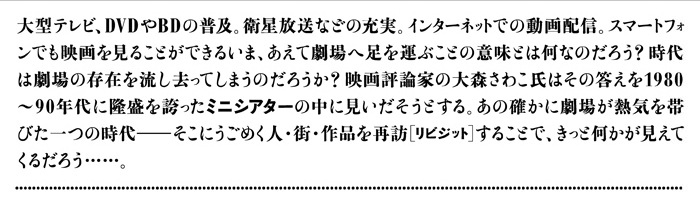かつて東京・六本木にあったビル、WAVEのことをどれくらいの人が覚えているのだろう。オープンしたのは1983年11月18日で、99年まで16年間、営業していた。住所は六本木6丁目2-27。
閉館から14年後の2013年3月。かつての場所を確認したくて、デジカメ片手に付近を歩いてみたが、様子が変わってしまい、跡地を特定できない。資料に「麻布警察署の近く」と書いたあったことを思い出し、今も変わらず立っている警察署に住所を調べてもらう。
「27という住所は今の地図にはないですね。2番地のあたりは六本木ヒルズに吸収されてしまったようです」
消えてしまった20世紀の遺跡探しは容易ではない。やがて六本木ヒルズのビルのひとつに「6-2-31」とプレートが打たれていることに気づく。至近距離にいるのは間違いないので、周辺をうろつきながら、ファインダーをのぞく。
撮影していると、ひと目で観光客と分かる団体や老夫婦、ベビーカーをかかえた母親の姿も飛び込んできて、時代の流れを実感する。WAVEの周辺にいた最先端のカルチャー好きの若者たちとは違う層だ。
WAVEの跡地には、現在の六本木のシンボルとなった巨大ビル群、六本木ヒルズがそびえ立ち、今では新しい観光地になっている。
現実の街には記憶を呼び起こすものが、もはや存在していないことに気づき、古い新聞記事をたどり直してみる。1983年11月18日の『朝日新聞』には一面の3分の2を使った大きな広告が出ていた。
「今日11:00am.オープン。音と映像の新しい空間、WAVE。ROPPONGI・SEIBU」
広告文を引用すると――「ウェイヴは、まったく新しい考えで創られた音と映像のための空間です。〔中略〕ウェイヴはさまざまな音と映像の情報を発進〔ママ〕する都市の基地です。同時に都市のひとびとが、自分の波長を創る〔ための〕静かな波止場です」(※〔 〕は編注)
このビルは7階建てで、3つのパートに分かれていた。地下1階がミニシアターのシネ・ヴィヴァン・六本木、1階から4階が世界中の音楽を集めたレコードショップのディスクポート、5階から7階が録音やコンピューター・グラフィックスのためのスタジオである。
新聞の「東京23区」面には「音と映像の殿堂オープン」の記事があり、「目を引く異色の外観」との見出しが打たれている。
「ダークグレー、窓のないブラックボックスのようなビルは、きらびやかな六本木の街に溶け込むか。〔中略〕『暴力的な音、ネオンのはんらんを吸収して存在感を主張した』とか」
こうして時の向こう側から、かつての建物の姿が浮かび上がる。
そのダーググレイのビルには異物感があった。高級クラブやおしゃれなカフェバー、ディスコなど風俗系の店が多かった六本木に、それは突如として出現した知的なカルチャー・ビルで、宇宙からやってきた不思議な物体に思えたものだ。とりすました雰囲気もあり、最初は近寄りがたいが、いったん中に入るとクセになる不思議な魔力も持っていた。
近年の複合ビルの場合、ファッションや食が中心だが、WAVEはあくまでも音と映像だけが売りのカルチャー・ビルで、こういう知的なイメージだけで統一したビルは、その頃、他になかった。


◉1983年11月18日の『朝日新聞』朝刊(東京版)に掲載されたWAVEオープンの10段広告(縮刷版コピー)
◉同じ『朝日新聞』の東京23区面に掲載された記事。
キャプションには「音と映像を売る『WAVE』ビル」と書かれている
◉同じ『朝日新聞』の東京23区面に掲載された記事。
キャプションには「音と映像を売る『WAVE』ビル」と書かれている
作ったのは西武流通グループ(のちのセゾングループ)で、当時の西武は文化事業に力を入れることで企業全体のイメージアップをはかり、文化的にも貢献していた。本拠地の池袋の西武デパートにセゾン美術館や多目的ホール、スタジオ200があり、他では実現できなかったイベントも行われていた。また、80年代にスタートした西武系の出版社、リブロポートではデザインや紙に凝った豪華な美術関係の本が次々に出版された(私も90年代にここから映画の翻訳本を出版した)。
当時の西武の勢いは遂に映画界にもおよび、84年には映画の配給会社、シネセゾンもスタートさせるが、その前年に六本木に作られたのがWAVEの中のシネ・ヴィヴァン・六本木だったというわけだ。
『パッション』は自分にとっての“理想の光”を探し求める映画監督が主人公で、彼は美術の名画を映画の中で生身の人間を使って再現しようとする。ドラクロワの「民衆を導く自由の女神」、レンブラントの「夜警」、ゴヤの「裸のマハ」などのイメージが劇中では次々に再現され、その映像の美しさにまずはひきつけられる。イザベル・ユペールやハンナ・シグラらが、監督の思いを託すヒロインとして登場するが、他のゴダール作品同様、ストーリーはあいまいで、主人公たちの観念的な会話のやりとりが写されていく(「物語は作る前に生きるものだ」「影は存在しない。光の反映でしかない」といったセリフが登場する)。そして、バックに流れるクラシック音楽の数々が、時にはセリフ以上に意味を持つ。ラヴェルやフォーレ、ベートーヴェン、モーツァルトなどの名曲に彩られた映画でもある。
絵画とクラシックの名曲が重要な要素となった先鋭的な作風の映画。そんな『パッション』の個性は、WAVEというカルチャー・ビルのコンセプト=“音と映像の新しい空間“にぴったりだった。
ゴダール作品以外にも、アンドレイ・タルコフスキー(『ノスタルジア』〈83〉)やテオ・アンゲロプロス(『シテール島への船出』〈83〉)など、映像詩人と呼ぶのがふさわしい、知的で、哲学的な作風の監督たちの映画が次々に上映され、この映画館の先鋭的な個性を作り上げていく。
異色作ともいえるのがフランシス・コッポラが製作にかかわったドキュメンタリー『コヤニスカッティ』(82、ゴッドフリー・レジオ監督、配給=ヘラルド・エース)で、この作品は『パッション』に続いて、劇場2本目の公開作となった。アメリカの大都市のビルやモニュメントバレーなどの自然の映像に現代音楽の鬼才、フィリップ・グラスの壮大な曲が重なり、観客は不思議な音と映像の体験に身をゆだねることになる。これも、また、WAVEのコンセプトに合う作品だった(劇場には最新式の音響設備も備わっていた)。
『コヤニスカッティ』はPARCOの広告でも知られた石岡瑛子がポスターのアートワークを担当していた。彼女はコッポラ監督の『地獄の黙示録』(79)の日本版のポスターも手がけていて、コッポラ経由でレジオ監督と知り合い、『コヤニスカッティ』の日本での公開に力をつくしたようだ。
当時のプログラムで「私は、この映画を日本の人たち、特に若い人たちに、見てもらいたいと直感的に感じました。日本では、視覚言語・視覚伝達というものの効力がじゅうぶんでないでしょう。〔中略〕特殊な映画は、実験映画とか前衛映画というふうにカテゴライズされてしまって、マイナーな形でしか上映されない。そういう日本の状況の中にこの映画を投げ込んでみたいという気持ちが働いたのです。〔中略〕私が日本ヘラルド映画に働きかけて、結果としてこのように、シネ・ヴィヴァンで上映することにこぎつけたわけです」と語っている。
商業ルートに乗りにくかった映画を公開していくという劇場の方向性は、81年にオープンしたシネマスクエアとうきゅうとも似ているが、WAVEというビルのイメージにそって、サウンドや映像が際立つ作品にこだわる。それがシネ・ヴィヴァン・六本木のひとつの特徴だった。
音楽ファンには1階から4階までのレコードショップ、ディスクポートも魅力的だった。窓がないビルで外が見えないせいか、妙に集中力が発揮できて、1度入ったら、なかなか出る気になれない。輸入レコードが本当に充実していて、東京の他のレコードショップにないような貴重なアルバムも揃っていた(レコード袋も、モノトーンのビルの色に合わせて、グレーに黒のロゴだった)。
音楽関係者の間でも品ぞろえには定評があったようで、そこでレコードを買う有名ミュージシャンや音楽通の作家の姿を目撃したという話をたびたび聞いたことがある。
私もいろいろなレコードを買ったが、そのうちの1枚にモーズ・アリソンというアメリカの白人ブルースシンガーのアルバムがある。彼の曲「エヴリバディ・クライン・マーシー」を私の好きな別のミュージシャン(ボニー・レイット)が歌っていて、それの原曲がほしくて、ずうっと彼のアルバムを探していたが、遂にWAVEのレコードショップで見つけることができた。
そのアルバムは私の長年に渡る愛聴盤となっていて、昨年は80代で初来日を果たしたモーズ本人の生歌を東京のブルーノートで聴くこともできた。
「都市のひとびとが、そこで自分の波長を創る静かな波止場」というかつてのWAVEの広告コピーに嘘はなかったのかもしれない。
インターネットがなかった時代。そこは自分と“新しい文化”の出会いを約束してくれる場所だった――。

◉見た目では在りし日の姿を思い起こせないほど、変貌を遂げている。
正面にそびえているのは地上54階建ての六本木ヒルズ森タワー
正面にそびえているのは地上54階建ての六本木ヒルズ森タワー
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。