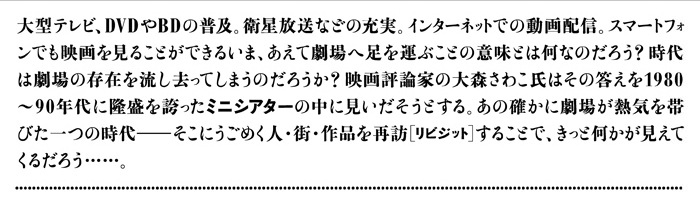2013年、2月。東京・新宿の繁華街、歌舞伎町にある映画街を訪ねようと思った。今の「シネマスクエアとうきゅう」を見るためだ。
もう、かなり長い間、この界隈には足を踏み入れていない。
平日の夕方、歌舞伎町に入り、まずは大きな変化に気づく。歌舞伎町のシンボル的な建物だった新宿コマ劇場が取り壊されている。
消えたのはコマ劇場だけではない。その隣にはロードショー館の新宿プラザがあった。スクリーンが巨大な映画館で、ハリウッド大作が似合う華やかな劇場だった。
しかし、コマ劇場同様、更地になっている。
通りを進んだ広場の周辺には複数の映画館が並んでいて、80年代は中央に噴水があったが、今は白い塀で覆われている。
かつてとは様変わりした歌舞伎町の劇場街。
ミラノ座が入ったビルの方に進み、「シネマスクエアとうきゅう」の文字が見える入口に行くと、やっとお目当ての劇場で上映されているポスターが目に入る。
その週はミュージカルの映画化『レ・ミゼラブル』がかけられ、次の週からオサマ・ビンラディンの事件に追った『ゼロ・ダーク・サーティ』が始まる。どちらもハリウッドの話題作だ。
こうしたポスターを見ると、かつての「シネマスクエアとうきゅう」とは変化したことが一目で分かる。こだわり系の作品だけを上映していた時代は終わってしまったようだ。
そんな劇場を見ながら、過ぎた年月の重さについて考える……。
映画会社、ヘラルド・エースの元宣伝部だった寺尾次郎さんは80年代の話を続け、「シネマスクエアとうきゅう」のミニシアターとしてのコンセプトについて語り始めた。
ヘラルド・エースの原正人社長は、その劇場に付加価値をつける必要があると考えていた。
「原社長は映画を上映する時、“何か特別な飾りをつけてあげなくては”と考えていたようです。この劇場の場合、“椅子を売りにしよう”という結論になり、エースのデザインルームのスタッフと話し合った結果、椅子をメインに据えたポスターを作ることになりました」
劇場に設置されることになった椅子はフランスのキネット社のもので、1席(当時で)7万円の価格。実は新橋駅前ビル1号館のヘラルド映画の試写室は、椅子が上質なことで知られていたので、座り心地にこだわったのだろう。その頃、東京の映画館の椅子は、今と比べ縦も横も幅が狭かったが、新劇場の椅子はゆったりと設計されている。
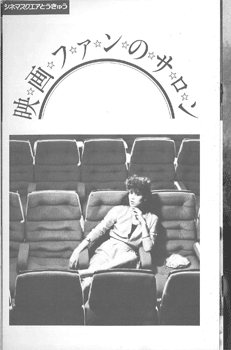
◉80年代ファッションに身を包んだ女性が、"ゴージャス感"満載で7万円の椅子に腰掛けている。
「シネマスクエア・マガジン」に収録された広告から
「シネマスクエア・マガジン」に収録された広告から
劇場の入場や鑑賞に関してもいくつかの制約が設けられることになった。従来の劇場は“流し込み”と呼ばれ、上映の途中で入り、そのままいることもできたが、新劇場では入れ替え制を実施した。さらに食事の持ち込みも禁止する。食べ物の音や途中入場に邪魔されないで映画に没頭できるよう配慮したルールで、その後、多くのミニシアターでも採用されるようになった(これに関しては批判もあったが)。
また、当時のロードショー館では客入りが悪い場合、1~2週間で打ち切られていたが、ここでは最低4週間は上映することになり、その作品の興行が週平均500万円を維持できる場合はかけ続けることになった。
「何週上映できるか、だいたい初日の成績で分かります。それで上映予定週を決めていたんですが、週平均500万円を目標にしていたのは、いい時代だったと思います。今だと1週間300万円がやっとではないでしょうかね」と寺尾さん。
椅子や入場方法、さらに興行形態など、あらゆる部分で従来とは異なるシステムを持ち込もうとしたが、作品の売り方も、大衆的なエンタテインメント作品とは異なる知的贅沢感を打ち出した。オープニング作品『ジェラシー』(79)では一風変わった連続広告を東京の情報誌『シティロード』に打つことになった。
同じタウン誌でもより大衆的だった『ぴあ』はどの作品もカタログ的な短い文章で紹介されていたが、『シティロード』は曲者のライターたちがこだわりと批評性の強い文章を書いていて、長文の作品評や取材記事を好んでいた。そんな雑誌の読者にアピールすることで、『ジェラシー』という作品、ひいては「シネマスクエアとうきゅう」の斬新なクオリティをアピールしようと考えたようだ。
81年の6月号から10月号まで連続広告が出たが、どれもカラーの大きな場面写真と800字ほどのコラム付きで、世紀末、ウィーン、音楽、美術、映画の5つの項目に分けて、映画の楽しみ方を伝えている。
「雑誌を開いてすぐのページをもらう、ということを条件に、5回で100万円に広告料をまけてもらいました。カラーポジの場面写真を50種類くらい用意してからデザインを決め、毎回、違う写真を出しました」

◉『シティロード』81年10月で表2対向面に掲載された『ジェラシー』の広告。
「その裂け目に男を引きずり込む女」のキャッチフレーズはあまりに印象的
「その裂け目に男を引きずり込む女」のキャッチフレーズはあまりに印象的
ポスターを作る時は作品の視覚芸術的な要素を強く打ち出すため、劇中に出てくるグスタフ・クリムトの絵画を生かすことにした。
「B全のポスターを作ることになりましたが、その時、“嫉妬は緑色の目の悪魔である”という『オセロ』からの言葉をアレンジしてキャッチコピーに使うことになり、画集で見つけたクリムトの絵の横に載せようと思ってデザイナーに渡しました。勝手に絵を引き伸ばし、まるでその絵をけがすかのように、場面写真を散りばめたポスターです。すごくいいかげんな時代で、版権のことなんて何も考えていませんでした(笑)。この映画がきっかけでクリムトの絵に興味を持ち、出張で訪ねたウィーンの美術館で本物を見ることができました」
寺尾さん同様、私もこの映画を通じてクリムトやエゴン・シーレの絵を知り、試写を見た後、伊勢丹美術館で開催中だったクリムトとシーレの絵画展に行った覚えがある。
映画を経由して新しい別のカルチャーと出会う。そんな楽しみ方を教えてくれる作品がミニシアターでは数多く上映されることになる。
「あの頃、文化の変わり目というか、これまでとは違うものが生まれつつあった時代かもしれません。映画の内容もそうですが、原稿を書くライターたちも、従来の古いタイプの映画評論家とは違う人たちが出て、自由な文章を書き始めていたし、雑誌も『ポパイ』や『ブルータス』のように、これまでなかった雑誌が注目されていました」
そういえば六本木の「俳優座シネマテン」では『ブルータス』のプロデュ―スによる“ブルータス座”という上映会(新作の試写や旧作の上映)も行われ、ひそかに人気を集めていた。人気雑誌と映画館が手を組んで定期的におすすめ作品を一晩だけ上映する。そんな状況も70年代には見られなかった傾向で、大手の商業館ではなく、パーソナルなミニシアターだからこそ実現できたのだろう(80年代、私も『ブルータス』で、時々、仕事をしていて、『さらば青春の光』(79)の上映を提案して採用していただけた時はうれしかった)。
81年には多目的スペース「PARCOスペースパート3」も誕生し、渋谷の先駆的なミニシアターとなったが、このスペースでの最初のイベントはルキノ・ヴィスコンティの衣装展と彼の映画祭だった。同じ場所を使って、衣装展と映画祭を行うという試みも大きなロードショー館では実現しなかった企画だ。
「俳優座シネマテン」「PARCOスペースパート3」「シネマスクエアとうきゅう」は、いずれもヘラルド・エースと縁があり、この会社の作品をよく上映していた。
実はエースの代表者の原社長は黒澤明監督の『乱』(85)の製作者で、製作・配給に関して多くの偉績を残した伝説的なプロデューサーであるが、そんな社長と運営側である東急レクリエーションの武舎忠一部長、堀江鈴男常務といったパイオニア・スピリットを持った人々が手を組むことで、その後のミニシアターの基礎となる「シネマスクエアとうきゅう」が誕生することになる。
「東急レクリエーションは大手企業ですが、そこに武舎部長のように太っ腹な方がいたからこそ、この劇場は生まれました。新米の宣伝マンだった僕にとっては、ひとつの劇場を立ち上げて、そこの作品を宣伝していくのが本当におもしろかった。『シネマスクエアとうきゅう』のコンセプトを守るため、他社が権利を持つ作品もエースが宣伝を担当しましたが、そうした会社の担当者からも特別な注文はなく、劇場の存在をおもしろがってもらえました。あの頃、マーケティングなんて言葉は誰も意識していなくて、自由に宣伝していました」
ちなみにワーナー・ブラザースの担当者は無類の映画好きで、その映画人生が『ロードショーが待ち遠しい/早川龍雄氏の華麗な映画宣伝術』(藤森益弘著、文藝春秋社刊)でも綴られた気骨のある早川龍雄さん、CIC(後のUIP)は知的で優雅な雰囲気の故・高橋美子さん、コロムビアはいつも元気な鹿野教子さん。洋画界では名物宣伝マンとして知られていた最強のメンバーたちが新劇場の窓口を担当していた。
劇場の個性を浸透させたのは宣伝だけではない。「シネマスクエア・マガジン」と題されたハンディなサイズの豪華なプログラムも作られたが、これも当時としては新しいスタイルだった。
劇場の番組選定委員を担当していたのは映画評論家の故・南俊子さんで、同じく映画評論家の小藤田千栄子さんの編集協力も得ることで、カラーの上質紙を多用した中身の濃いプログラムが毎回作られた。当時のパンフレットは縦30センチほどの大判のものが主流だったが、このマガジンはパリの情報誌「パリ・スコープ」を参考にして作られ、女性のハンドバッグに入るサイズ(縦22センチ、横15センチ)ということで考案された。

◉「シネマスクエア・マガジン」のバックナンバー一覧。
このような掲載のされ方自体、映画パンフレットとしては異例だった
このような掲載のされ方自体、映画パンフレットとしては異例だった
さらに「マガジン1」「マガジン2」と通し番号を打つことで、劇場の固定ファンを作ることにも貢献していた。ちなみにオープニング作品『ジェラシー』のプログラムには、先日亡くなった大島渚監督が「『ジェラシー』との奇縁」という文章を寄せている。実は大島監督の『戦場のメリークリスマス』(83)と『ジェラシー』はどちらもジェレミー・トーマスの製作作品だ(新人だった私はこのマガジンで3年ほど、シナリオ採録の仕事をいただいた。シナリオの要約の仕事で、ふだんは手にできないオリジナル・シナリオを読めるのがうれしかった)。
初代の堀江利行支配人は、寺尾さんによれば大の映画好きだったという。「シネマスクエア・マガジン」の記念すべき創刊号に掲載された寺尾さんらとの座談会の中で、支配人は拡大公開というシステムの弊害で、公開されない洋画が増えたことを嘆き、「(この劇場を作るにあたり)興行者側も、配給者側も、映画ファンの立場にかえって考えたわけです。六年前からの構想だったのですが、ようやく長年の夢が実現したという、今はその感慨にひたっているところです」と語っている。
関係者たちの熱意と情熱の結晶ともいえる革新的な劇場「シネマスクエアとうきゅう」。81年12月11日に『ジェラシー』でこけら落としを迎えるが、新劇場に対する話題もあってか、結果的には7週間上映の快挙となった(毎週、金曜日と土曜日にはレイトショーも行われた)。その後も、フランスの巨匠フランソワ・トリュフォー監督の『隣の女』(81、12週)、スペインのカルロス・サウラ監督の『カルメン』(83、15週)など数多くのヒット作が生まれていく。寺尾さんは当時を振り返る。
「僕自身が今も忘れられないのは、オープニングの『ジェラシー』。それと柳町光男監督の『さらば愛しき大地』(82)です。シネマスクエアで初めて上映された邦画で、当時の地方(茨城)の町の実態を映し出した作品として話題を呼びました。監督もすごくやる気がありましたし、実在のモデルがいるという映画の内容もリアルでした」
『さらば愛しき大地』は他の劇場では難色を示され、ここでの上映が決まったが、結果的には12週上映の大ヒットとなった。ヨーロッパやアメリカの埋もれた作品だけではなく、邦画の力作にも新劇場は救いの手を差し伸べた。86年には中国映画界の新しい才能、チェン・カイコー監督の『黄色い大地』(84)を上映し、アジアのアート系映画にも門戸を開くことになる。
世界中の埋もれた名作を発掘する革新的な映画館としてスタートした「シネマスクエアとうきゅう」。80年代初頭、そこに並んだ224席の椅子には新時代の夢と理想が託されていた――。

◉景気の後退と法律による規制の強化で、歌舞伎町の喧噪もバブル期と比べると翳りを見せている
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。