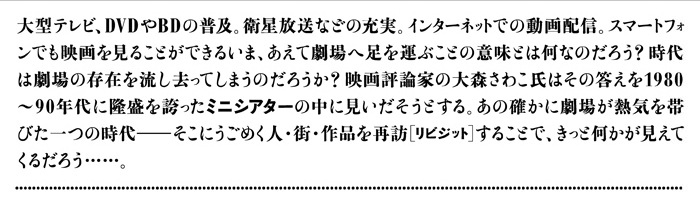数ある東京のミニシアターの中で、多くの映画関係者が〝特別な劇場〟としてあげるのが神保町の岩波ホールである。映画だけではなく、講座やコンサート、演劇などもかける多目的ホールとして産声を上げたのが1968年のこと。
74年からは映画の常設館となり、以後、40年間に渡って、商業主義に流されず、「いい映画を上映していく」という姿勢を貫き通している。オープンから20年~30年で閉館したミニシアターもけっこう多いが、そんな状況の中で岩波ホールは最高齢のミニシアターとなっている。
「もし、岩波ホールが渋谷にあったら、こんなに長く続かなかったかもしれないです」
ホールの歴史をそう振り返るのは約40年間に渡ってこの劇場の企画・宣伝を担当してきた原田健秀さんだ。確かに流行の移り変わりが激しい街、渋谷で、長い年月に渡って同じスタンスを保ち続けていくのは大変だ。
岩波ホールが問題意識の高い大人の観客のために良質の映画を送り続けることができたのも、神保町という立地条件に負うところが大きいだろう。ホールは千代田区神保町2丁目にあり、ビルが駅から続いているため、雨の日でもぬれずに行くことができる。
そして、映画が終わった後は書店まわりを楽しめる。三省堂や書泉グランデといった大型書店が至近距離にあるし、その周辺にはさまざまなジャンルの本を取りそろえた多くの古本屋が集まる。古い雑誌のバックナンバーをズラリと揃えた古書店もあり、こうした店にいると、まるで遠い過去に戻ったような気分になる。
書店だけではなく、大手の小学館や集英社、岩波書店などさまざまな出版社が集まった地域でもある。デジタル主流の現代において、紙の上に刷られた文字や絵の存在が神保町ほど今も誇らしく感じられる街は他にないだろう。
老舗の喫茶店やレストランなども残っていて、静かにつみ重ねられた時間の重みが心地よく思えるスペースと出会える。
「ただ、今はいろいろなもののサイクルが本当に速いですよね。神保町でもその店の主人が亡くなったりすることで、消えていく老舗の店が多いです。それでも他の場所より、まだいいのかもしれません」
原田さんは、毎朝、御茶ノ水駅から神保町まで古本屋をのぞきながら出勤する。今は本の値段が以前より安くなっていると感じる。
「100円でもかなり掘り出しものがあるんですよね」
買い手としてはうれしいことだが、よく考えれば本の価値が下がっているともいえるわけで、活字の街の住人にとっては複雑な思いもよぎるはずだ。
そんな原田さんが岩波ホールを初めて訪ねたのは1974年のこと。サタジット・レイの『大樹のうた』(58)を見るため、ビルに足を踏み入れた。
「できたばかりだったので、とてもきれいなホールだと思いました。当時の僕は日本中を放浪していて、山の中から出てきたようなかっこうでやってきたんですよ。まさにヒッピーでした。その後、人づてにこのホールの仕事を手伝わないかという話が来ました。岩波という名前には、その書店のイメージも重なり、アカデミズム的な印象が強かったので、サブカルチャー寄りの僕でいいのかなと思いつつも、軽い気持ちで入りました」
74年12月にアルバイトを始め、翌年、正式に社員となった。20代前半の原田さんの上司となったのが、岩波ホールの〝顔〟となる高野悦子総支配人である。
岩波ホールの岩波雄二郎社長は高野総支配人の義理の兄にあたり、フランスで映画製作を学んで帰国した彼女に完成したばかりのホールの企画作りを任せた。岩波社長の方針は「よいことなら何をやってもよい」で、高野総支配人は自由に企画を決めていったという(ホールは岩波書店とは別経営)。
68年のオープン当初は多目的ホールとして使われ、岩波書店主催の「岩波市民講座」やピアノやコーラスの発表会、演劇の上演なども行われた。
映画に関しては海外の短編映画の上映会やドイツやイタリア等、ヨーロッパの映画史の研究上映も実施され、後の岩波ホールに縁の深いアンジェイ・ワイダ、ルキノ・ヴィスコンティ、イングルマル・ベルイマン等の作品もすでに上映されている(いわゆるシネマ・クラブ的な活動を行っていた)。
映画の常設館となったのは74年からで、サタジット・レイの『大樹のうた』はその第1回目の作品だったのだ。
「この映画の上映に合わせて74年から〝エキプ・ド・シネマ〟もスタートしたんですが、その頃、高野は大きな責任を感じていて、とにかく、世界の名作を上映していこう、という動きがありました。その頃のスタッフたちは僕と同じように20代が中心で、みんなで夢中になって仕事に取り組みました。あの頃、家には仮眠のために戻っているような状況でした」
〝エキプ・ド・シネマ〟(映画の仲間)は当時の日本では上映されない世界の埋もれた名作を発掘する映画運動で、中心人物になったのが、高野総支配人と東宝東和の川喜多長政社長の夫人であり、フィルムライブラリーの専務理事でもあった川喜多かしこだった。
映画を愛するふたりの女性たちの手で結成された〝エキプ・ド・シネマ〟が岩波ホールの核となるが、その運動に合わせてホールでは一般の会員も募った(今も2年間、2000円の会費で、誰もが入れるシステムで、料金の割引などの特典がある。会員数は約3000人)。
それまでサタジット・レイの『大地のうた』(55)のような作品は、アート・シアター・ギルド(ATG)の配給によって日本でも陽の目を見ていた。ATGは川喜多かしこ(当時、東和映画の副社長)、森岩雄(当時、東和副社長)、井関種雄(当時、三和興行社長)の3人によって、61年11月に設立され、一般的な興行がむずかしいと思われる世界中のアート系作品を日本に輸入することで知られていた。
『大地のうた』はモノクロフィルムによって表現されたインドの庶民たちのリアルな描写が大きなインパクトを残す作品だが、その続編『大河のうた』(56)はATG系で配給されながらも興行的には厳しい結果を残した。そのため、三部作の完結編『大樹のうた』がATG系で公開できない状況になっていたが、そこに救い船として現れたのが岩波ホールだった。
この作品にほれ込んでいた高野総支配人が公開を決めて、74年の2月にロードショーを行うことになった。商業的には未知数の作品ゆえリスクも大きく、周囲も心配していた。実際、初日には50人しか観客が集まらなかったという。しかし、少しずつ作品のクオリティの高さが浸透していき、4週間後にホールは遂に満席となった。
80年代以降のパイオニア的なミニシアターも、普通の映画館にはかかりにくい個性的な作品の受け皿となっていくが、そんなミニシアターの発掘精神を最初に見せたのも岩波ホールだった。
この時から常設館として新たなスタートを切ることになり、埋もれた名作を次々と救いあげていく。

◉「神保町」の交差点から至近の距離となる、千代田区神田神保町2-1 岩波神保町ビル10Fに所在
「高野はサタジット・レイのことはすごく大事にしていて、その後も彼の作品を何本もかけました。また、フェデリコ・フェリーニやイングマル・ベルイマンといった世界の巨匠たちの未公開作品の紹介や宮城まり子監督の『ねむの木の詩』(74)と『ねむの木の詩がきこえる』(77)、名匠、ルネ・クレール監督の30年以上前の『そして誰もいなくなった』(45)も上映しました」
ちなみに『フェリーニの道化師』(70)は76年にホールにかけられているが、そのプログラムには川喜多かしこ専務理事が〝エキプ・ド・シネマ〟に関して、こんな文章を寄せている。
「岩波ホールの高野悦子さんと、『女ふたり』の仕事として始めた〝エキプ・ド・シネマ〟が、皆様がたから予期以上のご支援を得て、すくすくと育ち、3周年を迎えることができました。実際面のややこしい仕事は高野さんにお任せして外国の映画祭を飛び回っている私は、いささか晴れがましい気持ちです」
この〝エキプ・ド・シネマ〟の運動に関しては、主に以下の4つの目標が掲げられていた。
一、日本では紹介されることのない第三世界の名作の紹介
二、欧米の映画であっても、大手の興行会社が取り上げない名作の上映
三、映画史上の名作であっても、何らかの理由で上映されなかったもの、また、カットされ不完全な形で上映されたものの完全版の紹介
四、日本映画の名作を世に出すことの手伝い
こうした目標は今もホールを運営する後輩たちに引き継がれている。
また、『道化師』のプログラムにはパリで映画製作を学んでいた高野総支配人の映画の師でもある日本の巨匠監督、衣笠貞之助がホールに関して貴重な一文を残している。彼の幻の名作、『狂った一頁』(26)と『十字路』(28)は75年に岩波ホールにかけられ、大成功を収めた。
「一風かわった異色映画は、おそらく一般のロードショウ劇場にかけても、かなしいことに、日本では1週間もつのがやっとかもしれない。映画というものに対して、一般がもっている固定観念は、ただ、劇(ドラマ)を見てたのしむものと、きめてかかっている。〔中略〕だからこそ、また、『岩波ホール』の存在意義が一段と光ってくるのである」
その後もホールは着実に成功を重ね、77年にはアンドレイ・タルコフスキー監督の幻の名作『惑星ソラリス』(72)、ルイス・ブニュエル監督の『自由の幻想』(74)など、普通の劇場では上映できなかった問題作をかけた。
78年には原田さんの人生を大きく揺さぶる映画、『ピロスマニ』(69)も上映された。
「主人公は実在の画家、ニコ・ピロスマニで、放浪の画家だった彼の人生を描いた作品でした。自分でも絵を描いていた僕の人生を大きく変えた一作です。この映画を見た後、グルジアに興味を持ち、その後、実際に訪ねて、すごく魅せられました」
帰国後、原田さんは日本グルジア友の会を設立した。その後、絵本作家としても活動するようになり、内外の名誉ある賞も手にしている原田さんは21世紀に出版された絵本『大きな木の家/わたしのニコ・ピロスマニ』と評伝本『放浪の画家 ニコ・ピロスマニ』(共に冨山房インターナショナル刊)の中でもこの孤高の画家への熱い思いを綴っている。公開時、映画は興行的にも大成功を収めた。
さらに、この年から翌年79年にかけて、岩波ホールの運命を大きく左右する作品群が登場する。
「まず、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『家族の肖像』(74)を上映しましたら、大変なヒットとなり、他のヴィスコンティ作品も何本かうちで上映しました。この成功の後、別の映画館も彼の作品を積極的に上映していました」
『家族の肖像』はこの劇場では10週間のロングランとなり、当時、スタッフたちはトイレに行くこともできないほど、毎日、問い合わせの電話が鳴り続けていたという。その後は東宝の拡大系映画館にもムーブオーバーとなり、さらに大きな人気を得た(当時、劇場プログラムは岩波ホール版、東宝版の2種類が作られたという)。
また、79年にはイタリアのエルマンノ・オルミ監督がイタリアの農民たちの生活を描く3時間の長編『木靴の樹』(78)やテオ・アンゲロプロス監督が旅芸人の視点でギリシャ史を綴った4時間の長編『旅芸人の記録』(75)も上映され、大きな反響を呼んだ。
「このあたりの作品からフランス映画社の作品もかけるようになり、この会社の柴田駿社長や川喜多和子副社長(かしこの長女)とのおつきあいも生まれました。ベルイマンやフェリーニといった世界の巨匠とは別に、これからの映画界を背負う新しい監督たちをいち早く見つけようとしていましたね。フランス映画社のおかげで、巨匠の幅が広がっていったと思います」
80年には数年間オクラだったヴィスコンティ監督の大作『ルードウィヒ』(72)の公開も実現し、こちらも大きな反響を呼んだ(この作品も岩波ホールでの上映以外に、東宝系の映画館でも公開され、『家族の肖像』同様、2種類のプログラムが作られた)。
こうしたヨーロッパの作品群がかけられることで、岩波ホールは劇場として幅広い認知を得る。その成功に他の映画人も刺激を受け、80年代以降の多くのミニシアター誕生の大きな発火点となる。

◉岩波ホールでは「名作」を意欲的に選ぶ〝運動体〟として出発した。その中の一人、アラン・レネ監督の遺作が来年2月に上映される
81年に新宿のシネマスクエアとうきゅうを作る時、その中心人物のひとりだったヘラルド・エースの原正人社長(当時)も「岩波ホールをもっと商業的にしたミニシアターをめざした」と語っていた。83年には六本木の文化ビル、WAVEの中にシネ・ヴィヴァン・六本木が作られ、今度はこちらでフランス映画社の作品群が上映されることになる。どちらも大手企業が作ったミニシアターで、シネクラブ的な運動体の意味合いが強い岩波ホールより、もっと商業的な劇場だった。
このミニシアター・ブームの始まりについて、高野悦子総支配人は2013年に刊行された遺作『岩波ホールと〈映画の仲間〉』(岩波書店刊)の中で、こんな風に回想している。
「『家族の肖像』が成功し、ヴィスコンティ・ブームが巻きおこった頃から、エキプを取りまく興行界の動きの変化が感じられはじめた。特にアメリカの娯楽映画一辺倒だった大会社が、岩波ホールの興行形態に興味を持つようになったらしく、何人もの映画関係者がエキプの研究のためにとホールを訪ねてきた。〔中略〕私はいつの間にか、ミニシアターの元祖とか、生みの母と呼ばれるようになっていた」
「ところがである。岩波ホールがつぶれるという噂がまた耳に入ってきた。岩波ホール創立当時、すでによく耳にしたし、エキプスタート時には、上映作品が終わるたびに言われてきた。〔今回は〕ミニシアターが増えるにつれ、作品の取りあいになり、岩波ホールで上映する映画がなくなるため、ということなのである。確かに初期のエキプを支えてくれた名匠監督たちは、たちまち日本で甦り、他の劇場でどんどん上映されることになった。テオ・アンゲロプロス、アンドレイ・タルコフスキー、アラン・レネ監督たちの作品も、その難解さゆえに流行になった感もあった」
「しかし、私はこの現象をかえって喜んだ。私たちには、上映したい作品がたくさんある。私たちの力は微々たるものだから、お仲間が増えるのは嬉しいことだ。私たちの好きな映画を上映する映画館が増えれば、良質の観客も増える、つまり、私たちの映画の仲間が結果的には増えるのだ。名匠巨匠の再発見を他の人がやってくれるなら、私たちはもっと地味な作品を上映することができる」
他のミニシアターの出現を〝映画の仲間〟の増加につながる、と好意的にとらえ、前向きな考え方を示した高野総支配人であるが、これについて原田さんからはこんな答えが返ってきた。
「シネマスクエアやシネ・ヴィヴァンが出てきて、それぞれが自分たちのカラーを求めた時代だったと思います。たとえば、シネスクと岩波の関係は、今の文化村のル・シネマとうちに関係に似ているところがあり、シネスクやル・シネマの方がうちより華やかなイメージでした。映画ファンとして、ミニシアターが増えたことは歓迎すべきことだったと思いますが、ホールの支配人としては厳しい時代になったな、という気持ちもあったはずです。カンヌ映画祭では各社で作品の争奪戦が起きていましたから。僕は自分の好きな作品を上映したいという思いが強かったのですが、高野はどこかおっとりしていましたね。とにかく、一本の映画をみんなで取り合っても仕方ないので、ホールの今後の個性についていろいろ考えていきました」
本格的なミニシアター時代が到来した80年代以降、岩波ホールはいくつかの新しい方向性を模索する。まずは「アジア映画への新たな挑戦」である。
「当時、アジア映画をもっと開拓しようという思いがありました。ひとつには高野が大陸(満州)生まれで、中国への思いが強かったせいでしょう。そこでシェ・チン(謝晋)監督の『芙蓉鎮』(87)を上映したのですが、これが大ヒットとなり、同監督のその後の作品も上映しました。高野は中国映画への思いというものを強く持っていました」
『芙蓉鎮』は文化大革命の大きな波に飲まれながらも、その厳しい環境を生き抜こうとする庶民たちの姿を力強く映し出した作品で、88年に岩波ホールでは2時間45分の完全版の上映が実現して大ヒットを記録した。岩波ホールの歴代動員数の第10位(20週上映)に入っていて、1億2000万円の興行収入を上げ、7万6000人を動員している。80年代後半から90年代にかけて、日本のミニシアターでは中国や台湾、香港などからやってきたアジア映画が人気を得ていた。
特に中国の第五世代を呼ばれるチェン・カイコー(『さらば、わが愛/覇王別姫』〈93〉)やチャン・イーモウ(『紅いコーリャン』〈87〉)、ホウ・シャオセン(『悲情城市』〈89〉)といった監督たちの斬新な映像感覚が注目を集めたが、彼らより年上である第三世代のシェ・チンの作品には大河ドラマ的なうねりがあり、それが当時の観客の心をとらえた。
その後は旧・満州に捨てられた日本人孤児の運命を追った93年上映の『乳泉村の子』(91、歴代興行の第9位、22週上映)19世紀の阿片戦争を映し出した歴史大作97年上映の『阿片戦争』(97、歴代興行の第7位、約17週上映)といった同監督の映画もこの劇場でヒットしている。
また、歴代興行の1位もアジア映画で、女性監督、メイベル・チャンの香港・日本の合作『宋家の三姉妹』(97)が99年に大ヒットを記録した。蒋介石や孫文らの妻となった実在の三姉妹の運命をマギー・チャンやミシェール・ヨー、ヴィヴィアン・ウーといった豪華な女優陣で描きだした大河ドラマだ。
「高野は自分も三姉妹でしたので、特にこの姉妹の設定にひかれたのでしょう。当初は25週の上映を考えていたのですが、急に強気になって30週上映を設定してがんばりました。当時は民音(民主音楽協会)などの団体で、前売り券が売れていた時代でしたので、そうした恩恵もあり、記録的な大ヒットとなりました」
岩波ホールの場合、ほぼ1年前からラインナップを決め、その時、上映週も決めていく。興行成績が良かった場合、封切りから少し時間がたってからアンコール上映が行われることもあるが、『宋家の三姉妹』の場合は30週の上映後、アンコール上映も実現し、最終的には44週の上映となる。3億円の興行収入を上げ、18万7000人を動員した。
ちなみに同じ頃、渋谷の若者向けのミニシアター、シネクイントでは『バッファロー'66』(98)が大ヒットしていて、こちらは34週上映された。20世紀最後の年、渋谷も神保町もミニシアターに勢いがあった。
「あの頃、いろいろ思考錯誤を繰り返していました。今は1本、500万円くらいで映画を買うことが多いようですが、当時は5000万円くらいで買われたものもあったはずです。とにかく、うちの場合は〝映画は国境を超える〟というコンセプトがあり、上映作品の国籍を増やしていきました。これまで40カ国以上の作品を上映していると思います」
中国映画に関しては2001年にかけられた人間ドラマ、『山の郵便配達』(99、22週上映)も大ヒットとなり、歴代動員数の第2位となる。約2億円の興行収入を上げ、12万4000人の観客を集めている。山奥の小さな村で黙々と郵便配達を続ける父と息子の物語で、その風景の美しさも心に残る。
「この映画は集英社から原作が出たんですが、映画がヒットしたおかげで10万部を超えるベストセラーとなりました」
集英社は岩波ホールの至近距離にある出版社で、この原作の表紙の絵も原田さんが手がけたという。そんなエピソードの中には本の街にふさわしい出版と映画館の幸福な関係が見える気がした。
「この映画は、『朝日新聞』の『天声人語』でも紹介されたんですが、あの頃はそういうことにも大きな意味がありました。新聞の文化欄でも、うちの映画をよく取り上げていただいたんですが、近年はそういうこともなくなり、映画が文化としてきちんと議論されなくなったことが残念ですね。今は上映の作品数も多いし、紹介もカタログ化しているのかもしれません」
この時代の「アジア映画の開拓」は、岩波ホールに大きな成果を残した。国籍は日本映画であるが、韓国の男優、アン・ソンギを主演に迎えた『眠る男』(96、小栗康平監督)も話題を呼んだ。韓国と日本との文化交流が今ほど広がっていなかった時代に作られた貴重な作品で、96年に26週上映され11万人動員。歴代動員の4位で、1億7500万の興行収入を上げている。
小栗監督は84年にこの劇場で上映された日本映画『伽倻子のために』(84)でもすでに韓国の問題を取り上げていて、高野総支配人は「〔この映画は〕監督と岩波ホールとの距離をぐっと近づけてくれた。〔この作品があったからこそ〕岩波ホールは今でも韓国の映画人と〝映画の仲間、エキプ・ド・シネマ〟として付き合えるのだ」と回想している(『岩波ホールと<映画の仲間>』より)。

大きなきっかけとなったのが、85年5月31日に東京で始まった第1回東京国際映画祭だった。バブル景気で盛り上がっていた時代だからこそ、始めることができたイベントだったが、その中に女性映画の部門も設け、高野悦子総支配人がジェネラルプロデューサーを務めることになった。前述の著書『岩波ホールと〈映画の仲間〉』の中に高野総支配人はこう書き残している。
「日本が経済大国といわれるようになってから、なぜ日本には国際映画祭がないのかと、外国の友人からよくいわれていた。だから、日本の映画人の一人として、この映画祭の発足を心から嬉しく思っていた」
「時あたかも一九七六年にスタートした<国際婦人の一〇年>の最終年にあたり、女性の地位向上ための将来戦略が注目を集めていた。これを受けて、欧米、ソ連・東欧諸国はもとより、アジア、中南米の国々でも、映画の内容を決定する監督の座に、女性が群れをなして出現しはじめていた。しかし、日本には、劇映画の監督を職業とする女性は皆無だった」
「世界の映画祭では、一九七五年頃から女性監督が映像の中で積極的に発言するようになっていた。〔中略〕それまでの、男性だけの視点でできた映画の中に、女性の視点が加えられていくのだから、映画の世界を豊かにするという意味でも喜ばしいことである」
「若い頃、監督を夢見て挫折した経験のある私は、〔このイベントは〕若い女性たちに勇気と希望を与えるに違いないと考えた。〔中略〕私はこの企画をエキプ運動のひとつと考え、川喜多かしこさんにアドバイザーをお願いした。タイトルには<映像が女性で輝くとき>とつけた」
この女性映画祭はその後も続いていくが、第1回目に上映された女優ジャンヌ・モローの監督作『ジャンヌ・モローの思春期』(79)、ヘルマ・サンダース・ブラームス監督の『エミリーの未来』(84)、羽田澄子監督の『AKIKO/あるダンサーの肖像』(85)といった作品は、映画祭で上映後、岩波ホールで封切られている。
女性映画祭の劇場への影響について原田さんはこう語る。
「この映画祭を通じて高野の女性監督への思いがより強く出た番組作りになっていきました。とにかく女性監督の映画を多く取り上げるようになり、年間のラインナップの半分くらいが女性監督の作品だったこともあります。今年亡くなったヘルマ・サンダース・ブラームス監督の場合、80年代の『ドイツ・青ざめた母』(80)から最近の『ハンナ・アーレント』(12)まで多くの作品を上映してきました」
実在の人物を主人公にした『ハンナ・アーレント』は13年に岩波ホールで7週間上映された後、他の劇場にもかけられ、かなり話題を呼んだ。
「日本ではあまり知られていなかった女性の思想家の物語ですが、今の不安定な時代の中で、自分のしっかりした意志を持つことの大切さを明確に描いた作品でした。人間が考える意志を持つことがいかに大事か。そんなテーマが打ち出され、共感できる作品だと思います」
今のネット社会の中では確かに「自分自身で考えること」の意義が見失われつつあるのかもしれない。誰かの意見がコピー&ペイストで簡単に複製されていき、時にはそれを読むだけで自分も分かった気になる場合がある。そんな時代だからこそ、自分の目で考えることの大切さを訴えたこの作品には公開意義があった。
「ユダヤ人問題なども含まれた政治的な内容なので、実はうちでの上映に対して反発する意見もありましたが、上映は成功でしたし、この映画をきっかけにハンナの本も爆発的に売れたそうです」
映画ではドイツの人気女優、バルバラ・スコヴァが強い意志を持つ知的なヒロインを好演しているが、80年代には同監督の『ローザ・ルクセンブルグ』(85)にも主演してカンヌ映画祭主演女優賞を獲得している。こちらは社会運動に身を投じる実在の革命家が主人公で、『ハンナ・アーレント』に共通するテーマをすでに発見できる。
岩波ホールでは前述のヘルマ・サンダース・ブラームス以外にも、『サラーム・ボンベイ!』(88)や『ミシシッピー・マサラ』(91)のインドのミーラー・ナーイル、『アントニア』(95)や『ダロウェイ夫人』(97、16週上映、歴代動員数の第8位)を手がけたオランダのマルレーン・ゴリス、『森の中の淑女たち』(90、再上映も含み26週上映、歴代動員の第6位)のカナダのシンシア・スコットなど、さまざまな国籍の女性監督たちの作品を紹介してきた。。
また、「社会性の強い作品の上映」もこのホールは積極的に実践してきた。
「その代表的な例はポーランドのアンジェ・ワイダ監督の作品でしょうね。80年代以降、ソビエト社会主義に反発する作品が東欧の中から出てきました。タルコフスキーのような監督はソビエトから亡命していましたが、ワイダの場合は社会主義をめぐる問題を扱った映画を撮ってきました」
まもなく90歳を迎える巨匠のワイダは戦後ポーランドの歴史の転換点を背景にした70年代の『大理石の男』(77)や80年代の『鉄の男』(81)で高い評価を受けたが、2014年にホールにかけられた『ワレサ/連帯の男』(13)はこの過去の代表作と地続きともいえる内容で、ポーランドの民主化運動で主導的な役割を担った「連帯」の創始者・ワレサ委員長を主人公にしている。こうした硬派の作品群の受け皿となっているのも岩波ホールである。
「80年代後半にソ連が崩壊すると、90年代以降は民族紛争の時代となります。ユーゴスラヴィアなどを見るとそれが分かりますが、そうした紛争の時代の問題を取り上げた作品も上映していきました」
ユーゴスラヴィアの映画としてはこの国の代表的な監督のひとり、エミール・クストリッツアがユーゴのロマ(ジプシー)の放浪生活を独特で感覚でとらえ、カンヌ映画祭監督賞を受賞した『ジプシーのとき』(89)を91年にかけた。クストリッツア作品はカンヌ映画祭パルムドールを受賞の処女作『パパは、出張中!』(85)も80年代にこの劇場で上映されている(蛇足ながら同監督がボスニア・ヘルツェゴヴィナ=旧ユーゴスラヴィアの50年間の歴史を追った作品には『アンダーグラウンド』〈95〉もあるが、これは別の劇場で上映されている)。
ボスニア・ヘルツェゴヴィナの問題については、この国の戦火をくぐり抜けたアデミル・ケノヴィッチ監督が平和への祈りを込めて作った『パーフェクト・サークル』(97)を98年に封切った。
厳しい社会状況を背負った監督としてはトルコのユルマズ・ギュネイも忘れがたい。政治犯として投獄されていた時にシナリオを書き、代理監督に獄中から指示を出すことで作られた『群れ』(78)『敵』(79)といった作品が80年代にこの劇場にかけられた。
イギリスの社会派、ケン・ローチ監督はスペイン内乱をテーマにした大作『大地と自由』(95)が上映されているが、ゼロ年代には息子のジム・ローチ監督が教会の腐敗を暴いた『オレンジと太陽』(10)でデビュー。父子二代に渡って、その作品が岩波ホールのスクリーンに登場している。
社会問題といえば、日本の戦争をテーマにした作品も上映されてきた。その代表的な例は岩波映画出身の名匠、黒木和雄の<戦争レクイエム三部作>で長崎への原爆投下の前日を描いた井上光晴原作の『TOMORROW 明日』(88)、敗戦の夏の人々の暮らしを見つめた『美しい夏キリシマ』(03)、井上ひさし原作の『父と暮せば』(04)などが上映された。『父と暮せば』は宮沢りえが広島の原爆の悲劇を生きのびたヒロインに扮し、亡くなった父親の幻(原田芳雄)と生きることの意味について語り合う。この作品は再映も含めて25週上映され、歴代動員数の第5位。9万7000人がホールを訪れ、1億円以上の興行成績を上げている。
さらに黒木和雄の助監督だった日向寺太郎の演出による実写版『火垂るの墓』(08、野坂昭如原作)、日系監督のスティーヴン・オカザキがアカデミー賞のドキュメンタリー賞受賞の『ヒロシマナガサキ』(07)などもかけられている。
「『ヒロシマナガサキ』の上映後、特に広島や長崎の原爆の問題に興味を持ちました。そこで佐々木昭一郎監督に新作を撮ってもらう時、長崎をテーマにした作品にできないだろうか、と持ちかけたところ、自分には長崎は撮れない、と言われたんですが、結果的には戦争のテーマも含まれた作品に仕上がりました」
2014年に公開された『ミンヨン 倍音の法則』(14)はNHKの伝説的な監督だった佐々木昭一郎の劇映画デビュー作である。原田さんが初めて製作も手がけ、5年の歳月をかけて作られた。
韓国出身のヒロイン、ミンヨンの意識の旅を追い、さまざまなイメージが交錯していき、戦争をめぐるエピソードも登場する。ミンヨンが出会う宣教師が、午前11時2分で止まった時計を背負っているのだ。これは1945年8月9日、長崎に原爆が投下された時刻を意味している(長崎原爆資料館には実際にこの時間で止まった投下時の時計も展示されている)。
「佐々木監督は自分を赤裸々にさらしつつも、納得できる形にするまで譲らない人で、その強い思いが作品にも出ていると思います。今の邦画は製作委員会方式なので、多くの人が意見を出しながら作っていき、監督の姿が見えなくなることもあります。効率や経済を優先する時代で、その結果、作家性が薄い作品が誕生していく。芸術の意味について考えさせられますね」
そんな昨今の商業的な邦画の傾向とは異なり、どこまでも作り手の自由が発揮された野心作だが、憲法第九条の意味が問い直されている時代に見ることで、戦争の問題についても考えさせられる。
原田さんは高校時代にテレビで佐々木監督のテレビ・ドラマ「さすらい」(71)を見て、「人生の意味について考えた」というが、後に岩波ホールで上映したエルマンノ・オルミ監督の『ポー川のひかり』(06)がきっかけで監督と交流が始まり、70代後半にして監督が劇場映画デビューを飾ることになったこの新作で製作を担当した。岩波ホールはそんな創造的な縁を引き寄せる場所でもあるのだろう。

アメリカのメイン州にある小さな島の別荘で夏を過ごす姉妹の物語で、ハリウッドを代表する名女優、リリアン・ギッシュとベティ・デイヴィスの共演が大きな話題を呼んだ。
「老いてどうのように生きるのか、ということがテーマになっていました。ふたりの高齢者の姉妹が主人公で、ヒロインを演じたリリアン・ギッシュは当時90歳、ベティ・デイヴィスは79歳でした。ふたりの演技を見ていると、足元が危なくて、よくぞ、あそこまで演技をさせたな、と思ったものです」
この作品は当初、14週の上映が予定されていたが、記録的な大ヒット作となり、何度かアンコール上映が行われている。再映も含めて30週の上映で、1億7900万円の興行収入。13万人の動員となり、歴代動員数の第3位となっている。
「高野が最初にカンヌで見て、それで上映が可能になった作品だったと思います。でも、ここまでヒットするとは誰も思っていませんでした。上映時は劇場に人があふれ、ドアを閉められない日もありました。ここまでヒットしたのは日本だけで、映画のシナリオライターが来日した時、とても喜んでいました。ひとつには淀川(長治)さんの力が大きかったのかもしれません。この映画のことを気にいり、とても熱心な口調で、あちらこちらで話していただきました」
当時のプログラムから淀川長治がこの映画に寄せた文章を引用しておこう。文章のタイトルは「『八月の鯨』からあふれるもの」。
「女ふたり……これは名小説、これは名舞台、そして私たちは名作の名文を読む楽しさに溺れてゆく。2度、3度、その3度目には声を出してリリアンの台詞についてゆくにちがいない」
「リリアンとベティのしっかりと握り合ったその握手の手のクローズアップでこの名作はしめくくられた。さらにまた涙があふれた。しかしまた、あのアメリカ映画の歴史その長い長い道をへてきたこの2名女優のしかも今ここにまたこの2人の見事なる共演。この2人が〝長生きしていてよかったわねぇ〟のそのプライベートなやさしく可愛い心あたたまる握手にもかさなり、このラスト・シーンは映画ファンに涙をかくすことを困らすであろう。かまうことはない。泣き給え、思いきり涙をあふらせ給え」
また、ポスター・デザインの大御所であり、映画やジャズの評論家としても知られる野口久光もこの映画の熱心な支持者のひとりで、公開時にニューヨークでリリアン・ギッシュと会って彼自身が描いた彼女の若い時のポートレートを手渡したという。淀川長治に野口久光と、映画の黄金期の記憶が甦ってくるような大ベテランのサポートが、この映画の場合、大きな意味を持っていた。
「古くてもいい作品はもう一度上映したいと思っていて、岩波ホールの創立45周年(2013年)を迎えるにあたって、この作品をもう一度、かけました。監督が亡くなった後は配給権が行方不明になっていたのですが、ベルリン映画祭に行った配給会社の方から電話が来て、権利が売りに出ているといわれました。アンコール上映ではプリントの状態で6週間上映しましたが、当時のお客様も含め、多くの方に来ていただけました」
まさにこの劇場の看板作品の一本となった『八月の鯨』である。高齢者をテーマにした作品としては、岩波ホールに縁の深い羽田澄子監督の『痴呆性老人の世界』(86)『安心して老いるために』(90)といったドキュメンタリー、さらに2011年にかけられたポーランド映画の『木洩れ日の家で』(07)なども上映されている。
現在の日本ではこのテーマがますますクローズアップされているが、同劇場の歴史を振り返ってみると、すでに80年代後半からこの問題を含んだ作品が上映されていたことが分かる。
この40年間、老舗のミニシアターとしてさまざまな方向を模索してきたわけだが、特に大切にしてきた〝岩波ホールらしさ〟とは何だろう?
「作品を通じて人間性の豊かさみたいなものを示したいと思ってきました。戦争や差別のように人間性を損なうものに対しては断固戦っていきたいし、人間性をうたい上げる作品は積極的に紹介していきたい。そういうものが基本的にありますね。映画は人間が人間を描くためにあるもの。だから、映画館としては人間のぬくもりを大切にしたいと思います。そう考えると、シネコンやデジタル化はそうしたものにそぐわない気もします。これまでの40年間、さまざまな作品を上映し、世界の時代の空気を伝えてきましたが、今は大きな岐路に立たされているのかもしれません」
特に原田さんがむずかしいと感じているのは〝文化の伝承〟だ。
「僕が古くから学んで、経験したことをどこまで維持できるのか? それが問題になっているのかもしれません。うちのホールも、他の映画会社もどんどん世代交代しています」
そんな変化の波の中にあっても、2013年には前述の『ハンナ・アーレント』、14年にはドキュメンタリー『大いなる沈黙へ/グランド・シャルトルーズ修道院』(14)といったヒット作を世に送り出してきた。
後者は製作に21年の歳月がかけられ、05年に完成。かなり前にこの作品に出会って、公開を切望していた原田さんは日本での公開のタイミングをうかがっていた。そして、9年遅れで封切られたところ興行的に大成功を収め、その後は他の劇場でも上映され続けている。どちらも人間性の大切さを問いかける作品だ。
ただ、残念なことに高野総支配人はこうした作品の成功を見ることなく、13年2月に他界した。
「高野とはよくケンカもしましたが、とにかく、責任感が強い人で、社員ひとりひとりに母親のように接してくれて、その目くばりはなかなかのものでした。ちょっと前に高野の夢も見ました。そこで何気ない会話を交わしているんですが、目が覚めるとすごい喪失感があって……。かつての豊かな思い出がよみがえってきて、その世界を失ってしまったことに改めて気づきました。大切な家族のひとりを亡くしたような思いにとらわれることもあります」
大きな喪失感は現在の文化全体に関しても抱いている感情でもある。
「今、失われたものがとにかく多い気がします。かつて『ぴあ』のような情報誌があった頃は全体を見渡すことができましたが、ネットでは全体像が把握できない。また、実際に身を持って経験しないと分からないこともありますが、そういうものがあまり必要とされない時代になりつつあるのかもしれません」
スマートフォンなどで映像そのものは簡単に見られる時代になったが、映画館の映像との違いについて原田さんはこう語る。
「小さな画面で見ると、情報としては入ってきますが、その人の人生に響くものがない気がします。やはり、スクリーンで見た方が得るものが大きい。ただ、今の状況では観客を映画館に戻すのがむずかしいし、時間もかかる。果たしてそこまで映画館が持ちこたえられるのか、よく分かりません。民間だけの力ではむずかしく、学校も含めた教育が映像文化に積極的に取り組まないと厳しい部分もあるのかもしれません。とにかく、確実に時代が変わってきているので、柔軟性も保ちつつ、未来に向かっていけたらいいですね」
こういう時代だからこそ、人間性の豊かさを追求する劇場の意義も深い。人の輪(=映画の仲間)を大切にしてきた老舗ミニシアターの未来への取り組みを見守っていきたい。

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。