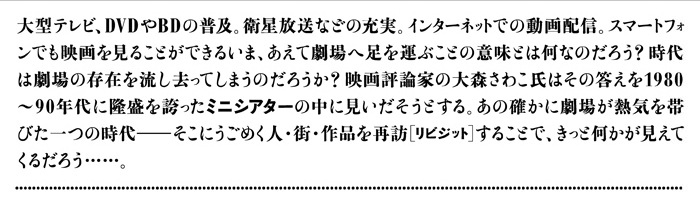メジャー系洋画会社の持ち込み作品が、その後もシャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)で上映されていくが、アンソニー・ホプキンス主演の『日の名残り』(93)はソニー・ピクチャーズからの持ち込み作品だった。
シャンテの副支配人だった高橋昌治東宝専務取締役(取材時。現・東宝不動産社長)はこの作品についてこう語った。
「大手の配給会社の従来のやり方では興行的にむずかしそうな映画もありました。『日の名残り』もそうした一本で、拡大公開系の大きな劇場には出にくい作品だったはずです。監督はジェームズ・アイヴォリーで、海外に住む日系の作家が賞をとった原作の映画化です」
原作者のカズオ・イシグロは英国在住の日系人作家で、この小説で英国の権威ある文学賞、ブッカー賞を受賞。日本でも映画公開前から原作小説が静かな人気を呼び、映画化作品へも期待が高まっていた。シャンテでは1994年3月19日から17週間に渡って上映され、歴代興行の第6位(1億1700万円)につけている。
この年のアカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞(アンソニー・ホプキンス)、主演女優賞(エマ・トンプソン)等、8部門の候補になったこともヒットを支える要因になったのだろう。
主人公は英国の貴族の屋敷に勤める執事のスティーヴンスで、完璧な執事であろうとする彼は自分の感情を抑えて主に仕える。そのため、その屋敷の女中頭、ミス・ケントンに対する自分の愛情にも気づかない。そんなスティーヴンスに失望したケントンは好きでもない別の男性と結婚するため、屋敷を出てしまう。
そして、20年後、スティーヴンスは彼女との再会の旅に出る。
執事という職業は英国特有のものだが、そこで綴られる人生の喪失感というテーマは普遍的で、特に年齢を重ねた観客にはグサリと胸につきささる内容だ。また、ナチスの政策を支持して、やがては失脚していくスティーヴンスの主を通じて、歴史に翻弄される人間の姿も見ることができる(主に危機が迫っていても主人公はただ見守ることしかできないが)。「品格」や「忠誠心」といった今の時代からは失われつつある価値観が浮かび上がる文学的な作品だ。
イシグロの原作(日本での初版は中央公論刊、土屋政雄訳)は淡々とした文章の中に詩情がにじむが、映画版は主演の男優と女優の個性の強さもあってか、原作以上に厳しい男女の心理的な葛藤が登場する。公開時は自分の感情を隠さないケントンに共感しながら見たが、年を重ねた後に再見すると、影のように生きながらも仕事への誇りを貫こうとするスティーヴンスの心情もよく分かる。
こういう作品に出会うと、映画は一生ものの体験だな、と思う。年を経ることで、若い時とは違った解釈ができて、さらに作品の余韻も深まる。
ジェームズ・アイヴォリーは『眺めのいい部屋』(86、俳優座シネマテンとパルコ・スペース・パート3で上映)や『モーリス』(87、シネスイッチ銀座で上映)も手がけていて、どちらも大ヒットを記録。ミニシアターが育てた人気監督のひとりである。
「アイヴォリーの映画としては『眺めのいい部屋』もよかったですね。公開されたのはシャンテのオープン前ですが、こういう作品もやってみたかったです。他にもパーシー・アドロン監督の『バグダッド・カフェ』(87)などもシャンテで上映してみたかったです」
高橋専務はそう語る。見る側だけではなく、送り手の強い思いをかきたてる作品が当時のミニシアターでは次々に上映されていたということだろう。
ふだんはディズニーのアニメや大作エンタテインメントを配給しているブエナ・ビスタ・ジャパン(現・ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン)がシャンテにかけて大ヒットとなったのがイタリア映画の『イル・ポスティーノ』(94)で、96年5月18日より19週間の上映。シャンテの歴代3位の興行成績(1億4800万円)となった。
この作品に関しては高橋専務の取材に同席していた東宝総務部の松本章也室長(元スカラ座・旧みゆき座勤務)がこんなエピソードを披露した。
「この映画はシャンテのキャパシティではお客様が入りきれず、しばらく近くの〔旧〕みゆき座で上映したことがありました。シャンテは220席ちょっとですが、みゆき座は750席以上ありました。前日までシャンテで上映した後、みゆき座まで上映用のフィルムを運んだのですが、シャンテから近かったので、こんなことができたと思います」
通常、1本の映画は6か、7巻の長いフィルムに収められている。その重さは相当なもので輸送が楽ではなかったが、みゆき座はシャンテの至近距離だったので、夜の上映後、翌朝までにフィルムの束を届けることができたという。
『イル・ポスティーノ』の舞台はナポリの小さな島で、郵便配達人(イル・ポスティーノ)と実在のチリの詩人パブロ・ネルーダとの温かい関係が描かれる。怠惰な日々を送っていた主人公は、共産思想のため母国を追われた詩人との出会いを通じて詩の魅力にめざめ、村一番の美女に思いを告げようとする。
澄んだ空と青い海に囲まれ、水道さえもひかれていない自然のままの島。その風景を見ていると、自分もその島の住人になったようで、ほっこり気分に浸れる。
ルイス・バカロフの牧歌的なテーマ曲も耳に残るが、海外で発売されたサントラ盤にはジュリア・ロバーツ、イーサン・ホーク、ウィレム・デフォー、マドンナ、スティングといった人気スターによるネルーダの詩の朗読も収録され、詩の喚起力も伝わる。
監督のマイケル・ラドフォードは英国人だが、郵便配達人役のイタリアのコメディアン兼俳優マッシモ・トロイージと交流があった。41歳のトロイージは撮影前から心臓病をかかえていて、なんと撮影終了の12時間後に他界した。
最後の生の輝きをスクリーンに残したトロイージは、その年のアカデミー賞では主演男優賞候補となり、他にも作品賞、監督賞など5部門でノミネートを受けた(結果はバカロフがオリジナル作曲賞を受賞)。
ロケ地の美しさ、40代で急逝した主演男優、ネルーダの詩。いくつかの話題が重なることで、世界的な大ヒット作となり、シャンテでの興行も大成功を収めたのだろう。

◉『イル・ポスティーノ』も『フル・モンティ』も、音楽が秀逸だった
メジャー系洋画会社、20世紀フォックスも、シャンテの興行史に貴重な足跡を残している。英国のコメディ『フル・モンティ』(97)は97年12月13日から25週間の上映で、歴代5位の成績(興行収入1億3600万円)である。
"フル・モンティ"という聞き慣れない言葉は"すっぽんぽん"を意味する俗語。英国のさびれた町に住む6人のさえない男たちが、一夜限りのストリップショーで儲けようとする。バカバカしく、お下劣なコメディだが、工場の閉鎖で定職がなく、離婚後は息子の親権まで失いそうになっているダメ男(ロバート・カーライル)や過去のプライドを捨てきれない彼の元上司(トム・ウィルキンソン)など、失業者たちの悲哀感も出ていて、笑いつつもホロリとさせられる。
この作品についても松本室長が公開時の思い出を語り始めた。
「ちょうどバブルがはじけて後で、日本の元気がなかった時代に公開されました。『タイタニック』(97)と同じ年で、配給会社も同じです。そこで当時、『タイタニック』を上映している映画館で『フル・モンティ』の予告編をかけさせてほしいと申し出たら、フォックスの担当者はいやがって『冗談じゃない、あんなもの、かけちゃダメだ』と言われたものです。確かに下品なところはあるけれど、『タイタニック』のお客さんにぜひ見てほしいと女性のスタッフたちも言っていました。これまでとは違う新しいタイプの作品をシャンテのお客様に見てほしいという思いがありました」
フォックスの担当者は劇場のスタッフたちの熱意に負けて、『タイタニック』を上映する一部の映画館で予告編をかけることが実現した。
「実は『タイタニック』の試写会が国際フォーラムで行われた時、そこでチラシを配ったんですが、予告編を見た人の食いつきがよくてチラシのハケもよかったです」
この連載の中で高橋専務はシャンテを(2館ではなく)1.5館のミニシアターと呼んでいた。純粋にアート系映画だけを上映するのではなく、時にはあいまいな立ち位置の作品がかかることもあるという意味だったが、『フル・モンティ』に関してはそのことがむしろプラスとなった。
「いわゆるアート系映画ではないんですが、かといって普通のロードショー館では上映できないタイプの作品で、1.5館の劇場だからこそ、上映できたと思います。スタッフの熱意で上映が決まりましたが、封切ってみると、思った以上にお客様も入りました。客層は若い人が多く、男女の比率は半々でした。当時の宣伝プロデューサーは20世紀フォックスの高橋仁さんでしたが、何年か前に亡くなられたのが残念です」
笑顔が印象的な高橋仁さんは日本ヘラルド映画の宣伝部にいたこともあるが、その後は20世紀フォックスの宣伝マンとして元気に活躍していた。しかし、50代で突然、亡くなった。取材中にかつて活躍していた宣伝マンたちの話が出ることもあり、そんなところに過ぎた時間の流れを感じる。
『フル・モンティ』は音楽にも魅力があり、サントラ盤も話題を呼んだ。トム・ジョーンズが歌うテーマ曲「その帽子はそのままで」(ランディ・ニューマン作)やドナ・サマーの「ホット・スタッフ」など思わず体でリズムをとりたくなる70年代風味のダンスナンバーがたっぷり詰まっていて、オリジナル曲を担当したアン・ダドリー(<アート・オブ・ノイズ>のメンバー)はアカデミー賞のオリジナル作曲賞も手にした。
超低予算で作られた作品の方も、大作『タイタニック』と並びアカデミー賞の作品賞候補となった。
「あの年は『タイタニック』と『フル・モンティ』でしたね」と松本室長は語る。
実は主人公のダメ男を演じたスコットランド出身の個性派男優、ロバート・カーライルに99年にロンドンで取材をしたことがある。神経質で気むずかしい性格で知られ、取材を約束していてもドタキャンもあると聞いていたが、いざ、会ってみると気さくな雰囲気で、「日本からファンレターをたくさんもらったよ」とうれしそうな笑顔を見せていた。シャンテでこの作品を見て、彼のファンになった人も多かったはずだ。
この作品の興行的な成功の要因のひとつに、『タイタニック』の劇場での予告編上映があったとは知らなかった。
予告編とヒット作の関係については高橋専務がこんな話もしてくれた。
「予告編を流すことで、わりといい効果がでますね。もちろん、そこに来ているお客様と次にかける作品の感性があうかどうかの問題もあります。『ベルリン・天使の詩』(87)は大ヒットしましたが、この作品の後に同じヴェンダース監督の『都会のアリス』(73)の予告編をかけると大きなプラスになりました」
もっとも、どんな予告編でも流せばいい、というわけではないようだ。
「シャンテのお客様もそうですが、ミニシアターに来るお客様は自分をしっかり持っていらっしゃいます。だから、ヴェンダース作品の次に『フル・モンティ』のようにタイプの違う作品の予告編をかけた場合、自分の感性に合わないと思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。上映作品で予告編の効果も変わる場合があります」

◉『タイタニック』という恋愛映画と「今年いちばん赤裸々なモンダイ作」を結び付けたところに、映画興行の面白さがある
87年にスタートしたシャンテは当初は2館だったが、95年3月には192席のシネ3が加わる。それまでTBSラジオのスタジオがあり、地域FMを流していたが、それが撤退することになって3館目の登場となったが、当時と現在の洋画を取り巻く状況の違いについて高橋専務はこう言う。
「90年代までは洋画の興行がよかったので、ひとつでもたくさんの劇場がほしいという動きがあり、シャンテも3館となりました。でも、近年は洋画があの頃より不振となり寂しいですね。確かに今もおもしろい・良い作品はありますが、大作になればなるほど、ワンパターンになっているような気もします。また、小粒でいいものもあるけど、そういう作品は日本に入ってこなくなっているのかもしれません」
シャンテの歴代興行では圧倒的に洋画が強く、21位(興行成績7300万円)の矢口史靖監督の『ウォーターボーイズ』(01)が邦画では最高の成績となっている。こちらは01年9月15日から13週の興行だった。
これまでアメリカのインディペンデント映画や英国映画、アジア映画、さらにフランス、イタリア、ドイツや北欧やギリシャやフィンランドまで、世界の映画地図をカバーするプログラムを組んできたシャンテだが、いい映画を発見するためのルールはあるのだろうか?
「とにかく、勘しかないです。感性が大事ですね」
高橋専務はそう答えた。
「だから、自分の感性がお客さんの感性とずれたら、もうおしまいです。ロードショー公開の大きな作品であれば、監督や俳優、映画の中身などで判断できます。ミニシアター系でもたとえば、タヴィアーニ兄弟の作品だと、前がこれだけ入ったから、こっちもこれだけ入るかもしれない、という読みが成立していきます。しかし、ミニシアターの場合はそれだけでは成り立たずに、一から売り直す必要がありました。劇場側や配給会社にも、これを売ろうという気がないと、うまくいかないと思います。自分だけの感性ではなく、配給会社に同じような感性を持っている人がいれば、その人の感性に乗って決める場合もあります。また、配給会社に勢いがあると、それが決め手のひとつになることもあります。いろいろと総合的に見て上映作品を判断していきます」
シャンテの副支配人を務めた後、渋谷のロードショー館、渋谷シネタワーの支配人を経験した高橋専務だが、銀座と渋谷の違いについてはこう語る。
「銀座は一般のロードショー劇場が多く、お客様と劇場の距離があくまでもビジネスとして成り立っているわけですが、渋谷の場合、シネマライズやユーロスペースなどミニシアターもかなりあったので、お客さまとの距離がもっと近く感じられました。銀座でもシャンテなどにはそういうところがあって、劇場にお客様がついているという感覚があります。また、銀座の場合、一般のロードショー作品とアートの中間くらいの感覚のものをミニシアターで上映していました。渋谷はもっとアートに徹した作品が多かったです」
運営する側にとって、ミニシアターの醍醐味はどんなところにあるのか?
「それはお客様に優れた映像文化の場を用意できているという歓びですね。すべての人が満足するのではないかもしれませんが、多くの方にそう思ってもらえる場を提供できて、作品が心の中に残っていくわけです。お客様からその映画を『見てよかった』という声が聞こえることもあるし、『よく分からなかった』と言われれば、それでもいいと思います」
優れた作品を観客に届けること。そこにミニシアター運営の手ごたえがあったのだろう。
「実はフランス映画社の社長だった柴田駿さんがBOWシリーズを上映している頃、スクリーンの1番前に立って、お客様をばーと見ていたことがありました。そこで『高橋さん、いつものお客さん、今日も来ていますよ』とか言われるわけです。お客様のいる光景を脳にやきつけているような印象で、改めてすごい方だな、と思ったものです。そんな配給側とお客様たちの双方の熱意を劇場で感じました」
『ベルリン・天使の詩』が上映された80年代はひとつのミニシアターでの独占興行が多く、その結果、1館で1億円以上の収益を上げるヒット作も生まれていたが、21世紀に入ってからいくつかのミニシアターが手を組んで公開する興行形態が増えた。その結果、ひとつの作品に対する1館あたりのアベレージの収益が減った。シャンテの歴代興行成績の上位も80年代と90年代の作品が中心になっている(ベストテン内には9位に『英国王のスピーチ』(10)、10位に『チョコレート』(01)と21世紀の作品がかろうじて2本入っている)。
そんな時代の中で、高橋専務はこんな未来への言葉をシャンテというミニシアターに託した。
「ミニシアターはひとつの時代を築きましたが、今は第二の時代に入ってきているのかもしれません。とにかく、シャンテに関しては、シャンテ風の作品をやり続けて、それを積み重ねて文化にしてほしいと考えています」
(この項おわり)

◉現在は3つのスクリーンで「TOHOシネマズシャンテ」として営業している
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。