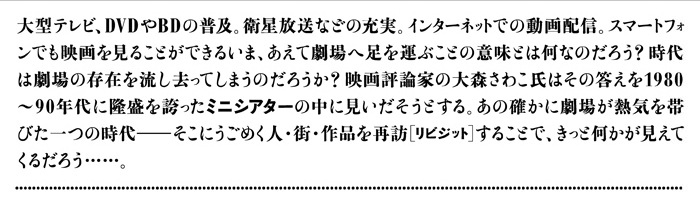地下鉄の六本木駅を降りて、大きな交差点の方に向かうと横断歩道が見える。かつては角に誠志堂という書店があり、よく待ち合わせに使ったものだが、今は携帯ショップに替わってしまった。その店を背にして道を渡り、しばらく直進すると左手にあるのが俳優座劇場だ。丸いチケットブースがあり、ガラスのドアを入ると、円形のロビーが広がる。そのロビーの向こうに英国式と銘打ったパブ、HUBのカウンターがある。
そんな俳優座劇場を映画館にかえた人々がいた。映画館といっても、別の部屋があるのではなく、演劇の上演が終わった後、そこで映画を上映していた。その映画館は「俳優座シネマテン」という名前で始まり、途中で「俳優座トーキーナイト」と名称を変え、20年以上続いた。
いま、劇場を外から見ても、かつて映画館が存在した跡は何ひとつ残っていない。もともとあった芝居小屋を映画館として利用していただけだから外観は変わるはずもなく、劇場にしてみれば以前に戻っただけだろう。しかし、そこに映画館が存在した時代を知る人間にとって、その(今では古ぼけた)劇場はさまざまな感慨をかきたてるはずだ。外観が変わらないからこそ、映画館の不在が寂しく、かつての記憶をたぐり寄せたくなる……。
俳優座シネマテンがスタートしたのは1981年3月20日。初めてかけられた映画はフランソワ・トリュフォー監督の『アメリカの夜』(73)である。ヨーロッパ映画好きの吉田叡子元支配人の趣味を反映して、この作品を“はじまり”に選んだ。会場時間は9時45分、開映は10時。“午後10時の映画館”が誕生した。
いま、こうして文字にしてみると、特に珍しいとは思えないが、当時、日本の映画館の最終上映時間は夜の7時前後。土曜日のオールナイトをのぞけば、夜に映画を見ることはできなかった。しかも、DVDやビデオも、衛星放送も普及していなかった時代。夜の映画を見るための唯一の方法は地上波のテレビの映画番組だけだ。
そこで吉田元支配人は観客が夜も映画を楽しめる劇場を作ろうと考えた。場所は六本木。70年代に起きたディスコ・ブームはこの街でも盛り上がり、その華やかな雰囲気が80年代初頭にも残っていた。夜も人が絶えない六本木という街を選び、シネマテンは東京で初めてレイトショーを始めた映画館となった。


◉亀井俊介を引用し意気込みを感じさせるシネマテンオープン当時のチラシ。客席数は300あった
毎日、夜の10時から1回だけ、芝居小屋で映画を上映する。いま、思えばまるで砂漠の蜃気楼のようではないか。しかし、そんな特殊な上映スタイルが当時は新鮮に思えたものだ。
そんな劇場の“はじまり”を知りたくて、2012年6月、吉田元支配人と再会した。
「あの頃、六本木の夜には活気がありました。日本は経済が上向きで、テレビ局では24時間放送が真剣に検討されていたほどです。夜の時間を使わないのはもったいないとさえ思われていたんですね。夜の活気と経済の活気。その両方が揃った時代でした」
シネマテンは80年から準備を進め、81年にオープンすることが決まった。
「ヨーロッパでは夜も映画を上映していて、夕食後も映画を楽しめるのに、日本にはそういう劇場がないことを残念に思っていました。そこで大人が夜に映画を楽しめる映画館をめざしました。劇場名の由来は、10時からの上映という意味もありますが、その頃、『テン』というアメリカ映画が海外では話題になっていて、10点満点の美女が出てくる映画なので、それもひっかけて、この劇場名になりました」
最初は封切り館ではなく、『アデルの恋の物語』(75)や『バレンチノ』(77)といった旧作が名画座のように上映されていたが、思うようにお客が集まらない。そこでオープンから4カ月後、ルキノ・ヴィスコンティ監督の51年の未公開作『ベリッシマ』を上映することになった。
吉田元支配人はもともとヨーロッパ映画の大ファンで、フランス映画やイタリア映画には思い入れが深かった。大好きな映画は『天井桟敷の人々』(45)で若い頃はこの映画が劇場にかかるたびに何度も繰り返し観ていた。また、60年代半ばには絵の勉強のため、イタリアに住んだこともあり、当時の映画ファンを魅了していたヴィスコンティやフェデリコ・フェリーニなどにも心を動かされた。
日本では70年代後半からヴィスコンティ映画のブームが起こり、岩波ホールで上映された『ルードヴィッヒ 神々の黄昏』(72)や『家族の肖像』(74)などは大きな話題を呼び、彼の他の作品も入ってきたが、50年代に作られたシンプルなモノクロ映画『ベリッシマ』は日本では30年間、未公開のままだった。アンナ・マニャーニ扮する母親がわが子をスターにしようとする物語で、悲劇のイメージが強かったヴィスコンティ作品としては軽やかなユーモアがある。
8月に封切られたこの映画の興業は成功して、スタートしたばかりのシネマテンにも明るい兆しが見え始める。ヴィスコンティはその後、シネマテンの看板監督のひとりとなり、特にデラ・コーポレーション配給の『地獄に堕ちた勇者ども』(69)『ベニスに死す』(71)のリバイバル上映は行われるたびに観客を集める。

その後は英国のユニ・セックス的なミュージシャン、デヴィッド・ボウイの2本の未公開作──伝説のライブ映画『ジギー・スターダスト』(73)と『ジャスト・ア・ジゴロ』(78)、セルジュ・ゲンズブールが監督して、ジェーン・バーキンが主演した75年のカルト的なフランスの恋愛映画『ジュ・テーム…』、イタリアの先駆的なふたりの女性監督、リリアーナ・カヴァーニとリナ・ウェルトミュラーの幻の名作なども上映される──カバーニは『ミラレパ』(73)『ルー・サロメ 善悪の彼岸』(77)、ウェルトミュラーは『セブン・ビューティーズ』(76)。
草分け的なミニシアターの最初の大きな役割は、長年、埋もれていた海外(特にヨーロッパ)の名作やカルト的な作品の発掘だった。当時の日本のロードショー館ではハリウッドのメジャー作品の上映が中心。マイナーなインディペンデント映画やヨーロッパ映画も、たまにホール上映されることはあったものの、一般の商業館にかけるのはむずかしく、映画の多様性への道のりはまだまだ遠かった。
しかし、状況に風穴をあけたのが新しい劇場のオープンだった。六本木の俳優座シネマテンが3月、シネマテンと共同公開も多かった渋谷のパルコ・スペース・パート3が9月、新宿のシネマスクエアとうきゅうが12月。
81年の東京の繁華街に、ミニシアターという新しい文化が芽ばえたのだ。

◉いまや不夜城と化している六本木でも、夜の映画館は新鮮だった
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。