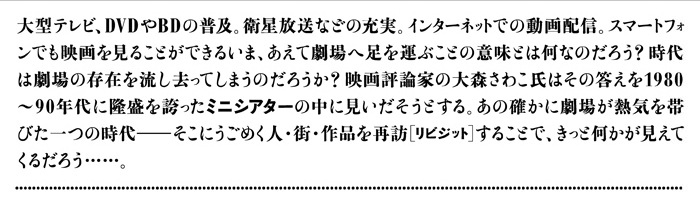シャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)で30週連続上映という記録的な大ヒットとなり、この劇場の歴代興行記録ナンバーワンとなった『ベルリン・天使の詩』(87)はフランス映画社配給だったが、その後もこの会社と劇場の蜜月時代は続いていく。
『ベルリン・天使の詩人』は1988年4月に封切られたが、同年の12月24日に封切られたのが『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』(85)。翌89年の6月23日まで25週間連続上映となって1億6800万円の収益を上げ、シャンテの歴代興行収入の2位となる。
この作品を振り返って、かつてシャンテシネの副支配人だった高橋昌治東宝専務取締役(取材時。現・東宝不動産社長)はこう語る。
「『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』はいい映画でしたね。とにかく、写真〔作品〕を見て、やってみよう、と思いました。タイトルが分かりにくいのが難点ですが、主役の子供はかわいいし、見た後、気持ちいいし、すごくいいと思いました。監督はスウェーデンのラッセ・ハルストレムで、当時は日本では知られていませんでした。ただ、新しい監督の方がこちらも先入観なく見ることができましたし、スウェーデンという国籍も特に気になりませんでした。その後、この監督はアメリカに渡って話題作も撮っていますね」
主人公は病気の母親を持つ12歳の少年、イングルマルで、母親の病気が悪化した後、彼は田舎の叔父の家に預けられる。最初は不安を抱えているが、次第に周囲と打ち解けていく。特にサッカーやボクシングが得意で少年のような容姿の女友達との関係に、思春期の少年・少女の性に対する微妙な意識がよく出ている。また、イングマルは死ぬことも知らずに宇宙に打ち上げられてしまったライカ犬に共感していて、そんな犬の人生よりも自分の人生の方がマシと考える。心温まる可愛い作品でありながら、生と死、あるいは性へのめざめという人間の根源的な問題も入っていて、哲学的な眼差しもある(年齢を重ねた後に再見すると、この部分がより深く理解できる)。
ハルストレムはこの一作で世界的に評価され、アカデミー賞の監督賞候補にもなった。その後は『ギルバート・グレイプ』(93、ジョニー・デップ、レオナルド・ディカプリオ主演)から近作の『砂漠でサーモンフィッシング』(11、ユアン・マクレガー主演)まで良心的なドラマを手がけるハリウッドの職人監督として活躍している。
同じ北欧(デンマーク)出身のビレ・アウグスト監督が父と息子の絆を描いた感動作『ペレ』(87、マックス・フォン・シドー主演)もシャンテでヒットした。シャンテ歴代19位の興行成績で、89年6月から14週の上映となった(興収7500万円)。ハルストレム同様、その後はハリウッドスターを起用して、『愛と精霊の家』(93、メリル・ストリープ主演)、『レ・ミゼラブル』(98、リーアム・ニーソン主演、ミュージカルではなくドラマ版)などのメジャーな作品を撮った。
シャンテ公開時には名前を知られていなかったヨーロッパの監督たちはこの劇場にかけられたヒット作を経て国際監督に成長した。

◉『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』は、インディペンデント・スピリット賞外国映画賞、ゴールデングローブ賞最優秀外国語映画賞などを受賞した
フランス映画社は他にも、映画ファンの間で知られるようになる監督たちの初期の代表作を配給している。アメリカのジム・ジャームッシュもそうした監督のひとりで、80年代半ばにスバル座で『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(84)や『ダウン・バイ・ロー』(86)を成功させた後、シャンテで彼の新作を次々に上映してきた。高橋専務は振り返る。
「彼の作品には固定ファンがついていましたね。スバル座での『ストレンジャー・ザン・パラダイス』はなんともいえない作品でした。いい映画という表現は違うかもしれませんが、とにかく、新鮮さがありました。シャンテで初めて上映したのは『ミステリー・トレイン』(89)ですね。他にも『ナイト・オン・ザ・プラネット』(91)や『コーヒー&シガレット』(91)、『デッドマン』(95)なども上映していて、お客様も入りました。『デッドマン』の時は監督とジョニー・デップの来日会見も話題になりましたね」
この会見(95年、帝国ホテル)には私も行ったが、初来日のデップは、まだ本当に若かった。近年の会見ではサービス精神を発揮しているデップだが、この時は言葉が少なく、タバコをやたらと吸っていた(つっぱっていた?)。そんな無口なデップのかわりに饒舌なイメージとはほど遠かった監督がひとりで喋っていた。いま思えば控えめな宣伝費のミニシアター公開のために(監督はともかく)ハリウッドの人気スターが来日することは珍しかったので、シャンテ公開作の中でも特に忘れがたい会見になっている。
当時、ジャームッシュ作品は次々にシャンテで上映され、興行成績も好調だった。89年12月から13週間上映の『ミステリー・トレイン』はシャンテの歴代興行14位で興収8400万円。80年代以降、日本の会社が海外の映画作りに積極的に投資するようになったが、この作品は日本のビクターが投資したことが話題になり、長瀬正敏や工藤夕貴など日本の俳優も出演。エルヴィス・プレスリーゆかりのメンフィスめぐりを描いた3話のオムニバスで、音楽好きで知られるジャームッシュらしい企画だ。
92年4月25日から21週上映の『ナイト・オン・ザ・プラネット』は歴代4位で興収1億4500万円。ニューヨークやパリなど5つの都市のタクシーの運転手の日常をジャームッシュらしいひょうひょうとしたユーモアで見せてくれる。トム・ウェイツの音楽のねじれた感覚もいい。
95年9月14日から14週上映の『デッドマン』は歴代15位で興収8400万円。旅人(ジョニー・デップ)の死への船出が詩的なタッチで描写されたモノクロ作品で、ニール・ヤングがインスト音楽を担当。
近年のジャームッシュ作品は別の会社の配給だが、昨年12月に上映されたヴァンパイア映画『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライブ』(13、ティルダ・スウィントン主演)もシャンテでの公開。まさに“ジャームッシュ劇場”となっている。

◉ジム・ジャームッシュといえばシャンテ、という一時代が確かにあった
フランス映画社とシャンテの蜜月時代を代表する監督は他にもいて、台湾のホウ・シャオシェンやギリシャのテオ・アンゲロプロスの代表作もこの劇場で封切られた。こうした監督たちについて高橋専務は回想する。
「フランス映画社は監督たちと家族的なつきあいを続けていました。『悲情城市』(89)のホウ・シャオシェン〔候孝賢〕などは帝国ホテルに泊まり、近くにある中華料理店の慶楽が好きで、そこで食事をしていました。テオ・アンゲロプロスとも、ひじょうに家族的なつきあいでしたね。ご夫妻と世界の監督や製作者とのおつきあいがあって、彼らの作品の公開窓口はフランス映画社が担当することが多かった気がします。ただ、監督が成功すると、この会社のお金では動かないという問題もありました」
難解なイメージで知られるギリシャの巨匠、故テオ・アンゲロプロス監督の場合、『霧の中の風景』(88)、『こうのとり、たちずさんで』(91)、『ユリシーズの瞳』(95)等、多くの作品がシャンテで上映されたが、特に興行成績がよかったのが『永遠と一日』(98)。シャンテ歴代22位で99年4月から13週の上映で興収7000万円となった。この作品は『ベルリン・天使の詩』の名優、ブルーノ・ガンツ主演で、不治の病に侵された老詩人が難民の少年と過ごす最後の一日が圧倒的な映像美で綴られる。
台湾のホウ・シャオシェンの監督作では1940年代後半の激動の歴史の中で生きる人々を描いた大作『悲情城市』(若きトニー・レオン主演)がシャンテの歴代11位。90年4月から17週間上映され、興行収入9700万円。ホウ・シャオシェン作品は89年に『恋恋風塵(れんれんふうじん)』(87)と『童年往事/時の流れ』(85)も日本公開されているが、『悲情城市』は興行的にも決定打となった。
「あの頃、シャンテはいいものをやりたいという思いしかなく、作品の国籍は気にしていませんでした。『悲情城市』はアジア映画としてははしりだったと思います。監督も当時は今ほど有名ではありませんでした。そして、『悲情城市』が大ヒットした時、フランス映画社の社長、柴田さんに、この監督は他にもいいのがあるんです、と言われて、旧作だった『風櫃(フンクイ)の少年』(83)や『冬冬(トントン)の夏休み』(84)も上映しました。これも『悲情城市』の成功があってのことです。この作品はけっして分かりやすい内容ではなかったのですが、なかなかいい映画でしたよね。この後、この映画の舞台が観光の名所になったようです」
90年のシャンテはまさに“ホウ・シャオシェン・イヤー”となり、4月の『悲情城市』に続いて、『風櫃の少年』が7月、『冬冬の夏休み』が8月に上映されている。

◉台湾出身のホウ・シャオシェンは、「台湾ニュー・シネマ」の代表監督の一人。80年に監督デビューした
フランス映画社は才気ある女性監督の作品も積極的に配給してきた。ニュージーランド出身のジェーン・カンピオンの場合、『エンジェル・アット・マイ・テーブル』(90)が日本での彼女の出世作となった。世間とうまく折り合えず、精神障害で入院生活を送ったこともある実在の女流作家(ジャネット・フレイム)の魂の変遷を風変わりな映像で見せる。ヒロイン役を演じた新人女優のケリー・フォックスに、当時、取材する機会があったが、とても頭のいい女優で、きびきびした受け答えが印象に残った(その後はダニー・ボイル監督のデビュー作『シャロウグレイブ』〈94〉でも好演を見せている)。
「『エンジェル・アト・マイ・テーブル』は渋い映画ですが、興行はよかったです。そこでカンピオンの次の監督作『ピアノ・レッスン』(93)をみゆき座で上映するはずでした。ヴェンダース監督の『パリ、テキサス』(84、フランス映画社配給)がみゆき座で成功したので、それと同じやり方です。ところが、日劇プラザの番組に穴があいたので、急きょ、この作品を入れたらまずまずの結果が出ました」
93年のカンヌ映画祭パルムドールに輝き、翌年のアカデミー主演女優賞(ホリー・ハンター)や脚本賞等を受賞した『ピアノ・レッスン』はこうして有楽町の拡大公開系の劇場、日劇プラザにかけられ、特に女性層から熱い支持を得た。ピアノをめぐる官能的なラブストーリーで、ニュージーランドの原始的な風景とマイケル・ナイマン作曲の美しいピアノ曲が完璧なる融合を見せる。
シャンテの約2倍の客席(554席)を持つ東京の中心的な劇場のひとつ、日劇プラザでの上映はフランス映画社にとって大きなチャレンジとなった(残念なことに同社の副社長、川喜多和子さんはこの作品を見た93年カンヌ映画祭の直後、6月に53歳で他界。映画はその8カ月後の2月に日本公開となった)。
フランス映画社が日本の土を踏むチャンスを与えた女性監督には英国のサリー・ポッターもいて、ヴァージニア・ウルフ原作の『オルランド』(92)はシャンテの歴代16位となる。93年9月から14週の興行で、興収は8300万円となっている。主演は英国人のティルダ・スウィントン。当時は知る人ぞ知る的な存在ながら、今ではオスカー女優となり、『ベンジャミン・バトン 数奇な運命』(08)などハリウッド大作でも活躍中だ。『オルランド』では男と女のふたつの性を持ち、時空を超えて生きる主人公を好演していた。
英国つながりでいうと、90年代にフランス映画社配給で話題を呼んだ英国映画にはマイク・リー監督のカンヌ映画祭パルムドール受賞作『秘密と嘘』(96)もあった。奔放な青春時代を送ったヒロインが、かつて自分が生んだ娘と再会する物語で、ホロ苦い人生の果てにある希望が胸に迫る作品。来日会見の時、監督はいかにも英国風の辛辣な発言を飛ばしていて、その“こってり味”のユーモアが生きた代表作となる。こちらはシャンテの興行歴代7位の作品で、96年12月から18週上映された(興収1億840万円)。
また、ベルギー出身のジャコ・ヴァン・ドルマルもフランス映画社が発見した監督のひとりで、ミシェル・ブーケ主演の『トト・ザ・ヒーロー』(91)はシャンテの歴代12位で、91年12月から14週上映(興収8600万円)。孤独な老人、トマの過去の思い出と願望まじりの妄想が不思議なテイストで映像化される。ドルマル監督は2作目の人間ドラマ『八日目』(96、ダニエル・オートゥイユ主演)も話題を呼んだ。
アメリカのインディペンデント系監督ではハル・ハートリーの『シンプルメン』(92)、『愛・アマチュア』(94)などもフランス映画社が配給してシャンテにかけた。この監督、線の細さは気になったが、知的な才気はあった。
個人的に忘れがたいのはアキ・カウリスマキ監督が英国で撮った佳作『コントラクト・キラー』(90)。人生に絶望していた中年男(ジャン=ピエール・レオ)の再生がカウリスマキお得意のとぼけたユーモアとブルース音楽をまぶして描写され、人生の味わいがあった。
フランス映画社作品はそのレーベル、BOW(ベスト・オブ・ザ・ワールド)シリーズの名前に偽りなしの多彩な作品群をシャンテシネで展開してきた(シャンテ誕生前は、シネ・ヴィヴァン・六本木でジャン=リュック・ゴダール、アンドレイ・タルコフスキー、ビクトル・エリセ等の話題作を上映していた)。
高橋専務が語るところによれば、フランス映画社の宣伝会議も本当に熱のこもったものだったという。
「社長の柴田さんのディスカッションは、本当にすごかったです。デザイナーの小笠原正勝さんがポスターを作って持っていくわけですよ。それを見て、僕なんか、いいんじゃないと思うんですが、柴田さんは首を縦にふらない。ときどき、ぶつぶつと言うだけで、半日にらめっこです。ふたりのいるところに川喜多和子さんが入ってきたら、また、大変で……。こちらがいたたまれないくらいすごい口論もありました。でも、結果的にはみなさん、本当に立派な仕事をされていたと思います」
シャンテシネはフランス映画社が才能を見出した新しい作家たちの新作だけではなく、オープニング作品の『紳士協定』(47、東宝東和配給)のように旧作の名作発掘の路線も考えていた。
「上映する作品は古典的なものもやっていこうという姿勢があったのですが、どこから手をつけたらいいのか、わかりにくいわけです。そこで東宝東和に写真(=作品)を探してもらうという流れもありました。マルセル・カルネ監督の『天井桟敷の人々』(45)などは柴田さんの会社でリバイバル上映していただけました。ただ、D・W・グリフィス監督の『國民の創生』(1915)などの公開はあまりうまくいきませんでした。東宝東和にお願いして権利をクリアして上映したんですが……」
やがて、シャンテシネはフランス映画社の新作や映画史上の名作の上映に加え、大手の洋画会社がかかえる個性的な作品も上映するようになり、さらなるヒット作を生み出していく。
(この項つづく)

◉現在は3つのスクリーンで「TOHOシネマズシャンテ」として営業している
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。