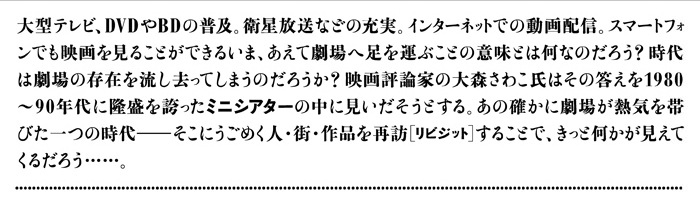ミニシアターの歴史を振り返ると、2つの特筆すべき年がある。ひとつは1981年。この年、六本木の俳優座シネマテン、パルコスペースパート3、シネマスクエアとうきゅうの3つの劇場がオープンし、ミニシアターの創生期となった。もうひとつの記念すべき年は1987年。この年、銀座・日比谷地区に3つのミニシアターがオープンした。銀座一丁目にある銀座テアトル西友、日比谷のシャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)、銀座の四丁目交差点の近くにあるシネスイッチ銀座だ。
ミニシアターのスタートに関しては新宿や六本木にやや遅れをとっていたものの、洋画の封切りについては銀座・日比谷地区は東京の先進地域だった。今では新宿や渋谷などでも銀座・日比谷地区と同時に封切られるが、かつては銀座周辺の映画館だけが、特権的な力を持っていて、他の地域に先駆けて洋画を公開していた。ロードショーという言葉が初めて使われたのも東宝の日比谷映画街だ。人気歌手フランク永井の57年の大ヒット曲として知られる「有楽町で逢いましょう」は日比谷の近くにあった有楽町のデパート、そごうのキャンペーンソングだったが、その中には「きょうのシネマはロードショー かわすささやき」という歌詞も出てくる。かつて銀座・日比谷地区の映画館にはワンランク上の感触があった。これについては作家の山口瞳がこんなエッセイを残している。
「それはすべて戦後のことだった。僕が家の近くの小便臭い映画館ではなく、映画館らしい映画館で初めてアメリカ映画を見たのは日比谷映画劇場だった。十歳であったと思う。叔父が東宝に勤めていたので無料で見た。(中略)東宝というのはモダンで明るい感じがした。色調で言えば白である。日比谷映画は白っぽかった。館内に一歩足を踏み入れただけで胸が躍った」(『新東京百景』、88年、新潮社刊)
日比谷映画街の周辺には映画館だけではなく、帝国劇場、宝塚劇場のように華やかな劇場や高級感漂う帝国ホテルもあった。
「日比谷映画劇場、有楽座、東京宝塚劇場、帝国ホテル、日比谷公園、帝劇、東京会館、丸ビル、日劇といったあたりは日本の文化の中心であるような気がしていた。文化の中心というよりは、ハイカラの中心と言ったほうがいいかもしれない」(前掲書)
山口は当時の映画街についてそう回想する。
吉見俊哉が87に刊行した都市論『都市のドラマトゥルギー 東京・盛り場の社会史』(弘文堂刊、後に河出文庫に収録)によれば、銀座周辺が“ハイカラの中心”となったのは、関東大震災の後で「『銀座』とは同時代の人々にとって、何よりもまず『近代的(モダン)』なるものの象徴としてあったのだ」。この本に引用された安藤更生の文章では、銀座は「日本の都市生活の檜舞台」と定義され、「銀座は幸福な街である。ここには美しきもの、新しきもの、香り高きもの、高雅なもの、選ばれたものが集められている」とも記されている。
こうした文献からも分かるように銀座や日比谷周辺にあった映画館には豪華な印象があったし、また、多くの映画会社がこの地域に集まることで“映画の街”となっていた。邦画系の映画会社、東宝や東映は丸ノ内線の銀座駅から歩いていける距離にあるし、松竹は東銀座の駅の近くにある。洋画系の会社にしても、洋画配給の草分け的な東宝東和もかつては銀座(現在は永田町)にあった。また、70年代までは銀座の晴海通りの側のフィルムビルに20世紀フォックス、MGM、ワーナー・ブラザースといった洋画メジャー会社が入っていた。また、日比谷の映画街に近いリッカー会館の中には『E.T.』(82)などの大ヒットを放ったCIC(後のUIP、今は解散)が入っていた。
私が映画業界に入った80年代はマスコミ試写もほとんどが銀座・日比谷周辺で行われていていたので、ある試写会が終わった後、近くの別の試写室へかけこむというのがおなじみのパターンだった(今は試写室が六本木、神谷町、東銀座などに分散している)。また、90年代くらいまではスティーヴン・スピルバーグやトム・クルーズなどハリウッドの人気監督や大物スターの記者会見も日比谷の帝国ホテルで行われることが多かった。新しい洋画を日本で最初に見ることができて、海外から来日するホットな映画人にも会える。銀座・日比谷周辺はまさに“映画の檜舞台”に思えたものだ。

◉今でも日比谷には往時の雰囲気を偲ばせる映画館のいくつかは姿を残すが上映作品の傾向や劇場の役割は変わってきている
しかし、ことミニシアターについて銀座はやや後発となった。銀座地区で最初のミニシアターとなったのは銀座テアトル西友で、シネ・ヴィヴァン・六本木(83年オープン)やシネセゾン渋谷(85年オープン)を成功させていたセゾングループが87年3月に開館。コーエン兄弟の『ブラッド・シンプル』(84)ではじまりを迎え、六本木や渋谷に遅れた形で銀座地区に参入した。
日比谷に東宝系のミニシアター、シャンテシネ1・2ができたのは同年10月だったが、この劇場の場合はミニシアターだけが単独でつくられたわけではなく、あくまでも銀座・日比谷地区の映画館のリニューアルと合わせた形で完成した。この頃、東宝だけではなく、松竹、東映など日本の大手会社が結集して有楽町のビル、マリオンに新しい映画館をつくった。マリオンは朝日新聞の本社ビルと東宝の日劇の跡地に建てられ、阪急や西武などの大手デパートも入っていた。本館は84年に開館して評判を呼び、別館の方は87年に完成する。
この年の『朝日新聞』(8月24日夕刊)にこんな記事が掲載されている。
「東京・有楽町駅前のマリオンと、晴海通りを隔てて目と鼻の先の日比谷に、それぞれ豪華な設備を整えた映画館が合わせて4館、この秋に加わり、『リッチな気分で見られる映画街』にイメージチェンジする。(中略)その中で、10月に完成する有楽町マリオンの増築ビルには、世界でも珍しいコンピューター制御のシャンデリアつきがお目見えするなど、映画館の『豪華志向』に拍車がかかりそうだ。新たに出来る映画館のうち2つは、『からくり時計』などで都心の新名所になった有楽町マリオンの東隣に増設中。(中略)一方、JR線の線路をはさんで日比谷側の旧日比谷映画、有楽座の跡地に東宝が建設を進めている有楽町一丁目の『シャンテビル』(地上18階、地下4階)の2-4階には、『シャンテシネ1』(226席)と、4-6階部分に『シャンテシネ2』(同)が出来る。両館とも小規模ながら、音響効果とゆったりした座席に重点を置いている」
文中に登場する日比谷映画や旧有楽座は84年に閉館(有楽座などは場所を変えて後に再オープン)。銀座・日比谷の映画館地図が塗り替えられていったわけだが、そんな中でシャンテシネはアート系映画の受け皿としてスタートし、小ぶりながらも歴史に残る多くの傑作・秀作を世に送り出すことになる。
手元にこの劇場の歴代ヒット作のリストがある。トップテンを拾うと、1位『ベルリン・天使の詩』(公開年=88年、配給=フランス映画社、興行収入=2億2500万円、上映=30週)、2位『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』(88年、フランス映画社、1億6800万円、25週)、3位『イル・ポスティーノ』(96年、ブエナビスタ、1億4800万円、19週)、4位『ナイト・オン・ザ・プラネット』(92年、フランス映画社、1億4500万円、21週)、5位『フル・モンティ』(97年、20世紀フォックス、1億3600万円、25週)、6位『日の名残り』(93年、コロムビア映画、1億1700万円、17週)、7位『秘密と嘘』(96年、フランス映画社、1億800万円、18週)、8位『セックスと嘘とビデオテープ』(89年、ヘラルド映画、1億600万円、16週)、9位『英国王のスピーチ』(11年、GAGA、1億100万円、20週)、10位『チョコレート』(02年、GAGA、9700万円、18週)という順番になっている(興行収入は100万円未満切り捨て)。
作品の個性はそれぞれ異なるが、どの作品も質が高い。また、その下を見ると11位の『非情城市』(90年、フランス映画社、9700万円、17週)から22位の『永遠と一日』(98年、フランス映画社、7000万円、13週)まで、1位から22位までの間に12本ものフランス映画社の配給作品がランクインしている。これには改めて驚いた。ジム・ジャームシュ(『ナイト・オン・ザ・プラネット』)やテオ・アンゲロプロス(『永遠と一日』)など、多くのすぐれた監督たちを発掘し、彼らの作品を育てることで、ミニシアターファンに強い印象を残してきた会社だが、作品のクオリティだけではなく、興行に関しても大きな功績を残していた。もちろん、あくまでも200席ちょっとの劇場での話で、ハリウッド系のメジャーな洋画や大手会社の邦画のように巨大なヒット作とはならないが、小さい規模ながらも、それを必要とする心ある映画ファンたちにしっかりと作品を届け、ヒット作を連発していた。“質”で勝負できて、それがしっかり数字としても反映されていた。そんな時代の幸福感がこのリストからは伝わる。
幸福な時代の記憶をとどめる人に会うため、日比谷の東宝本社を訪ねることになった。劇場のはじまり、大ヒット作『ベルリン・天使の詩』のこと、シャンテが育てた人気監督たちについても聞きたい! そんな期待感を胸に日比谷にあるビルの入り口へと足を踏み入れた。(この項つづく)

◉TOHOシネマズシャンテと、東宝日比谷ビルが囲む一角
80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。